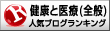思春期(特に男)には、他人に語れない苦悩がある。それは恐ろしく醜く、芸術の対象にすらならない。生理学風に言えば、急に活発となる性腺からの男性ホルモンの作用だろう、動物的で暴力的で見境のない性的衝動が突き上げる。
突き上げるのは性的衝動だけではない。既存の権力、うるさい年長者、縛り付ける因習や法律、放置された社会悪、これら全てを潰そうとする強い破壊衝動が、全能感と同時に突き上げてくる。この衝動と陶酔がロックと共鳴する。
でも自分は非力だ。分かっている。それらの衝動は満たされずに虚しく終わるだろう。世の中、自分がいてもいなくても、何も変わらない。それでも衝動は時に強く突き上げてきて、それを制御しようとして少年は苦しむ。
その時の蓋となるのが、母親だ。自分を生んでくれた母には無条件で頭が上がらない。その創造と共生の目が、破壊と征服に狂う雄としての自分の逸脱した行動を抑制する。母を悲しませたくなくて、親不孝を思いとどまる。
しかし、蓋を飛ばしてしまう奴もいる。やってみて、その現実に向き合って、自分の愚かさを改めて思い知る。憧れの偉人も助けてくれない。そして、後悔と自虐と恐怖で胸がいっぱいとなり、謝罪と甘えの涙を流しながら、思いは母に回帰するのだ。
あの虚無感の雲から稲妻のように突き上げてくる衝動の化け物。多くの少年は、それに戸惑い、悪魔に脅されながらも逸脱せずに過ごす。しかし、一歩間違えば、「やっちまった」少年となり、戸惑いと悲しさの淵に落ちたかもしれないのだ。
残ったのは何か。確かなReality(現実)は、ここに自分があることだ。Nothing really matters(何もたいしたことはない)、Any way the wind blows(どうせ風は吹くんだ)。現実は続き、この先も生きる・・最後に淡い希望を感じさせて、曲は終る。(了)