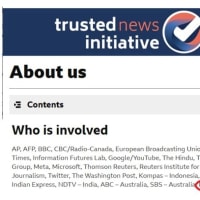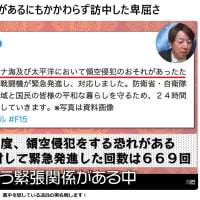(朝日新聞の社説 朝日新聞DIGITAL 2013年08月15日00時42分)
戦後68年と近隣外交―内向き思考を抜け出そう
人気バンド、サザンオールスターズの新曲は「ピースとハイライト」。暑い夏の人々の心をつかんだ歌はこう始まる。
――何気(なにげ)なく観(み)たニュースでお隣の人が怒ってた/今までどんなに対話(はな)してもそれぞれの主張は変わらない/教科書は現代史をやる前に時間切れ/そこが一番知りたいのに何でそうなっちゃうの?――
今の私たちに最も近いはずなのに見えにくい。そんな現代史を考えるために、1945年8月15日の「お隣」で何が起きていたかを振り返ろう。
■無関心の原点
その日までの日本は、アジアで広大な領域とさまざまな民族を支配する帝国だった。
掲げた看板は「大東亜共栄圏」。日本が欧米からアジアを解放すると唱え、太平洋戦争を「大東亜戦争」と呼んだ。ところが敗戦とともに、日本は、その東亜圏との関係を断ち切ってしまった。
作家の故・堀田善衛はその日を上海で迎えた。ラジオで聞いた終戦の詔勅に「怒りとも悲しみともなんともつかぬものに身がふるえた」と記している。彼の周りには、日本と親しい中国の文化人が多くいた。ところが詔勅は、もっぱら日本本土向けで、アジアに対しては「諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス」と片づけていた。
堀田はそんな宣言を「薄情」「エゴイズム」と感じた。(ちくま学芸文庫「上海にて」)
日本の敗戦の過程に詳しい国文学研究資料館助教の加藤聖文さんは「当時の政府は国体(天皇制)護持という内向きの議論ばかりしていた。詔勅はその素(す)の気持ちが表れた」とみる。その結果、当時は日本人だったはずの朝鮮人や台湾人の保護責任もあっさり放棄した。アジアを率いる指導者面しておいて突然、知らん顔をする。それが68年前の実相だった。
■国際環境は変わる
戦前戦中の日本の責任を問う声がアジアから湧き起こるまでには時間がかかった。それは、戦後の秩序の影響が大きい。
米国とソ連が世界を二分した冷戦の時代。日本と台湾、韓国は米国陣営に組み入れられた。さらに日本は高度成長にも入った。資金と技術で隣国を助ける優位を保つことができた。70年代までに終えた近隣との国交正常化は、冷戦構造の産物でもある。日本への賠償請求権は消えたとされたが、当時の近隣諸国では外交に民意が反映される状況ではなかった。
やがて冷戦は終わる。グローバル経済の時代、韓国は先進国へ、中国は大国へと成長した。日本と国力の差がなくなるにつれ、歴史問題に由来する大衆感情が噴き出している。 日本はもはや軍国主義は遠い遺物と思っても、隣の民衆にとっては戦争を問う時が今やってきた。そこには歴史観の時差ともいえる認識のズレがある。
日本の政権も無策だったわけではない。93年に宮沢喜一政権は従軍慰安婦をめぐる「河野談話」を出し、95年に村山富市首相は「植民地支配と侵略」の談話でアジアに謝罪した。それを歴代内閣は引き継いできた。
しかし安倍首相は当初、継承を明言しなかった。加えて「侵略の定義は定まっていない」とも発言し、波紋を呼んだ。
中韓首脳にとって、歴史は、貧富の格差など国内問題から国民の目をそらす手段にもなる。だとしても、そんな思惑に対抗するかのように日本もナショナリズムの大衆迎合に走ってしまえば悪循環は止まらない。
安倍政権の歴史認識については、同盟相手の米政府も懸念している。侵略の史実を否定すれば、日本の歴史認識に対する国際世論の風当たりは強まる。
■他者を知ることから
他の国々との関係を忘れた内向きな思考に拘泥していると、外交の幅を狭め、自縄自縛の隘路(あいろ)に迷い込む。それは、戦争の失敗から日本が学んだはずの教訓だったが、今もその思考の癖から抜け出せていないのではないだろうか。
多くの日本人にとって、戦争の光景とは、日本各地の惨状だろう。この夏に公開されている映画も、日本を舞台にした「風立ちぬ」「終戦のエンペラー」「少年H」。どれも平和の尊さを人間味豊かに描いている。
私たち国民が実体験した戦争を語り継ぐのは、当然の責務である。ただ、そこで立ち止まらず、想像をアジア、世界へと広げたい。あの戦争の被害に国境はなかったのだから。
昨年夏の朝日新聞の世論調査によると、「日中戦争は日本による侵略戦争だったと思いますか」との問いに日本では「そう思う」との答えが52%、「そう思わない」が31%。中国では99%が「そう思う」と答えた。
この認識の溝は、あまりに深い。だが、そこが出発点だ。アジア抜きに日本の未来は語れない今の時代こそ、じっくり考えよう。「お隣」は今なおなぜ、怒り続けているのか、と。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
朝日新聞は、他の国々との関係を考えず内向きな思考に拘泥し、外交の幅を狭め、軍部を煽り戦線拡大させ、国民からは戦意高揚の歌を公募し軍部と一体となって戦争遂行に邁進した。
「国々との関係を忘れた内向きな思考に拘泥していると、外交の幅を狭め、自縄自縛の隘路(あいろ)に迷い込む。それは、戦争の失敗・・・・」とは、そのまま朝日新聞に当てはまる。日本を自縄自縛の隘路に誘い込ませた元凶であるにもかかわらず自らの戦争責任に目を瞑り、被害者然として振舞っている。
「(朝日新聞を除く)“私”たち国民が実体験した戦争を語り継ぐのは、当然の責務である。」よくもこのような事がいえるもんだ。鉄面皮、恥を知れ!
戦前、戦意高揚のため朝日新聞が公募した歌は数々あるが、その一つ「アッツ島血戦勇士顕彰国民歌」は、「ああ皇軍の神髄に 久遠の大義生かしたる 忠魂のあとうけ継ぎて 撃ちてし止まむ醜の仇」と “玉砕”を美化し勇ましい。
「アッツ島血戦勇士顕彰国民歌」(1943年)
陸軍省報道部推薦歌曲、朝日新聞社撰定、作詞:裏巽久信、作曲:山田耕筰
1943(昭和18)年の5月29日、山崎保代大佐(死後2階級特進、中将)率いるアリューシャン列島のアッツ島守備隊2500名余は、圧倒的な火力を持つ米軍1万の猛攻の前に全滅した。大本営は5月30日、この敗北を「玉砕」と盛大に発表した。これ以降、「全滅」を「玉砕」と表現するようになった。
アッツ島の山崎部隊の玉砕を受け、玉砕を称え戦意高揚を目的として幾つかの歌が作られた。最も有名なのが、朝日新聞社が企画した「アッツ島血戦勇士顕彰国民歌」である。
朝日新聞では5月31日の玉砕報道の直後、陸軍省後援のもと6月3日に「アッツ島山崎部隊勇士記念国民歌募集」として、歌詞の公募を発表した。その記事には、
「アッツ島に壮烈鬼神を哭かしむる最後の突撃を敢行、玉砕した山崎部隊長以下二千数百勇士の血戦に一億国民の血涙感謝を捧げその青史不朽の武勲と赫々たる皇軍精神を永く後世に伝ふべき、記念国民歌を左記により広く募集する。」
「厳粛、荘重、雄渾なる大国民歌たるべき事。特に在来の平凡なる修辞法にとらはれず、真に国民的感激と米英撃滅の熱情をこめた日本的の国民叙事詩たる事を望む。」 などといった表現が見える。
審査に当たったのは、陸軍省から報道局長の矢萩那華雄少将(審査委員長)、堀田中佐、山ノ内大尉。山口陸軍軍楽隊隊長。情報局から井上司文芸課長、井上清芸能課長。矢部放送協会業務局長。山田耕筰。百田宗治。公募軍歌の作詞者は学校の教師公務員がおおかった。
【歌詞】
1.刃も凍る北海の
御楯と立ちて二千余士
精鋭こぞるアツツ島
山崎大佐指揮を執る
2.時これ五月十二日
暁こむる霧深く
突如と襲ふ敵二万
南に邀へ北に撃つ
3.陸海敵の猛攻に
わが反撃は火を吐けど
巨弾は落ちて地を抉り
山容ために改まる
4.血戦死闘十八夜
烈々の士気天を衝き
敵六千は屠れども
吾また多く喪へり
5.火砲はすべて摧け飛び
僅かに銃剣、手(て)榴弾
寄せ来る敵と相搏ちて
血汐は花と雪に染む
6.一兵の援、一弾の
補給を乞はず敵情を
電波に託す二千キロ
波頭に映る星寒し
7.折柄拝す大御言
生死問はぬ益良雄が
ただ感激の涙呑む
降りしく敵の弾丸の中
8.他に策なきにあらねども
武名はやはか穢すべき
傷病兵は自決して
魂魄ともに戦へり
10.ああ皇軍の神髄に
久遠の大義生かしたる
忠魂のあとうけ継ぎて
撃ちてし止まむ醜の仇
(毎日新聞の社説)
社説:8・15を考える 積み重ねた歴史の重さ
毎日新聞 2013年08月15日 02時30分
第一次大戦を描くバーバラ・W・タックマンの「八月の砲声」に、次のような一節がある。「人間はなんの希望ももたずに、これほど大規模で苦痛に満ちた戦争に耐えられるものではない。
希望−それは戦争は極悪非道であるがゆえにふたたび起こるはずはないとする期待、また、なんとか結着を見るまで戦い抜けば、より秩序ある世の中の基礎が築かれるという希望である」(山室まりや訳、筑摩書房・ちくま学芸文庫)
「希望」は「幻滅」に変わり、第二次大戦が起きる。平和を壊すのはたやすい。保つには過去の歴史に学び、政治リーダーが大局的な判断力を持つことが必要だ。
◇希望を幻滅に変えるな
日中戦争と太平洋戦争の死者は日本人で310万、アジアで2000万以上とされる。戦争は政治の延長だとか、戦いは人間の本性だという声があるが、戦争は非人間的な残虐行為にほかならない。
あのような愚行を再び犯さないこと。それが、平和への希望を託して死んでいった死者たちへの、私たちの世代の義務だろう。戦後、私たちは平和の果実を食べてきた。だがいま、その基盤が崩れる不安が漂っている。
直接の原因は、中国、韓国との絶え間ない摩擦である。
中韓両国の政府や政治家が歴史や領土をめぐる問題で反日ナショナリズムを過度にあおれば、日本人の国民感情を刺激する。両国には、その抑制を強く求めたい。
一方、私たちの側にも歴史認識のゆらぎが生じている。象徴的なのが、中国への侵略についての議論であろう。
大平正芳首相のブレーンだった故猪木正道元防衛大学校長は「軍国日本は、一九三一年から中国への露骨な侵略を開始した」「中国への侵略行為が国際社会のきびしい非難にさらされた背景には、戦争、平和、侵略などに関する人類の価値観がはっきり転換したという重大な変化があった」(「軍国日本の興亡」)と書いた。こうした認識が、穏健保守の標準的な態度だった。
第1次安倍政権下で始まり、3年前にまとまった日中歴史共同研究の報告書も、「日本軍の侵略」という言葉を使っている。そして日本は既に、戦後50年の村山談話と戦後60年の小泉談話で、2度にわたって「侵略と植民地支配」への反省と謝罪を世界に表明している。
それが第2次安倍政権になって、侵略を明確に認めようとしないかのような発言が政治家から出てきた。さらには村山談話の見直し論が語られたりする。A級戦犯をまつる靖国神社への首相参拝の是非も、再び国論を二分させている。
背景には、戦争責任や戦後処理をあいまいにしたまま、新しい世代が政治の主流を占めるようになったことも影響しているだろう。先の参院選の当選者の平均年齢は52.4歳。70代以上はわずか7人(5.8%)である。58歳の安倍晋三首相をはじめ、戦争を知る政治家は、いまやほとんどいなくなった。
だが、戦後70年近くたっても過去の総括が定まらず、歴史の評価が政権によって左右されるような国は、健全だとはいえない。
◇村山談話は外交資産だ
村山談話は、中韓だけでなく日本が占領したアジア全体を対象にしたものだ。独善的なナショナリズムを排し、国際協調を促進するという未来志向の誓いも盛り込んでいる。これは、世界からの信頼をつなぎとめる外交資産である。見直せば、東南アジアなど日本に好意的な国々の支持まで失いかねない。
安倍首相は2年後の戦後70年に新たな談話を出すというが、侵略と植民地支配という言葉を消すようなら無用な誤解を招く。3度目の談話を考えるよりも、過去の談話を変えないことが大切だろう。
靖国神社の首相参拝も、戦争の総括にかかわる問題だ。
敗戦国の日本は、戦争責任者の責任追及と処罰を戦勝国による東京裁判にゆだねた。その象徴がA級戦犯だ。そして東京裁判を受諾した1952年発効のサンフランシスコ講和条約は、尖閣と竹島の領有権主張の根拠にもなっている。
私たちは靖国神社や領土の問題を考える時、内向きの論理ではなく、そうした世界史的、客観的な視点で判断する必要がある。
最近、韓国で日韓合意に反する賠償判決が相次いだ。中国は尖閣付近の領海侵犯を繰り返す。歴史と外交をからめ、過去の積み重ねを一方的に変えようとする動きだ。だからこそ日本は、歴史の事実と解釈をゆるがせにしない姿勢を維持し、相手に歴史カードを使わせない賢明さを持たなければならない。
安倍首相が目指す集団的自衛権の解釈変更の問題なども、日本が過去を謙虚に受けとめる姿勢を明確に示してこそ、内外の疑念を招かず論議できるのではないか。
あの戦争が終わり、68年目の暑い夏がめぐってきた。私たちは敗戦と引き換えに平和と繁栄を手にし、戦後の国際秩序を受け入れた。8・15はその出発点だった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
毎日新聞が政府や軍部の国策遂行に加担した「あのような愚行を再び犯さないこと。それが、平和への希望を託して死んでいった死者たちへの、私たちの世代の義務だろう。」というが、1930年代は朝日新聞と毎日新聞の2大紙体制であり、情報局と組んで国論誘導に果たした役割は絶大であった。自らの戦争責任を明確にすることが不可欠である。
「靖国神社の首相参拝も、戦争の総括にかかわる問題だ。敗戦国の日本は、戦争責任者の責任追及と処罰を戦勝国による東京裁判にゆだねた。その象徴がA級戦犯だ。」そうだ!戦争の総括はまだ終っていない。A級戦犯の戦争遂行に加担した毎日新聞の戦争責任も総括しなければならない。
「戦争責任者の責任追及と処罰を戦勝国による東京裁判にゆだねた。」と言うのは適切ではない。国民が国の指導者やママスコミの戦争責任を糾弾しなしよう戦勝国に擦り寄って生き延びたのが大手マスコミである。「私たちは敗戦と引き換えに平和と繁栄を手にし、戦後の国際秩序を受け入れた」が中国は、これを受け容れない。どうするのだ。
毎日新聞が、戦意高揚のために公募した歌も数々あるが、そのうちの一つに「大東亜決戦の歌」がある。
この歌は、日米開戦翌日の1941年12月9日に東京日々新聞と大阪毎日新聞が「興国決戦の歌」の名で公募した歌である。12月12日、閣議で戦争の名称が「大東亜戦争」となった事を受け、「大東亜決戦の歌」に改められた。
13日の締め切りまでに2万5千篇の詩が集まり、そこから伊藤豊太のものが撰ばれた。その後ただちに海軍軍楽隊に作曲を依頼し、19日に発表される。当時としては異例の速さでの製作であった。
「起つや忽ち撃滅の 勝鬨挙る太平洋」という冒頭句から、まさに開戦当時の雰囲気が伺われる。この歌に駆り立てられて国民は戦場に赴いた。毎日新聞は「大東亜決戦の歌」の歌詞を読み直し、何を叫んでいたか思い出すべきだ。戦に負けたら自己の哲学も当然に変えるべきものなのか。今は、昔の勇ましいさと全く逆の“平和”の旗手だ。この歌の文言を見れば、商売のための“変心”か正義感の発露か判断に苦しむ。ペテン師のようだ。
「大東亜決戦の歌」 (1941年)
情報局推薦 大阪毎日新聞社・東京日々新聞社募集
作詞:伊藤豊太 作曲:帝国海軍軍楽隊
【歌詞】
1.起つや忽ち撃滅の
勝鬨挙る太平洋
東亜侵略百年の
野望をここに覆す
いま決戦の時きたる
2.行くや激しき皇軍の
砲火は叫ぶ大東亜
一発必中肉弾と
散つて悔いなき大和魂
いま尽忠の時きたる
3.見よや燦たる皇国の
歴史をまもる大決意
前線銃後 一丸に
燃えて轟くこの歩調
いま興国の時きたる
4.いざや果さん十億の
アジアを興す大使命
断固膺懲堂々と
正義貫く鉄石心
いま決戦の時きたる
毎日新聞が公募した歌の二つめ「空襲なんぞ恐るべき」も勇ましい。
国民歌「空襲なんぞ恐るべき」 1941(昭和16)年発表。
防空総司令部、陸軍省、 東京日々・大阪毎日新聞社撰定
作詞:難波三十四(防衛総司令部参謀 陸軍中佐)
作曲:飯田信夫
【歌詞】
空襲何んぞ恐るべき
護る大空鉄の陣
老いも若きも今ぞ起つ
栄えある国土防衛の
誉れを我等担いたり
来たらば来たれ敵機いざ
空襲何ぞ恐るべき
つけよ持場にその部署に
我に輝く歴史あり
爆撃猛火に狂うとも
戦い勝たんこの試練
来たらば来たれ敵機いざ
空襲何ぞ恐るべき
護る大空鉄の陣
老いも若きも今ぞ起つ
栄えある国土防衛の
誉れを我等担いたり
来たらば来たれ敵機いざ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
毎日新聞は「空襲なんぞ恐るべき」と歌を公募し国民の戦意高揚に腐心したが、昭和19年、20年になると日本列島の主要都市は米軍のB-29の焼夷弾攻撃でことごとく灰燼に帰した。それでも毎日新聞は「栄えある国土防衛の誉れを我等担いたり 来たらば来たれ敵機いざ」と歌い続けたくらいだから、終戦終結や和平を模索する報道などするはずが無い。戦後、多くの共産党員が毎日新聞に入ったから偏向報道が多いのだろう。
朝日新聞、毎日新聞社は共同で戦意高揚を目的とした歌を公募した
「爆弾三勇士の歌」と「肉弾三勇士の歌」
爆弾三勇士の歌は、爆弾三勇士(肉弾三勇士)をテーマにした軍歌である。大阪毎日・東京日日(現在の毎日新聞)と大阪朝日・東京朝日(現在の朝日新聞)は1932年(昭和7年)2月28日、それぞれ三勇士をテーマとした歌の懸賞募集を開始した。3月10日の締め切りで、毎日は84577通の応募があり、朝日は124561通の応募があった。
毎日新聞は題名を「爆弾三勇士の歌」とし、当時慶應義塾大学の教授をしていた与謝野鉄幹(寛)が詞を書いた。朝日新聞は題名を「肉弾三勇士の歌」とし、長崎日日新聞で経済記者をしていた中野力の作品が選ばれた。
【歌詞】
一、廟行鎮の敵の陣
我の友隊すでに攻む
折から凍る如月の
二十二日の午前五時、
命令下る正面に
開け歩兵の突撃路
待ちかねたりと工兵の
誰か後をとるべきや
三、中にも進む一組の
江下 北川 作江たち
凛たる心かねてより
思うことこそ一つなれ
四、我等が上に戴(いただ)くは
天皇陛下の大御稜威(おおみいつ)
後に負うは国民の
意志に代われる重き任
五、いざ此の時ぞ堂々と
父祖の歴史に鍛えたる
鉄より剛(かた)き「忠勇」の
日本男子を顕すは
六、大地を蹴りて走り行く
顔に決死の微笑あり
他の戦友に遺(のこ)せるも
軽(かろ)く「さらば」と唯一語
七、時なきままに点火して
抱き合いたる破壊筒
鉄条網に到り着き
が身もろとも前に投ぐ
八、轟然おこる爆音に
やがて開ける突撃路
今わが隊は荒海の
潮の如く躍り入る
九、ああ江南の梅ならで
裂けて散る身を花と成し
仁義の軍に捧げたる
国の精華の三勇士
十、忠魂清き香を伝え
長く天下を励ましむ
壮烈無比の三勇士
光る名誉の三勇士
真珠湾攻撃の号外
大手マスコミ、戦争は商機、飯の種
マスコミは“加害者”であった
戦前の日本では新聞紙法によって新聞は検閲の対象となっており、軍や政府は記事差止命令や写真の不掲載といった措置を取ることができた。大正時代まではこうした環境下にあっても露骨な言論統制が行われる機会は少なかったが、満州事変以後、軍の政治に対する発言力が増大すると、正面から政府や軍を批判する記事の掲載が困難となった。とりわけ、日中戦争の勃発とそれに続く国家総動員法の制定はそれを決定づけた。この点は唯一の放送機関であった日本放送協会(NHK)も同じだった。
しかしながらマスコミは自らを“被害者”というのは当たらない。1932年3月1日の満州国が建国に際して、読売新聞ほか全国132社は「満州国独立支持共同宣言」を掲載したのは何よりの証拠である。マスコミは読者獲得のため戦意高揚の記事を載せるだけでなく、新聞は政府の外交政策を「弱腰」「軟弱外交」という形で糾弾し、対外強硬論を煽り、開戦を主張するなど、国民を開戦支持に導く役割も果たした。
戦争とメディアを考えるとき、“言論弾圧”という言葉は、メディアが被害者であるということを強く訴える立場で使われている。1930年代初頭の左翼言論に対する弾圧はともかく、37年の日中戦争以後の言論統制を、言諭弾圧と表現することは適切ではない。マスコミは、“加害者”であった。
14942年6月5日、主力空母4隻とその艦載機を失ったミッドウエーの大敗を転機として、軍令部は参謀本部や東條英機総理兼陸相に対してさえ大敗の事実を隠蔽するようになった。 言論統制の結果もあるが、日本のラジオ・新聞などは大本営の発表をそのままに過大な偏向報道した。国民の多くは国際情勢ならびに戦況の実態を知らされず、戦争が長期化する大きな要因となった。
戦争が長期化すると、政府や軍の強硬派に迎合する形で戦争の完遂や国策への協力を強く訴える記事を多く掲載するようになった。検閲の元締めである情報局は戦争後期、緒方竹虎や下村宏など朝日新聞や日本放送協会の元幹部が総裁を務めていた。情報局の指導もあったがマスコミ、作家や芸術家などが軍部に協力した。
新聞に対しても政府は不当な圧迫を加えたと信する向もあるが、軍部は勿論情報局、内務省等は友好的協力的だった。新聞は必ずしも「統制に嫌々協力させられた」わけではなく、積極的に戦争推進に回った。
サア二年目モ勝チ抜クゾ 
暁教育図書株式会社「昭和日本史7 戦争と民衆」29頁(発行 昭和52年5月15日)
戦争は絶好の商機、この機会を見逃すな!
戦場に関する報道は兵士の生死はその家族や親戚等の最大の関心事だったから、戦争報道は商品としての新聞にとって最大の見せ場であり、売込み時である。戦争様様であった。国の戦争だから足を引っ張ったりはすべきではなかったとしても、報道内容は相当に行き過ぎがあった。大企業体であればあるほど、この商戦の機会を見逃すなどできぬ相談というのが、当時の新聞業界の実情だった。
新聞は、戦争中に部数を大いに増やした。新聞各紙は満州事変あたりから急に部数を伸ばし始め、あとは右肩上がりに一直線である。メディアというのは、戦争との相関性が非常に強い企業だが、これほど極端な業界は珍しい。
戦前・1931年、毎日新聞(東京日日と大阪毎日)は243万部、朝日新聞(大阪朝日と東京朝日)が144万部で、新聞界は2大紙体制だった。この時点で読売新聞は27万部だったが、1938年には100万部を超えるなど、戦線の拡大に伴って三大紙体制が築かれていった。
大阪朝日と東京朝日が1940年「朝日新聞」に統合。1942年には読売と報知が合併して「読売報知」になったほか、東京新聞(都新聞と国民新聞)、日本産業経済新聞(中外商業新報と日刊工業新聞など東日本の経済紙)、産業経済新聞(日本工業新聞と西日本の経済紙)、中部日本新聞(新愛知と名古屋新聞)が誕生した。1943年には東京日日と大阪毎日が「毎日新聞」に統合された。
地方紙の一部には、露骨な軍の嫌がらせに対して、個人としても、また社としても抵抗したものがあったが、大新聞にはそうした姿勢がなかった。満州事変以降はまるで縛られたようになり、二・二六事件でも全く抵抗しなかった。
抵抗できなかったということではない。新聞は自分の主張を持てという意味の「対立意識」が明治の終わりから薄れて、万人の好みに合わせた「商品新聞」になっていった。「どうしてもここだけは譲れない」という線がなくなってしまったのだ。
戦火の拡大に伴って軍部は次第にメディア統制がうまくなっていった。太平洋戦争では、大本営の発表体制ができあがり、客観的な流れをつかむことは難しくなった。ところが、新聞社は「VOA(ボイス・オブ・アメリカ)」など海外の短波放送をひそかに聞いていた。しかし、これを紙面に反映させることはなかった。大本営発表はウソだとわかっていながらそのまま報道していた。その責任は大変重い。弾圧で倒産や自殺に追い込まれたものも少しはいたが、三 大紙は力があった。協方すれば抵沈できたはずだ。新聞の原点を忘れたのだ。
戦後、ドイツ、フランスではファシズムに協力したメディア人は生涯、メディア界から追改された。これに比べ、マスメディアの幹部は、読売新聞の正力松太郎のように戦犯容疑者として収監されたり、公職追放されたりしたが、復帰は早かった。日本のメディアは其の戦争責任を“死者”即ち“旧軍”に押し付け被害者然として振舞っている。
【関連記事】
● 8月15日は終戦記念日、「旧軍が悪かった」,「東条英機が悪かった」と戦争被害者ぶってすむ話ではない! 2010-08-19 22:52:19