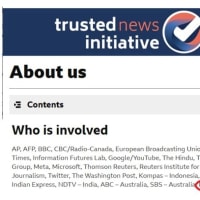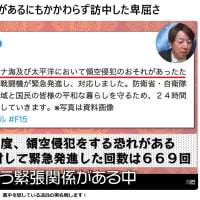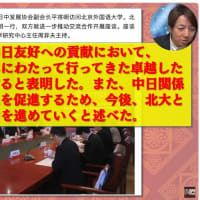二重橋前ではしゃいでいた中国人の若者
権威は うつろいやすい
第2次大戦の前と跡で、日本人の精神構造がすっかり変わってしまったと、しばしば言われる。戦前の日木人は、国家に忠誠を尽くす、天皇陛下に忠誠を尽くすという点で、ひとつの大きな目標をその人生に与えられていたようにみえる。もちろん、日本国内の学校教育もまたそうした国家的統一目標に向かって全てのカリキュラムが作成されていた。
日本では明治維新以降太平洋戦争の敗北まで天皇と皇后の写真を御真影といって、宮内省から各学校に貸与され、奉安殿に教育勅語と一緒に保管された。元旦、紀元節、天長節及び明治節には講堂の正面に飾り、児童生徒、職員一同が遙拝するよう教育されたのである。
占領軍が進駐する前、天皇に敗戦を詫びる人 
敗戦の報を聞いて佇む人

『別冊 週間読売9月号 実録 太平洋戦争 慟哭編』読売新聞社 昭和49年
天皇は“神”から ただの “人” になった
日本が第二次世界大戦で敗れると、1945年9月27日に昭和天皇がアメリカ大使館にマッカーサーを訪ねた際に、米陸軍の写真班によって昭和天皇とマッカーサーが並んで撮影された。この写真は政府により発禁処分にされたが、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が撤回させて9月29日の新聞各紙の朝刊の紙面に掲載された。昭和天皇がマッカーサーの隣に直立不動の姿勢で普通に新聞に写っていることに国民は大きな衝撃を受けた。
天皇自身も「過激な風潮が段々と強まり、道義の感情はとても衰えて、そのせいで思想に混乱の兆しがあることは、常に利害は同じくし喜びも悲しみも共に持ちたいと願う。私とあなたたち臣民との間の絆は、いつもお互いの信頼と敬愛によって結ばれ、単なる神話と伝説とによって生まれたものではない。」との詔書(『人間宣言』)を発表し、“神”であることを否定された。
昭和天皇と腰に手をあてたマッカーサー

この写真が新聞に掲載され後では、皇居前広場で陛下に詫びる人が徐々に減っていった。
これと同じようなことがバスの乗客の反応にも見られた。戦争中、皇居前を走るバス路線があった。そのバスに乗っている乗客たちは宮城の前を通るとき、車掌の指示によって、必ず宮城の二重橋に向かって礼拝するようになっていたそうである。 敗戦後も、そのバスは同じ賂線を走っていたが、もはや車掌は、誰に対しても何もいわず、客もまた二重橋に向かってお辞儀をしなくなっていった。
つまり、天皇の権威が たった一蹴の出来事によって 虚ろに去っていったのである。日本人における権威とは、このように儚く、うつろいやすい。
最高権力者 答礼する マッカーサー
写真撮影 ディミトリー・ポリア、編者杉田米行
『GHQカメラマンが撮った 戦後ニッポン』アーカイブス出版株式会社 2007年
皇居前広場をうめつくす占領軍
1947年7月4日米国独立記念日、皇居前広場で行なわれたパレード、マッカーサーの閲兵を受ける米第一騎兵師団 
『開封された秘蔵写真 GHQの見たニッポン』 太平洋戦争研究会編 2007年
昭和天皇とマーカット少将
マッカーサーは占領行政を遂行するため天皇を最大限利用した 
写真撮影 ディミトリー・ポリア、編者杉田米行
『GHQカメラマンが撮った 戦後ニッポン』 アーカイブス出版株式会社 2007年
上に従順、自主性を抑制
世界の大部分の国は必ず大きな宗教的な変革を経験している。しかし、日本においては、社会の上層部だけでなく、社会の最下層を含めたすべての国民が参加するような形での革命が行なわれなかったのである。
日本の社会においては、社会を構成する上部の人たちの下す命令によって全ての国民はおとなしい羊のように従順に、その示される道に従って左へ、右へと、歩きつづけてきたのである。戦国時代も江戸時代も、明治維新も第二次世界大戦の敗戦に伴う国家の一大変革も、“上”から与えられたものを受け入れたのである。
“泣く子と地頭には勝てぬ”、“藪をつついて蛇を出す”という諺がある。自分自身で黙ってジッとしていればいいのに、余計なことをして愚をおかす必要はないのである。何もしないでいたほうがいいのでだ。 自分からは積極的に動かなければ “雉雑も鳴かずば撃たれまい” し無難である。自分の意見はなるべく隠して主体性をなくして黙っていればいいのである。
“出る杭は打たれる” し、 "もの言えば唇寒し秋の風“ のご時勢である。自分の主体性を発揮することなく なるがままに任せ安全な生活を送れればいいのだ。“長いものには巻かれろ” という羊のように生きてきたのが、敗戦後の日本の生き方だった。
美徳を否定
敗戦前のように国に対して日本国民全体が生命・財産を提供するという考え方は、現在からみれば非常に歪められ、あまりにも極端な、奇怪な形に捻じ曲げられた愛国心であったと考えられるかもしれない。しかしながら、当時の日本人は一人ひとりが、自分が大日本帝国に対して尽くすべき義務と責任感を感じとっていたように考えられるのである。だから、それはむしろ “美徳” と呼んでも差し支えないとさえ思う。
たくさんの歪められた考え方が「軍国主義」の名のもとに存在していたと言われるが、戦前の日本人の抱いた考え方の中にはたくさんの美徳が含まれていた、ことも認めないわけにはいかない。しかし、敗戦によって、これら全ての日本的美徳が軍国主義という名のもとに抹殺されてしまった。
国づくりも人づくりも何もかも米国仕込みになった
今上天皇と常陸宮 
写真撮影 ディミトリー・ポリア、編者杉田米行
『GHQカメラマンが撮った 戦後ニッポン』 アーカイブス出版株式会社 2007年
米国の占領政策は成功した、残ったのは精神の空虚さ
米国の占領政策が成功したのは、日本人の 権威に対するうつろいやすい体質、主体性の欠如や従順な体質も関係している。
日米の権力関係を示す写真
桜田門を出る米軍部隊
警備のMPに制止される米兵 
写真撮影 ディミトリー・ポリア、編者 杉田米行
『GHQカメラマンが撮った 戦後ニッポン』アーカイブス出版株式会社 2007年
マッカーサーは絶対的権力を持ってが、直接統治をしなかった。彼は天皇以上の権威は持たなかった。順調に統治するためには天皇を排除するより協力して統治したほうがよいと判断したのだろう。
天皇の「人間宣言」で『過激な風潮が段々と強まり、道義の感情はとても衰えて、そのせいで思想に混乱の兆しがある』と述べられていることを考えると、1945年9月27日の会談で、両者は “協力して統治する” と暗黙の合意をしたのであろう。
敗戦によって米占領軍が日本に駐留し、全てを “改革” した。憲法は米国により “与えられ” た。憲法は思想や言論の自由を建前として、一応保障しているが、占領行政の実態は、プレス・コードに基づく検閲があり、米国の占領政策に支障があるものは発禁処分となった。
あらゆるものが変わり、後に残ったのは、精神の巨大な空虚さだけであった。日本の伝統的な宗教である仏教も無力化され、神道的な考え方も非常に力が弱くなってしまった。国家的道徳基準を教えていた学校教育にも、巨大な空虚さが支配するようになった。
8月15日、東京・九段下の道路で行なわれた左翼のデモ隊とこれに反発する集団の罵声も、日本人の心のなかに存在する空虚さの表れとみられる。そこには、“集団”という大きな“体”をもっている反面、“小さな頭脳”しか持っていないのである。少数のアジテーターによって多数の人間が盲目的に従っているのは、健全なことではない。
デモに参加する人たちは、個人としては非常に善良な人々であろう。しかし同時にこれらの善良な人々は、このデモ行進やこれに対する過激な反発が社会的にどのような悪影響を与えているかということについては全く考えていないかのように見える。左翼や労組が行なうデモと これに反対するもの行動は、瞬間的な激情を伴うものである。参加した者は、そこに人生の目的を発見できると、錯覚しているのかもしれない。
彼らの内心にひそむ空虚さは、それが大きい分だけ、そうした真撃な生活態度に耐え切れなくさせてしまい、過激な行動に走るのである。
8月15日、終戦の日に、宗教色のない千鳥が淵の戦没者墓苑に行く人が少なく、神様を祀っている靖国神社へ行く人が多いのは、精神の空虚さと関係があるのであろう。
権威はうつろいやすい
傘寿をむかえた父は、今年もまた戦没者の冥福を祈られた 
長男は、親の思いを知っているのか知らぬのか
幸せ一杯、バカンスから帰られた
【関連記事】
「税金泥棒 !」と罵声を浴びた雅子さん 天皇皇后両陛下は多忙です (1)
孫は、しっかり育てられているようで一筋の光明が見える

皇居前広場、今は 中国人の観光スポット
敗戦の報に佇む人がいた皇居前広場は、中国人の観光客でにぎわっていた。8月15日、この広場にいた日本人といえば、警備の警察官と、見物に来ていた数名の人、記念写真を撮る写真屋と私で、10名もいなかった。69年前、この広場で敗戦を詫びたひとがいたとは、誰も知らない。今は、日本人も来なくなった。猛暑で炎天下、この広場に来るよりもバカンスですごすほうが賢いのだ。主がいないから来てもしょうがないか。 権威はうつろいやすい。 かわりに中国人の観光客で賑わっていた。
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  *
* 
* 
* 
*