イエスの活動は、結局、キリスト教という新たな宗教を生み出す原動力となり、それはローマ帝国に拡がり、後の西洋世界を規定することになった。
なぜそういう事態になったのか――キリスト教誕生の経緯と発展の理由――については、とても手に余る問題で、私ごときが何かを論じることはできない。また、そのうちのどの部分までが「イエスの意図したこと」あるいは「イエスが責を負うべきこと」なのかという問題も、なかなか難しい問題である。
ただ、非常に重要だと思われる点を、二つだけ、指摘してみたい。
それは、終末論と殉教である。
* * *
イエスとその復活をめぐる宗教運動は、伝統ユダヤ教から、一つの大きな「ビジョン」を受け継いでいた。「終末論」である。
そもそもユダヤ教の終末論は、「唯一の神を正しく信仰していれば、神は救世主を遣わし、ユダヤの民を世界に冠たる民族にしてくれるだろう」という、非常に政治的なものだった。近隣の強国に虐げられ、支配されてきた弱小民族の痛切な恨みがそこにはこめられている。
だが、その「メシアの到来」は次第に「世界の大変動」のビジョンとなっていく。それはある意味当然で、イスラエルが「支配者」になるためには、戦争や大異変が起こり、諸国が崩壊する必要がある。宗教的な表現を取れば、「天変地異が起こり、その中にメシアが降臨し、義なるユダヤ人のみを救ってくれる」ということになる。このビジョンは、ユダヤ人国家の状態が悲惨であればあるほど、より強烈な「世界崩壊」のビジョンとなっていく。
まさにこのビジョンこそ、イエス時代のパリサイ派を始めとする多くのユダヤ教徒が切望し、到来を予感していたものだった。バプテスマのヨハネの「神の国が近づいたぞ」という雄叫びは、お説教ではなく、身も震える脅しであり、また希望の光でもあった。
ユダヤの政治的終末論とは別に、一般的な「終末のビジョン」というのは、おそらく人類に普遍の「元型」的なものと言えるものだろう。古代ユダヤ教でも「ノアの方舟」に見られる世界終末の神話は、後の政治的終末論とは異なる位相のものとしてあった。
この世界が、激烈な天変地異によって、あるいは巨大な戦乱によって、またたく間に崩壊する――この幻像は、世界史のあちこちに出現する。日本の天の岩戸神話も、仏教の「末法思想」も、ある意味では終末論と言えるだろう。イスラームももちろん、ユダヤ教の正統な継承者として、終末論を持っている。近年ではノストラダムスの予言とか、オウム真理教の終末論もあった。現在も、2012年の何たらとか「アセンション」とかいう風説がたくさんあって、それも終末論の一種のようである。
これは人類の「集合的無意識」の中に蓄えられた「ビジョン」であるのかもしれないし、あるいは「神の想像力」の一部なのかもしれない。ノアの神話のように、神様が「あちゃ、こりゃ失敗作だ」とお思いになって、「ガラガラポン」をやりたくなる衝動を一瞬お抱きになることも、ないとは言えまい(笑い)。
だが、初期のキリスト教ほど、「終末論」を強調した宗教も珍しい。そして、2000年経って、その到来がえらく間延びしてしまい、ほとんど疑問になっても、いまだにキリスト教では「終末論は信仰の中核」と捉えている(あまり表立っては言い立てないが)。私は以前、キリスト教の学者さんに「最後の審判って、引っ込められないんですか」と(無礼にも)聞いたことがあるが、答えは「それを取り下げるとキリスト教は成立しない」というものだった。
繰り返しになるが、受難物語をまともに受け取ると、イエスは「自分は殺されるが、三日後に雲のようなものに乗ってこの世に戻ってくる」と予言した。そして確かにイエスは死後、信奉者たちに姿を現わしたが、「雲のようなものに乗って、世界を裁きにやってきた」わけではなかった。一部の信奉者たちは、「あれは予行演習みたいなもので、もう一度、本当にこの世に審判をしにやってくる」と考えた。これが正統キリスト教に取り込まれ、パリサイ派の肉体復活論も取り込んで、「最後の審判」の教義となった。キリストは再来する。その時こそ、正しい信仰は「善し」とされ、報われる。
初期キリスト教徒にとっては、これは疑う余地のないビジョンだったようである。パウロは、「主自らが、指令の呼び声と、筆頭の御使いの声と、神のラッパの響きと共に、天から降りて来られ、そしてキリストにある死者たちが最初に甦り、次いで私たち生き残っている者たちが、死者たちと一緒に、雲の中へと運び挙げられて、空中で主と邂逅するであろう」(Ⅰテサ4:16-17)と言ったが、それは教義を読み上げているのではなく、本当にそう思っていたに違いない。「その時がいつ来るかは誰にもわからない」というのは、福音書にも頻出し、初期キリスト教徒たちも真剣に思っていた信条である。「いつ来るかわからない」は、わからないということではなく、もうすぐ来る、という切迫感の表現である。
こうした切迫感が、社会状況によって強められることはもちろんである。実際、イエスの時代は、ヘレニズム+ローマ帝国支配という圧倒的力と、伝統的民族社会との軋轢が高まっていた。今で言えば、グローバリズム+商業主義と地域社会との軋轢に似ているかもしれない。その中にいれば、人々は自分の生活の根底がいつ崩れるやもしれないという不安を抱く。これは経済的な問題だけではなく、人間の自己規定というか、アイデンティティに関する問題でもある。イエスの思想の一部が人々に受け入れられたのは、すでに古代ユダヤ教の律法や神観念では人々は安定的な自己規定を獲得できない、そういった社会状況が生まれていたという要因もある。
そして結果論から言って、ユダヤ社会は実際に「終末」を迎えようとしていた。バプテスマのヨハネやイエスの予言が、ユダヤ戦争やバル・コクバの乱(第二次ユダヤ戦争、132-135年)によるユダヤ社会の壊滅を予知したものかどうかは明言できない。この状況を敷衍していくとそうなるぞという知性的な判断だったのかもしれない。ともあれ終末は見えていた。それはユダヤ人の望む「成就の日」ではなく、2000年にわたる悲劇の始まりである「絶望の日」だったわけだが。
この実際に起こった「絶望の日」が、人々の宗教観にどういう影響を与えたのか、それは、イスラエル在住民/離散ユダヤ人、伝統ユダヤ教徒/キリスト教徒、ユダヤ人/非ユダヤ人といった立場によって様々だったろう。ただ、これを「終末の失敗」ではなく、「近未来の終末の予兆」として捉えた人々もいたことは確かである。「望むような終末は来ない」という絶望ではなく、「この先に真の終末が来る」という希望が、生き残った。
「終末」は、しばしば「希望」でもある。
そもそもユダヤ教の終末論は、強国に支配されるユダヤ民族の怨嗟の中から生まれてきた。この苦しみ、屈辱はやがて終わる。その希望であった。
どうにもならない苦しい状況の中にある時、働いても働いても生活苦から抜けられない時、あるいは働くことすら拒否される時、人は社会を憎悪し、その崩壊を願う。悪が勝ち誇り、善きものが踏みにじられる時、それを許しているこの世の秩序が崩れ去ることを望む。
終末の先に何があると考えるかは、また様々である。もっと素晴らしい世界が訪れるという希望。これはより善き現世への夢であり、純粋な終末論というよりは革命の夢でもある。イエスもまた、「神の国を来たらせる」夢を抱いていた。初期キリスト教徒たちもキリストの再来を信じ、熱望した。11世紀のキリスト教徒は「千年王国」の幻想を抱いて十字軍の狂気に走った。そしてついでに言えば、ユダヤ人のカール・マルクスは19世紀に「労働者による革命」と「理想的な共産社会」の到来を説いた。だが、言うまでもなく、革命はめったに起こらない。また革命の夢は常に正しいわけではなく、新しい秩序はしばしば地獄となる。
一方、新秩序の夢や可能性が薄らぎ、終末が純粋な終末として夢想されることもある。その先には何があるともわからない。この世ならぬ冥界へすべてが移行するのか、あるいは死滅・無となるのか、それははっきりしないまま、「この世が終わる」ことだけが夢想される。
そんな思想があるものかと思われるが、それは強烈なビジョンとしてしばしば人々に抱かれる。現世に対する呪詛であり、断念であり、否定である。
この「純粋な終末のビジョン」は、西洋世界の精神性・宗教性に、大きな影響力を持ったのではないかと私は思う。このビジョンは、キリスト教世界の中で、あるいはひょっとしてイスラーム世界の中でも、歴史を通じて何度も甦り続けた。そして、それは重要な役割を果たした、と。
いささか乱暴な言い方だが、西洋世界は、現世が大好きである。彼らは肉体が好きであるし、個人的存在としての自己が好きである。そうした西洋世界の「現世への執着」に、強烈な毒をぶち込むのが、「終末のビジョン」だった。現世にこだわり、執着し続ける彼らに、「この世ならぬもの」を意識させるためには、「もうすぐこの世が終わるぞ」という冷水が必要だった。
もちろん西洋世界にも「反現世」の宗教思想はあった。ユダヤ教のエッセネ派、グノーシス、カタリ派……。だがそれは決して主流にはならないものだった。
キリスト教はその中で、「終末のビジョン」をかざすことで、何とか「神」への回路をつなごうとした。「最後の審判」とそれを基盤にした「罪」の強調が、キリスト教の中核であったことは否めない。
終末論は悪しき思想である。それは大衆の怨嗟(ルサンチマン)や破壊衝動を煽動する。時には狂気的な行動を誘発する。終末とか断罪=地獄墜ち宣告とかいう、つまり恐怖によって教えを広めるのは悪しき宗教である。
イエスは終末論に加担した。それは彼の落ち度である。
「俺は雲に乗って再来する」と本人が言ったのか、物語なのかはわからない。当人が言ったら言ったで、また、そうでなくて物語が勝手にできてしまったのならそれができてしまったで、彼はそれを悔いているだろう。
* * *
ある言い方をすれば、イエスは衆目の前で、無残に死んで見せた。それは復活によって生命の永遠性を示すためだったとしても、その無残な死に方は、多くの人に衝撃だった。
その衝撃を中和するために、「犠牲」の神学や、「仮現論」などの説も生まれた。
そして、イエスに「倣って」積極的に死を選ぶ「殉教者」も生まれた。
殉教の問題は難しい。当事者のリアリティをなかなか把握することができないからである。
ただ、一口に殉教と言っても、いくつかパターンはある。
第一は、教団に参加して活動していたところを、弾圧者に襲われて死ぬ。そのことを予測していながら、あえてそれを避けようとしない。自発的な死ではないが、これも広い意味では殉教である。
第二は、棄教すれば赦免されるという場面で、それを拒み、殺されるという場合。これがまあ、一番正統な殉教なのかもしれない。
第三は、むしろ積極的に命を捨てることで、宗教思想や組織を守ろうとする場合。イスラームの自爆テロなどを考えればわかりやすいかもしれない。場合によっては単に「理想に燃えた戦士としての死」ということになるのかもしれない。
殉教を倫理的に評価できるのかどうかは、正直、よくわからない。一日本人としては、「宗教にそこまで重要性を与える必要はない」という感じもするが、たとえば、「ある倫理的悪をなさないとお前を殺す」と言われた場合、殺されることを選ぶというのもひとつの立派な選択となる場合もあるだろう(これは殉教とは言えないか?)。
ただ、「信じて命を捨てたら、一気に天国へ行ける」という思いに駆られて死ぬのは、どうも違うだろうとも思う。求道(霊的成長)というものは、骨の折れる一歩一歩の自己鍛錬によるものであって、一気に死んで天国へ行くというのは、その放棄であり、エゴであるようにも思われる。
実際、初期のキリスト教徒たちには、こういう思いで殉教を選んだ人々もいたようである。ただ、貧窮や奴隷的抑圧にあえぐ人たちがそれを選んだ場合、それを非難するのも無体な気がする。
いろいろ難しい問題があるが、イエスが「さあ殺せ」というような死に方をしたことで、それに「倣った」人も多くいたことは否定できないだろう。やはり教祖の生き方はお手本であり、それと同じ生き方をしようとするのは自然である。
殉教の美化は、やはり不当なことであるように思われるし、それによって歴史上、必要以上の殺戮が生まれたことは否定できないのではないだろうか。
なぜそういう事態になったのか――キリスト教誕生の経緯と発展の理由――については、とても手に余る問題で、私ごときが何かを論じることはできない。また、そのうちのどの部分までが「イエスの意図したこと」あるいは「イエスが責を負うべきこと」なのかという問題も、なかなか難しい問題である。
ただ、非常に重要だと思われる点を、二つだけ、指摘してみたい。
それは、終末論と殉教である。
* * *
イエスとその復活をめぐる宗教運動は、伝統ユダヤ教から、一つの大きな「ビジョン」を受け継いでいた。「終末論」である。
そもそもユダヤ教の終末論は、「唯一の神を正しく信仰していれば、神は救世主を遣わし、ユダヤの民を世界に冠たる民族にしてくれるだろう」という、非常に政治的なものだった。近隣の強国に虐げられ、支配されてきた弱小民族の痛切な恨みがそこにはこめられている。
だが、その「メシアの到来」は次第に「世界の大変動」のビジョンとなっていく。それはある意味当然で、イスラエルが「支配者」になるためには、戦争や大異変が起こり、諸国が崩壊する必要がある。宗教的な表現を取れば、「天変地異が起こり、その中にメシアが降臨し、義なるユダヤ人のみを救ってくれる」ということになる。このビジョンは、ユダヤ人国家の状態が悲惨であればあるほど、より強烈な「世界崩壊」のビジョンとなっていく。
まさにこのビジョンこそ、イエス時代のパリサイ派を始めとする多くのユダヤ教徒が切望し、到来を予感していたものだった。バプテスマのヨハネの「神の国が近づいたぞ」という雄叫びは、お説教ではなく、身も震える脅しであり、また希望の光でもあった。
ユダヤの政治的終末論とは別に、一般的な「終末のビジョン」というのは、おそらく人類に普遍の「元型」的なものと言えるものだろう。古代ユダヤ教でも「ノアの方舟」に見られる世界終末の神話は、後の政治的終末論とは異なる位相のものとしてあった。
この世界が、激烈な天変地異によって、あるいは巨大な戦乱によって、またたく間に崩壊する――この幻像は、世界史のあちこちに出現する。日本の天の岩戸神話も、仏教の「末法思想」も、ある意味では終末論と言えるだろう。イスラームももちろん、ユダヤ教の正統な継承者として、終末論を持っている。近年ではノストラダムスの予言とか、オウム真理教の終末論もあった。現在も、2012年の何たらとか「アセンション」とかいう風説がたくさんあって、それも終末論の一種のようである。
これは人類の「集合的無意識」の中に蓄えられた「ビジョン」であるのかもしれないし、あるいは「神の想像力」の一部なのかもしれない。ノアの神話のように、神様が「あちゃ、こりゃ失敗作だ」とお思いになって、「ガラガラポン」をやりたくなる衝動を一瞬お抱きになることも、ないとは言えまい(笑い)。
だが、初期のキリスト教ほど、「終末論」を強調した宗教も珍しい。そして、2000年経って、その到来がえらく間延びしてしまい、ほとんど疑問になっても、いまだにキリスト教では「終末論は信仰の中核」と捉えている(あまり表立っては言い立てないが)。私は以前、キリスト教の学者さんに「最後の審判って、引っ込められないんですか」と(無礼にも)聞いたことがあるが、答えは「それを取り下げるとキリスト教は成立しない」というものだった。
繰り返しになるが、受難物語をまともに受け取ると、イエスは「自分は殺されるが、三日後に雲のようなものに乗ってこの世に戻ってくる」と予言した。そして確かにイエスは死後、信奉者たちに姿を現わしたが、「雲のようなものに乗って、世界を裁きにやってきた」わけではなかった。一部の信奉者たちは、「あれは予行演習みたいなもので、もう一度、本当にこの世に審判をしにやってくる」と考えた。これが正統キリスト教に取り込まれ、パリサイ派の肉体復活論も取り込んで、「最後の審判」の教義となった。キリストは再来する。その時こそ、正しい信仰は「善し」とされ、報われる。
初期キリスト教徒にとっては、これは疑う余地のないビジョンだったようである。パウロは、「主自らが、指令の呼び声と、筆頭の御使いの声と、神のラッパの響きと共に、天から降りて来られ、そしてキリストにある死者たちが最初に甦り、次いで私たち生き残っている者たちが、死者たちと一緒に、雲の中へと運び挙げられて、空中で主と邂逅するであろう」(Ⅰテサ4:16-17)と言ったが、それは教義を読み上げているのではなく、本当にそう思っていたに違いない。「その時がいつ来るかは誰にもわからない」というのは、福音書にも頻出し、初期キリスト教徒たちも真剣に思っていた信条である。「いつ来るかわからない」は、わからないということではなく、もうすぐ来る、という切迫感の表現である。
こうした切迫感が、社会状況によって強められることはもちろんである。実際、イエスの時代は、ヘレニズム+ローマ帝国支配という圧倒的力と、伝統的民族社会との軋轢が高まっていた。今で言えば、グローバリズム+商業主義と地域社会との軋轢に似ているかもしれない。その中にいれば、人々は自分の生活の根底がいつ崩れるやもしれないという不安を抱く。これは経済的な問題だけではなく、人間の自己規定というか、アイデンティティに関する問題でもある。イエスの思想の一部が人々に受け入れられたのは、すでに古代ユダヤ教の律法や神観念では人々は安定的な自己規定を獲得できない、そういった社会状況が生まれていたという要因もある。
そして結果論から言って、ユダヤ社会は実際に「終末」を迎えようとしていた。バプテスマのヨハネやイエスの予言が、ユダヤ戦争やバル・コクバの乱(第二次ユダヤ戦争、132-135年)によるユダヤ社会の壊滅を予知したものかどうかは明言できない。この状況を敷衍していくとそうなるぞという知性的な判断だったのかもしれない。ともあれ終末は見えていた。それはユダヤ人の望む「成就の日」ではなく、2000年にわたる悲劇の始まりである「絶望の日」だったわけだが。
この実際に起こった「絶望の日」が、人々の宗教観にどういう影響を与えたのか、それは、イスラエル在住民/離散ユダヤ人、伝統ユダヤ教徒/キリスト教徒、ユダヤ人/非ユダヤ人といった立場によって様々だったろう。ただ、これを「終末の失敗」ではなく、「近未来の終末の予兆」として捉えた人々もいたことは確かである。「望むような終末は来ない」という絶望ではなく、「この先に真の終末が来る」という希望が、生き残った。
「終末」は、しばしば「希望」でもある。
そもそもユダヤ教の終末論は、強国に支配されるユダヤ民族の怨嗟の中から生まれてきた。この苦しみ、屈辱はやがて終わる。その希望であった。
どうにもならない苦しい状況の中にある時、働いても働いても生活苦から抜けられない時、あるいは働くことすら拒否される時、人は社会を憎悪し、その崩壊を願う。悪が勝ち誇り、善きものが踏みにじられる時、それを許しているこの世の秩序が崩れ去ることを望む。
終末の先に何があると考えるかは、また様々である。もっと素晴らしい世界が訪れるという希望。これはより善き現世への夢であり、純粋な終末論というよりは革命の夢でもある。イエスもまた、「神の国を来たらせる」夢を抱いていた。初期キリスト教徒たちもキリストの再来を信じ、熱望した。11世紀のキリスト教徒は「千年王国」の幻想を抱いて十字軍の狂気に走った。そしてついでに言えば、ユダヤ人のカール・マルクスは19世紀に「労働者による革命」と「理想的な共産社会」の到来を説いた。だが、言うまでもなく、革命はめったに起こらない。また革命の夢は常に正しいわけではなく、新しい秩序はしばしば地獄となる。
一方、新秩序の夢や可能性が薄らぎ、終末が純粋な終末として夢想されることもある。その先には何があるともわからない。この世ならぬ冥界へすべてが移行するのか、あるいは死滅・無となるのか、それははっきりしないまま、「この世が終わる」ことだけが夢想される。
そんな思想があるものかと思われるが、それは強烈なビジョンとしてしばしば人々に抱かれる。現世に対する呪詛であり、断念であり、否定である。
この「純粋な終末のビジョン」は、西洋世界の精神性・宗教性に、大きな影響力を持ったのではないかと私は思う。このビジョンは、キリスト教世界の中で、あるいはひょっとしてイスラーム世界の中でも、歴史を通じて何度も甦り続けた。そして、それは重要な役割を果たした、と。
いささか乱暴な言い方だが、西洋世界は、現世が大好きである。彼らは肉体が好きであるし、個人的存在としての自己が好きである。そうした西洋世界の「現世への執着」に、強烈な毒をぶち込むのが、「終末のビジョン」だった。現世にこだわり、執着し続ける彼らに、「この世ならぬもの」を意識させるためには、「もうすぐこの世が終わるぞ」という冷水が必要だった。
もちろん西洋世界にも「反現世」の宗教思想はあった。ユダヤ教のエッセネ派、グノーシス、カタリ派……。だがそれは決して主流にはならないものだった。
キリスト教はその中で、「終末のビジョン」をかざすことで、何とか「神」への回路をつなごうとした。「最後の審判」とそれを基盤にした「罪」の強調が、キリスト教の中核であったことは否めない。
終末論は悪しき思想である。それは大衆の怨嗟(ルサンチマン)や破壊衝動を煽動する。時には狂気的な行動を誘発する。終末とか断罪=地獄墜ち宣告とかいう、つまり恐怖によって教えを広めるのは悪しき宗教である。
イエスは終末論に加担した。それは彼の落ち度である。
「俺は雲に乗って再来する」と本人が言ったのか、物語なのかはわからない。当人が言ったら言ったで、また、そうでなくて物語が勝手にできてしまったのならそれができてしまったで、彼はそれを悔いているだろう。
* * *
ある言い方をすれば、イエスは衆目の前で、無残に死んで見せた。それは復活によって生命の永遠性を示すためだったとしても、その無残な死に方は、多くの人に衝撃だった。
その衝撃を中和するために、「犠牲」の神学や、「仮現論」などの説も生まれた。
そして、イエスに「倣って」積極的に死を選ぶ「殉教者」も生まれた。
殉教の問題は難しい。当事者のリアリティをなかなか把握することができないからである。
ただ、一口に殉教と言っても、いくつかパターンはある。
第一は、教団に参加して活動していたところを、弾圧者に襲われて死ぬ。そのことを予測していながら、あえてそれを避けようとしない。自発的な死ではないが、これも広い意味では殉教である。
第二は、棄教すれば赦免されるという場面で、それを拒み、殺されるという場合。これがまあ、一番正統な殉教なのかもしれない。
第三は、むしろ積極的に命を捨てることで、宗教思想や組織を守ろうとする場合。イスラームの自爆テロなどを考えればわかりやすいかもしれない。場合によっては単に「理想に燃えた戦士としての死」ということになるのかもしれない。
殉教を倫理的に評価できるのかどうかは、正直、よくわからない。一日本人としては、「宗教にそこまで重要性を与える必要はない」という感じもするが、たとえば、「ある倫理的悪をなさないとお前を殺す」と言われた場合、殺されることを選ぶというのもひとつの立派な選択となる場合もあるだろう(これは殉教とは言えないか?)。
ただ、「信じて命を捨てたら、一気に天国へ行ける」という思いに駆られて死ぬのは、どうも違うだろうとも思う。求道(霊的成長)というものは、骨の折れる一歩一歩の自己鍛錬によるものであって、一気に死んで天国へ行くというのは、その放棄であり、エゴであるようにも思われる。
実際、初期のキリスト教徒たちには、こういう思いで殉教を選んだ人々もいたようである。ただ、貧窮や奴隷的抑圧にあえぐ人たちがそれを選んだ場合、それを非難するのも無体な気がする。
いろいろ難しい問題があるが、イエスが「さあ殺せ」というような死に方をしたことで、それに「倣った」人も多くいたことは否定できないだろう。やはり教祖の生き方はお手本であり、それと同じ生き方をしようとするのは自然である。
殉教の美化は、やはり不当なことであるように思われるし、それによって歴史上、必要以上の殺戮が生まれたことは否定できないのではないだろうか。


















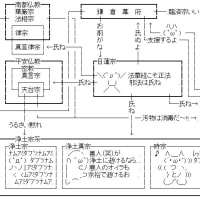

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます