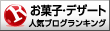那覇市は1921年に市制施行(那覇区→那覇市)、今年市制100周年。
その那覇市ですが、昔、「那覇」の読み方をどうするかで論争が起こったことがありました。
元来「那覇」は琉球王国時代の琉球語(うちなーぐち)で地元周辺では「ナーファ」または「ナファ」と発音していた。また、山原では「ナパ」、沖縄本島南部では「ナーハ」または「ナハ」と発音していた。
薩摩の役人は「ナハ」と発音していたと思われる。
琉球が沖縄県になると、日本語で「那」は「な」、「覇」は「は」と読むことから、標準語(大和口)を話す時は多く「なは」と読むようになった。「は」も普通の「ハ(ha)」で発音し、地元沖縄では標準語として現在と同じ発音で「ナハ(Naha)」という読み方が事実上定着していった。これに対し、内地の人から、「仮名表記は『なは』だが『ナワ(Nawa)』と発音すべきだ、もしくは濁点を付けて『なば』と読むべきだ」とクレームが付いた。
当時使用していた旧仮名遣いでは語中語尾の「は」は「ワ」と発音していて(一般単語では漢語や複合語の結合部分の先頭では語中語尾でも基本的に「ハ」と発音したが、地名の場合は「は」漢字の読みの先頭に来ても、それが音読みであっても「ワ」で発音する傾向があった)、「阿波」「小田原」「尾張」はそれぞれ「あは」「をだはら」「をはり」と書いて「は」を「ワ」と発音した。また、「丹波(たんば)」「千葉(ちば)」のように濁る地名もあるから「那覇」を「なば」と読んではどうかとも。「ナハ(Naha)」だと中国の地名みたいで(ここで言う中国風というのは日本人が中国の地名を読む時のような感じという意味)、これはよろしくない、日本らしい読み方にすべきだと主張したのだ。
そこから、「那覇」をどう読むかという論争が始まった。
その議論の中で従来の島言葉による「なーふぁ」や「なふぁ」と読ませる案も持ち上がった。しかし、「ふぁ」は普通の日本語にない特殊な音だから、これが正式な読み方として採用される可能性は低かったと言える。
沖縄の民俗学者・言語学者の伊波普猷は「『ナワ』と読むべきだ」というクレームに反論し、「市原」など語中語尾でも「ハ」と発音する地名の例を挙げ、語中語尾だから必ずしも「ワ」と発音するとは一概に言えないとして、「ナハ」と読むことを支持した。
1934年、日本放送語審査委員会は「那覇」を「ナハ(Naha)」と読むことを決定した。
「沖縄」は旧仮名遣いで「おきなは」と書いて「オキナワ(Okinawa)」と発音した。しかし、「那覇」のように漢字1文字ずつ区切って「は」が漢字の読みの先頭に来るものを内地の「阿波」などと同じように「ワ」で読むのは沖縄にはなじまない。
地名の語中語尾で漢字の読みの先頭に来る「は」を「ワ」と発音するか「ハ」と発音するかについては地域差もあり、「ワ」と発音する傾向が強い地域もあれば弱い地域もある。「阿波」「小田原」「尾張」が「あわ」「おだわら」「おわり」と読むようになったのはいわば自然のなりゆきなので、「那覇」のように「ハ」で読むのが定着したのを無理やり「ワ」に読み替えようとするのはお門違いだったと思う。