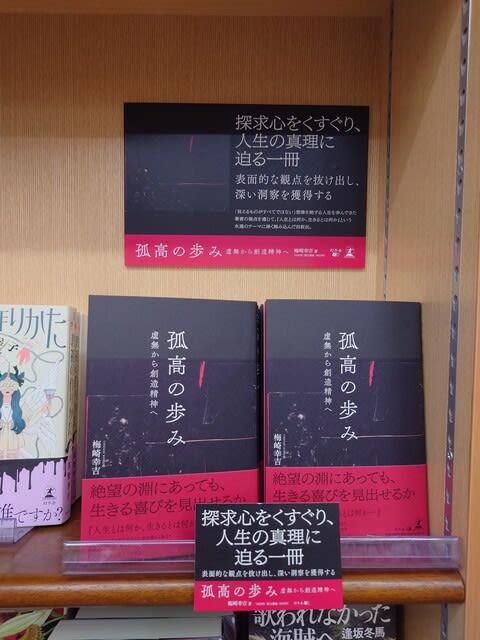「自己愛の不徹底」
拙著「小林秀雄論」より抜粋
自明の事と言えば自明の事だが、本当に我々は自分自身を愛しているのだろうか。さらに言えば自己認識をしているのであるか。我々は通常では自己愛を悪しきものとみなしている。無論、狭義の意味で用いられているのだが、その判断は何の根拠があって、誰によって、何の為に悪しきものと決定されたのか?殆どの人々はこの日常何気なく使われている言葉すら理解もせずに使っている。
真の自己とは何か? 我々が人間と呼ばれ、生き、生活する。一体我々はどこから来て、どこへ行くのか? そもそも我々は現実には存在しているが、その存在の意味は有るのか無いのか? 等々。これら非常に素朴な問いすら我々は日常的生の中にあって自らの意志で問うてはいない。天災、人災等によって精神の或は生命の危険によって始めて生存の理由の問いに意識が向かう。だが、そのうち習慣や本能、宿命という、曖昧かつ便利な言葉のなかで思考停止する。自己保存本能と呼ばれるこの反応は無意識、意識的に働く。
自己保存本能?皮肉って言えば我々を生存さしむるに足るような意味や根拠など一体どこにあるか。その位なら動物や虫ケラ、自然界のすべての存在にだって在る。弱肉強食が自然界の摂理であるか、法則であるか。たまたま人間に考える力が具わっていたので自然界で力を持ち得たのか、等々。
現代の最も有能とされる哲学者ですら紀元前の哲学者達を超えてはいない。ソクラテス、プラトンはもとより、ピュロン(前360~270)という懐疑派の中心人物の世界の入口でまごついているのがせいぜいの有様である。彼の相対的思考は徹底している。「断定しないということも断定しない。」と。ピュロンはこの世界観をインドの地で学んだ。二-チェ流に言えば「消極的ニヒリスト」に殉じたのである。皮相な色即是空を体現したにすぎない。最も現代人と比較すればピュロンの方がはるかに筋金入りである。
無私を手に入れたが自分自身も虫になってしまった。カフカの「城」ではないが方向性を、意志を完全に喪失してしまったのだ。判断停止とは思考の結果得られた考えであり、その結果は彼個人がこれ以上自分は考える方法が見い出せぬ、と自ら限界を引いたことによる。これは彼を守る為の単なる精神衛生学にすぎない。さらに言えば自己探求の放棄にすぎぬ。人生を達観する世界観など毒にも薬にもならぬ。ところが現代ではこの世界観が流行病となっているとなっては由々しき問題である。他にも神秘主義的世界観があるが、真の神秘家達は現実を軽視、或は遊離など断じてしない。現実世界のなかにこれら全て含まれているからだ。単純な言い方をすれば知覚力の深浅にすぎぬ。不可知論の信奉者は単に己れの知覚力の鈍さを語り、信じ込んでいるにすぎない。
今日ピュロンのひねた子供達はそこかしこに存在する。ピュロンを前にしてはパスカルといえども手がつけられぬ。何を言ってもピュロンは「そうかも知れぬが、そうでないかも知れぬ」と一切を相対化するのである。生きているのか死んでいるのか、その判断も下せぬ。さらにはそのような問答も、状況すらも在るのか無いのか、等々。きりがない。ピュロンに対して私が「君は結果として空間自体と化した。それも実体を伴わぬ。」と言えば彼は「そうかも知れぬ、そうでないかも知れぬ。」と答えるだろう。さらに私が「その君の世界観は思考の結果の果てに達した結論で、君のその返答にもその君が道具として用いた思考が無意識的に働いている。でなければ返答すら出来まい。」と突っ込んでも「そうかも知れぬし、そうでないかも知れぬ。」頭も無ければ尻尾も無い、まさに空間そのものとも言えるが、毒にも薬にもならぬこの意識はあらゆるものに対して偏見をもたぬという意味では必要な意識でもある。
白痴とも無邪気ともいえて、この意識を空間として所有し活動すればいかなる状況においてもバランスを保つ事が可能となるからである。
ソクラテスにとってはピュロンの世界観は自明のものであり、その上で、さらにあらゆる人々に意識的な対話を通して、無知の知への自覚に至らしめる為に活動していたのである。このソクラテスの所有していた地下水脈を小林秀雄も又、確実に所有していた。
極論すれば我々は此の地上に存する限り何ぴとといえども不具者である。聖者はもと より、天才と呼ばれた存在達は常に己の無力感を名状し難いほどに味わっている。
く どいようだが有能ゆえではなく自己の無力さゆえに苦悩する。
「天稟の倫理性と人生無常 に関する沈痛な信念とを心中深く蔵して、凝滞を知らず、俗にも僧にも囚われぬ、自在で しかもあやまたぬ、一種の生活法の体得者だったに違いないと思う。」(西行)と。
だが常に実生活のなかで「いかにかすべきわがこころ」をもって地獄絵の前に佇む己が姿を己自身が無す術もなく常に直視しているのである。
「一西行の苦しみは純化し、『読人知らず』の調べを奏でる」。
小林秀雄流に言えば「陸沈の人」と化す。だが、「惑ひの上に酔ひ、酔ひの中に夢をなす」人々の目にその姿は映らぬ。小林秀雄が自身を体得し観た、その心眼でもって彼ら「読人知らず」と化した存在の魂の相を言語表現によって描こうと決意したのだ。公人から私人へ、さらに批評家失格という手順を経て、彼は言い切る「文芸の道は人が一生を賭して余りある豊富な真実な道の一つだ。文芸の批評は人物の批評と何ら異なる処はない。この一種不遜な事業を敢行するには文芸を愛して恥じぬ覚悟が要る。」(マルクスの悟達)と。
文芸という言葉は人間と同義語である。小林秀雄は世間 が思っているほど頭は良くない。己れの心情すら制御出来ないではないか。見たまえ、彼がのたうち、よろめき己が胸を打ち、血へどを吐いている様を。
「彼は、真理の危 険を聖者の如く知り、言葉の危険を詩人の如く知っていた哲学者だ。ここから彼の表現 の、恐らく限なく意識された不安定が生ずる。彼に比べれば、彼を師とする現代の実存主義の哲学者達は、殆ど転調を知らぬ音楽家の様に見える。」。
ニーチェについ て語ったセリフはそのまま小林秀雄にも当てはまる。不安定という言葉は単純ではない。
常に生き活きとした芸術的感性を失わずにすべてに対応する意識の事である。知覚する事のなかに、見ると感じる、考えるが同時に作動する。あらゆる結論、或は結果等までがそのなかに含まれている。これは言葉で言うのは簡単だが、いざその状態が現実化した場合は言語を絶する苦悩、苦痛が感覚レベルとなり自己自身をコントロールすることすら困難となる。その体験の質と自覚がそのままその人物の言動、或は表現となる。 円という概念は大小の区別がつかない。円の視点から見れば大小関係無く円である。個々人の魂の実体験を通して人はその違いを感じる。断っておくが単なる体験主義を言うのではない。
無論、体験と言えば体験なのだが、感覚から心理、精神的なものをも含む意味での体験 である。体験主義者の良く使う言葉で他人の事は所詮理解出来ない、当人に代わって生きる事が出来ない、と同じような意味の似た言い方は他にもある。つまるところ生存の基本条件以外は所詮皆五十歩百歩でしかない、と。他の事はすべて個々人の主観であり、信仰でしかない。
さらに言えば此の世は「夢」にすぎぬという者さえいる。ピュロ ンも含めてこれらすべての考えの基本は「死ねばすべて無に帰す」ということである。無論、肉体的次元が基である。だが、元祖のピュロンはこれすらも判断すまい。
「死後の 世界は死んで分かるだろう。だが自分が死んでからも死んだのかどうかは死んでからも 分かるか分からないか、又そのような意識自体が在るのか無いのかすべて判断出来ない。この間い自体が空しい問いであるが、それすらも空しいのか空しくないのかその尺度すらない。いや在るかも知れないし、無いかも知れない。要するにその人の意識や考え方 によって世界は変化し、又変化しない。これも又、判断出来ない、──。」と、きりが無 い。
すなわち生きながらの眠りの世界である。これ又、ピュロンにおいては馬耳東風に すぎない。心頭を滅却すれば火もまた涼し、である。言葉は使用法でいかようにも変化させうる。
ピュロンと同時代に生きた人物でディオゲネス(前四四四 ~ 三二三)を対置させると痛快である。彼は女々しさを一切拒否する。「人は理性をもたねばならぬ、でなければ首つりひもをもたねばならぬ。」と。
眠りという平安を説く「徳」の賢者に対して二ーチェはかく言う。
「彼の知恵は、目覚めていることを、よく眠るための手だてにせよ、ということである。そしてまことに、生になんの意味もなく、私が無意味を選ばねばならぬとしたら、私にも彼等のこの知恵は、最も選ぶに値する無意味であろう。」(ツァラトゥストラ、手塚富夫訳)と。
非常に明快である。さらに歩を進めて「死の説教者」達ヘニーチェは鉄槌を下す。
「かれ らの知恵は言う。『生きつづける者は愚人である。こうして生きつづけているわれわれも愚人である。しかも、それを知りながらなお生きつづけているというこのことこそ、生 における最大の愚劣である』。『生は悩みにすぎぬ』──またある者たちはそう言う。そ してそれは嘘ではない。それなら、せめてそれを言う君たちの生が終結するように、意 を用いたらどうか。悩みにほかならぬ生が終結するように、意を用いたらどうか。── だから君たちの徳の教義はこうあるべきだ。『なんじはなんじ自身を殺すべきだ。この世 からひそかに去るべきだ』と。(中略)しかし君たちは静かに待つことができるほどには、自己のうちに充実した内容をもっていない。──いや、怠惰になりうるほどにも内容を もっていないのだ。」