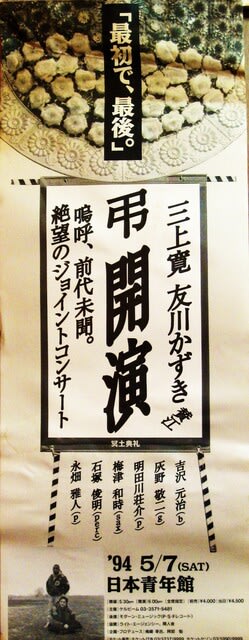黙せる詩人
彼の実体を誰をも見抜けず、又それを意に介さず然して逝った。
末期癌の激痛の中、死を目前にした三日間は両眼をかっと見開いていたという。
彼は寡黙であった。或いはその言動は他者に理解不能、誤解されうる印象を与えた。酒乱、淫乱、冷酷、有情無情が混沌たる彼の衣装であった。
自ら修繕屋という立場を日常に実践した希有な歌わぬ詩人であった。分野、意識のレベルを超えて酒を飲み、アルコール共同体と称して種種雑多なる人物と交流をもち、その人脈を継承維持しうるは皆無と言えるほど至難事である。
無私なる精神を蔵し、深々とした緻密なる心情と透徹した思考、及び不屈の意志を血肉化し、さらに真摯なる求道精神を必要とする。彼を慕う者はあまたいれども所詮自称ファンにすぎない。
彼の苦悩は彼自身ではなく他者の苦悩であるということを正確に現す言葉が見いだせぬ。「いかにかすべきわがこころ」に彼自身翻弄されていた。と言っても何のことやら分かるまい。
百万の桜の下に酔い臥して恥濃きわれををののき嗤ふ
数しれぬ過失は酒とともにありその酒抱きてけふも堕ちなん
彼の晩年の数少ない自虐的なこの二首の歌には名状し難い激しい苦悩が秘められている。
彼は多感な時期に三島由紀夫と出会い、そして自決という決別は他者の窺い知れぬ傷痕を、痛苦を刻印したであろう。
不撓不屈の意志をもってしても現代の相対化された不毛の対人関係を変革せしめることの困難さは筆舌に窮する。この暗澹たる状況にどっぷりとおのが身を浸して生き抜いたという意味では享年五十三歳は長生きともいえ
るであろう。
他者との比較等詮無きことであるにしても、想像を絶する軋み、苦渋の人生であった。
漆黒の闇の淵なる神楽舞その笛の音は虚無の使者かは間近なる自己の死を見据えての一首である。
――自らに息絶えるまで自己表現を禁じ、おのれを素材として媒体として供儀に捧げた希有かつ真摯な恐るべき詩人であった。
一九九九年十一月十四日