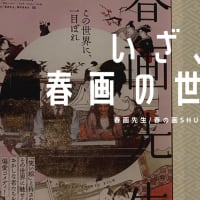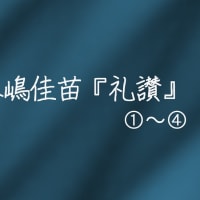ーーAIの行うことに美しさはあるのか?
この問いかけは畳に砂を撒かれたようななんともいえないザラつきを私の胸に残した。
(※尚ここでいう美しさというのは〝きれい〟なものではなく、AIの行ったこと、作成したもの、描いたもの等に心が揺さぶられるかどうかということを指しています)
羽生善治さんのAIとの対局を例に挙げ、なるほどという理由からつい私もNOと言いたくなった。
しかし果たして本当にそうだろうか?
確かにAIというだけで自動で作成されたものは心がこもっているとはいえない。
AIの歌なんかはそれが如実で、ほとんど人と変わらない、またはそれ以上に上手いけれど、どこか淡々とした冷たさを感じる。
感情が乗っていないからだろうか、テクニックだけといった印象を持った。
ではAIのつくったものに少しでも人間の手が加われば美しいものになるのだろうか?
それともやはり人間が一から制作しなければ美しいものにはならないのだろうか?
元々漫画家として活躍されていた方で、パーキンソン病の方の話を耳にする機会があった。
その方は段々動かなくなっていく体の中で、それでも絵を描きたくて、どうしたら描けるか考えた時にデジタル画と出会った。
震える手でペン入れをすることはできないが、デジタルであれば逆に手の震えを活かした描写ができる。
こうして描かれた鳥の絵は生き生きとしていて美しく、観る者を感動させる。
そうならなければいいと願いつつも想像してみる。
もしもさらに病気の進行が進んでデジタル画さえも描けなくなった時、それでも新しい絵に挑戦したくて、過去の自分の絵をAIに学習させて新しく絵を生み出したとする。
AIが描いたそれは果たして何の感情もこもっていない無機質なものだろうか…?
私はそうは思わない。
ものづくりをする中で機械化された社会やAIを否定する意見をよく耳にする。
便利になる一方で人の持つ技術力が失われている。
確かにそうだろう。
しかしそういった進化が悪いわけではない。
技術の進歩によって、これまでと違った美しさや感動を生むことは可能だと感じる。
AIだから美しくないのではない。
大切なのはそこにあるストーリーで、それはAIだろうが人間だろうが変わらないのである。
ただ闇雲にAIを使ってなんでも代わりにやってもらおうとするから失われていくものが多いのだ。
明確な理由を持ってAIと共存していくことが未来を明るくし、文化を残すことにも繋がるのではないだろうか。

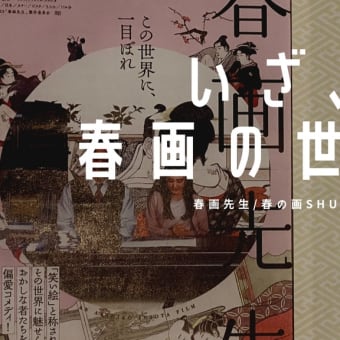






![倭姫命ご巡幸地[瀧原宮]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/62/a8/290cc58e55873d4d3cefa4daf4a34e57.jpg)
![倭姫命ご巡幸地[磯宮(伊蘓宮)]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/16/ed/a3f42482177a53c60a7ed9d54fb6c75f.jpg)