
第2章を参考に、VirtualBoxにCentOS7をインストールしてみた。
PCが非力なせいか結構インストールに時間がかかってしまった。
あとLinux標準教科書と微妙にバージョンが異なるのか、ちょっと違う部分もあったので、自分の環境に合わせて適宜修正した。
第2章 Linuxのインストール
2.1 実習で利用するハードウェア
- マシン本体:パソコンか「VirtualBox」のような仮想化ソフトウェア
- 実装メモリ:少なくとも1024MBのメモリ推奨
- DVD光学ドライブ
- ハードディスク:約10GBの空き容量
- その他周辺機器:キーボード、マウス、ディスプレイ
ここでは、VirtualBoxを使うことにする
2.2 利用するLinuxのディストリビューション
- Cent OSのバージョン7.3、x86_64版
- CentOS公式サイト
- https://www.centos.org/
- CentOSは、商用ディストリビューションであるRed Hat Enterprise Linuxの互換ディストリビューション
2.2.1 インストールDVDの入手方法
- ISOイメージをダウンロードする
ここでは、「CentOS-7-x86_64-DVD-2003.iso」をダウンロードした
2.2.2 バージョン
- より新しいバージョンのCentOSがリリースされていたら、新しいバージョンを使う
とあり、現時点ではバージョン8がリリースされているようであるが、ここでは上述の通り、7を使う
2.3 インストールの前に用意するもの
- インストールDVD
- マシンの設定:BIOSで「起動順序」の設定
- 光学ドライブを優先
- ハードディスク
2.4 インストールの開始
① インストールDVDを光学式ドライブにセットし、マシンを起動
自分の環境の場合、VirtualBoxで先程ダウンロードしたisoファイルを光学ドライブに割り当てて起動する

②起動画面が現れるので、「Test this media & install CentOS7」が選択された状態でEnterキーを押す。
③インストールメディアのチェックを行わない場合は、「Install CentOS 7」を選択
Testは要らないので、「Install CentOS 7」を選択した状態で、Enterした

④言語の選択画面が表示されるので、「日本語」を選択し、「続行」

⑤「インストールの概要」というメイン画面が表示される
ここでは、まず「インストール先(D)」を選択してハードディスクのパーティションを設定する。

⑥「インストール先」の画面を開くと既存のハードディスクが選択されているので、左上の「完了(D)」をクリック

⑦ハードディスクに十分な空き領域がない場合は「インストールオプション」が表示される
⑧「ディスク領域の獲得」という画面が表示されるので「すべて削除(A)」を選択し「領域の再利用(R)」をクリック
⑨ネットワークが利用可能な場合は「ネットワークとホスト名(N)」を選択。有効なネットワークインターフェイスが表示されるので必要に応じて「オン」にして「完了(D)」をクリック
⑩「ソフトウェアの選択(S)」を選び「開発およびクリエイティブワークステーション」を選択し、「完了(D)」をクリック

⑪メイン画面に戻り、「インストール開始(B)」を選択

⑫インストールが開始される

⑬「ROOTパスワード(R)」を選択してrootのパスワードを設定

⑭「ユーザーの作成(U)」を選択して、ユーザー作成画面を表示
ユーザ名(ここではlinuxtextとする)とパスワードを設定する

⑮インストールが終了したら、「再起動(R)」をクリック

2.5 インストール直後の初期設定
①インストールしたマシンを起動すると、ブートローダーが起動するOSの選択を求めるので、そのまま待つか、Enterキーを押す
②「初期セットアップ」画面で「LICENSE INFOMATION」をクリック

③「ライセンス情報」画面が表示されるので、ライセンス契約を確認し、問題なければ「ライセンス契約に同意します。(A)」を選択して、「完了(D)」をクリック

④「初期セットアップ」画面に戻り「設定の完了(F)」をクリック
2.6 ログインする
①ユーザ「linuxtext」をクリック
②「パスワード」を入力し、「サインイン」をクリック
③CentOSにログインできたらgnome-initial-setup画面が起動するので、言語が「日本語」になっていることを確認し「次へ(N)」をクリック

④入力メソッドが「日本語」になっていることを確認し「次へ(N)」をクリック

⑤「セキュリティ」画面で「位置情報サービス」を適宜オン・オフを切り替えて「次へ(N)」をクリック(この手順は標準教科書にはなかった)

⑥オンラインアカウント画面が表示されるので、「スキップ(S)」をクリック
※ 接続したい場合は画面に従って適宜接続

⑦「使用する準備が完了しました。」と表示されるので、「CentOS Linuxを使い始める(S)」をクリック

⑧「初めて使い方へ」の画面が表示されるので適宜参照し、「×」印をクリックして終了させる

⑨CentOSのデスクトップが表示される

2.7 コマンドの実行
- 端末を起動するには以下の方法がある
- 「アプリケーション」メニューから「ユーティリティ」、「端末」を選択
- デスクトップ上を右クリックし、ポップアップメニューから「端末を開く」を選択する

















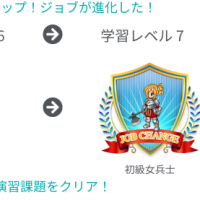







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます