MIXI、「競輪チャリロト」不正発覚で再燃する不安再び露呈したガバナンス不全、過去の教訓生きず_田中 理瑛様記事抜粋2025/01/23 5:50
昨年末、突如リリースされ、話題を呼んだ短文SNS「mixi2」。かつて一世を風靡した「mixi」の名を冠した新サービスだけに、往年のユーザーからの反響は大きく、登録者数は1週間で120万人を突破した。
順調な滑り出しを見せたmixi2だが、運営会社であるMIXIは目下、危うい局面に立たされている。
1月14日、MIXIは当初の予定より約2カ月遅れて、2025年3月期第2四半期決算を発表した。発表が遅れたのは、競輪やオートレースの車券販売サイト「チャリロト」を運営する連結子会社のチャリ・ロトで、昨年10月に不祥事が発覚し、調査に時間がかかっていたためだ。
最大規模の子会社で代表らが不正取引
外部の専門家で構成する調査チームがまとめた報告書によると、チャリ・ロトの代表取締役であった上田博雄氏と前・営業本部長が、直接または自らの関連会社や配偶者を通じて、複数の取引先から不正に金銭を受領していた。2人が不正に受け取った金銭は合計10億円超に上る。
MIXIは昨年10月30日付で上田氏を取締役から解任し、営業本部長も12月26日付で懲戒解雇処分となった。
今回の問題を受けて、MIXIの木村弘毅社長は役員報酬の30%を3カ月分、自主返納すると発表した。2人に対する刑事告訴の可能性について、木村社長は1月14日に開いた決算説明会の場で「現段階で発表できるものはないが、厳しい姿勢で臨みたい」と述べた。
2019年に買収したチャリ・ロトは、MIXI子会社の中で最大規模の売り上げを誇る。スマホゲームに次ぐ収益柱を育成するうえで欠かせない重要子会社で、なぜ不祥事は起きたのか。調査報告書からは、同社の決裁プロセスが形骸化し、不正を検出する仕組みも機能していなかったずさんな管理体制がうかがえる。
MIXIの現在の稼ぎ頭は、2013年にリリースされたスマホゲーム「モンスターストライク」だ。ただ、国内のスマホゲーム市場は頭打ちで、同社のスマホゲーム関連事業の売上高も、ピークの半分ほどまで減少している。
「モンスト一本足」からの脱却に向けて、MIXIが次の柱にすべく投資を進めてきたのがスポーツ事業だ。2019年2月にチャリ・ロトを完全子会社化したほか、2020年6月からはスポーツベッティングサービス「TIPSTAR」の運営も開始。傘下にはプロバスケチーム「千葉ジェッツ」やプロサッカークラブ「FC東京」を持つ。
スポーツ事業の2024年3月期売上高は329億円と、スマホゲーム関連事業(988億円)に次ぐ規模にまで拡大している。セグメント損益はオーストラリアのベッティング事業の先行費用などにより赤字が続くが、その中でもチャリ・ロトは安定的に成長を続け、同期の売上高は174億円、経常利益は18億円に達した。
買収前から曰くつきの会社だった
今回、不正に関与した取引先は、上田氏と前・営業本部長の個人的なつながりを契機に取引を開始した個人事業主だった。
決裁プロセスの最終承認権者でもある2人がこれらの取引先について独占的に対応しており、取引の具体的な中身はブラックボックス化していた。一部は社内ルールで定められた相見積が実施されないまま決裁プロセスが進められたほか、契約書が締結されなかったり、取引の実態が契約書の内容と異なったりするケースもあった。
2006年に設立されたチャリ・ロトは、実は買収前から曰くつきの会社でもあった。
2007年に同社を買収したテラネッツ(現クラウドゲート)では、2006年から2009年まで経営陣の共謀により不適切な会計処理が行われていたことが、2011年に発覚している。当時の第三者調査委員会の報告書によると、一連の不正においてチャリ・ロトを介した循環取引も行われ、取締役だった上田氏も協力・関与していたことが認められている。
その後、チャリ・ロトはジャフコなどの傘下を経てMIXIの完全子会社となったが、今回問題となっている上田氏による金銭の受領は、MIXIが買収する前の2018年2月から行われていた。調査チームの報告によると、一連の調査で証跡は発見されなかったものの、MIXIによる買収後も、今回の事案とは別にチャリ・ロトと取引先2社との間で不適切な資金のやり取りに関する疑義があるという。
MIXIは「買収時のデューデリジェンスにはしっかり取り組んだ」(島村恒平CFO)とする。しかし、昨年10月に外部から情報提供を受けるまで不正を見抜けなかった背景には、ガバナンスに対するMIXI経営陣の意識の低さもある。
例えば、チャリ・ロトにおける監査役による業務は会計監査に限定され、取締役の業務執行状況は対象外だった。これついてMIXIの島村CFOは、「連結(化した)時点から業務範囲を変えていなかった。前の段階で(監査の対象の変更について)判断すべきだった」と説明した。
子会社化後はMIXIの役職員を出向させていたものの、調査チームの報告は「チャリ・ロト社の事業や取引に関する理解が十分ではなかった面もあり、期待されたけん制機能としての役割を十分に果たせていなかった可能性がある」と指摘している。
過去には子会社の不正で社長交代も
MIXIにとって、子会社の不祥事は今回が初めてではない。
2015年に115億円を投じて買収した、チケット転売サイト「チケットキャンプ」を運営するフンザに対し、警察は2017年12月、商標法と不正競争防止法違反の疑いで強制捜査。翌年5月にチケットキャンプは閉鎖された。
その後、MIXIの森田仁基・前社長らが商標法違反の疑いで書類送検される事態にまで発展した。辞任に追い込まれた森田氏の後任として、ガバナンス改革を任されたのが木村現社長だった。
当時の第三者委員会の調査では、森田前社長がフンザの管掌役員でありながら、問題があるとされた商標の使用を認識していなかったことなどから、フンザとMIXIとの間での情報共有の不備を指摘されている。一連の事態を受けて、MIXIは執行役員制度を導入し、管理部門の役員を任命するなどガバナンス強化を図ってきた。が、結果的に教訓は生かされなかった。
MIXIはチャリ・ロトでの不正再発防止策として、取引先との面談記録を義務化し、購買先の選定審査などを行う「審査部」を設置するという。
早々にサービス終了に追い込まれたチケットキャンプと異なり、チャリ・ロトの事業は継続される見込みだ。MIXIは「事業の成長性に与える影響は軽微」(島村CFO)とするが、長きにわたり代表を務め、個人的なつながりで取引先を集めていた上田氏の解任後も、同社がこれまで通りの成長を続けられるのかは現時点で不透明だ。
一方、上田氏の後任の代表取締役には、MIXIから出向している石原洋輔氏が就任した。チャリ・ロト社の財務経理部長として出向し、取締役も務めてきた人物だ。
調査チームは一部調査を実施できず
今回の調査では、2人以外のチャリ・ロトの役職員が関与したことをうかがわせる事実は判明しなかったものの、調査チームは一部の関係者の協力を得られず、意図した調査を実施することができなかったとしている。公正さが求められる公営ギャンブル事業にもかかわらず、取引の健全性についてMIXIが十分な説明を尽くしたとは言いがたい。
“モンスト一本足”から脱却し、持続的な成長を描くには、この先もM&Aが有力な選択肢となりうる。子会社のガバナンスという経営の根幹が揺らぐ中、先行きには不安感が漂っている。












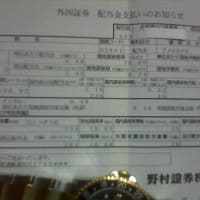

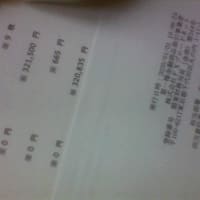
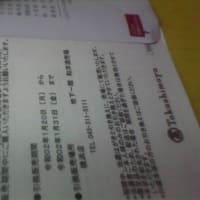

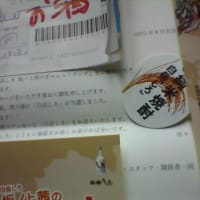

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます