低アル飲料」を喜んで飲む人が知らない"真実"むしろ時代によってその基準は変化してきた24/12/06 6:50千駄木 雄大様記事抜粋<
酒類メーカーが推進する「適正飲酒」の不都合な現実
適正飲酒、ソバーキュリアス、スマートドリンキングという言葉を最近、目にすることも多くなった。
ストロング系缶チューハイ(以下、ストロング系)が猛威を振るっていた時代は終わり、今は「微アルコール(以下、微アル)」と「低アルコール(以下、低アル)」が注目を集めている
今年に入ってアサヒビールはアルコール度数8%以上の缶チューハイを発売しないと決め、サッポロビールも今後は8%以上の商品については発売しないことを発表した。
そして、ストロング系の代表格ともいえるサントリーの「ストロングゼロ(以下、ストゼロ)」は「-196(イチキューロク)」と名前を変え、アルコール度数4%の商品も登場している。
前回記事ー『「微アルで適正飲酒」推進の裏にある不都合な現実 もはや、メディアに踊らされているにすぎない』ーでは、この現状を筆者は「ストロング系に対するバックラッシュ」だと指摘した。国が総力を上げて、ストロング系の流行に歯止めをかけようとしているのは間違いない。
そこで、微アルが頭角を現していくと同時に、低アルにも再び注目が集まっている。現在、何度目かわからない低アルブームが到来している(と言われている)のだが、過去と現在の共通点、そして異なる部分とはなんだろうか? そして、微アルと低アルが抱える課題とは?
低アルコールに明確な定義はない
低アルはノンアルコール飲料(以下、ノンアル)と微アルと違い、完全に酒だが、明確な定義は決まっていない。
そんななかで例えばキリンは、アルコール度数1〜4%未満を低アル商品と見做している。ということは、今年のヒット商品であるアサヒの「未来のレモンサワー」はアルコール度数が5%あるため、低アルには含まれない。
さて、こうした議論をするなかで抱く疑問が「そもそも、普通のアルコール度数ってどの程度なんだろう?」というものだろう。一般的に、ストロング系は8%以上が目安とされる。また、3~4%は「低アル」扱いをされる。
となると、5~6%が「普通」の度数なのだろうか? 筆者のようなアルコールに強い、元依存症患者からすれば、そんな度数は「水」のようなものだが、アルコールに弱い人にとっては十二分に強い度数にも思えるが……。
結論からいうと「時代によって変わる」のが実情だ。
例えば、「日経トレンディ」(日経BP)の2003年7月号に掲載された「果実テイストでボーダーレス化 『氷結』は独自の味を投入」という記事では「低アルコールドリンクとは〈中略〉アルコール度数が10%未満のアルコール飲料のこと」と書かれている。1%の誤記載ではない、10%なのだ。
つまり、この時代にアルコール度数9%のストゼロがあれば、こちらも低アルの部類に含まれていたということである。あくまでも「焼酎や日本酒と比べると」だ。
実際、このとき誌面で紹介されていた氷結をはじめ、「スキッシュ」(宝酒造)、「青春」(サントリー)、「旬果搾り」(アサヒ)のアルコール度数は、どれも5%前後だった。
こうなってくると、もはや「何が普通で、何が低アルなのか?」がわからなくなってくるのは筆者だけだろうか。「5%程度が普通」という考えは、本当にあなた独自の考えなのか、酒類メーカーの長きにわたるマーケティング戦略の影響がないと言えるのか……という話なのである。
ちなみに、2003年時点で低アル市場は1億ケースまで拡大しており、そのなかでも氷結は2002年のシェアで27.4%を占めていたそうだ。さすがに、前出した一覧で唯一生き残っているブランドだ。
そのほかにも、当時は「グビッ酎」(メルシャン)、「スーパーチューハイ」(サントリー)、「下町風味 酎ハイ」(協和発酵工業)、「ハイリキ」(旭化成・現アサヒ)、「ハイボーイ」(合同酒精)などが缶チューハイブームを牽引した。
さらに、居酒屋の定番となったカルピスサワー(カルピス・現アサヒ)も低アルを代表する存在である。1994年発売でアルコール度数は3〜5%というレンジで、今でもコンビニにはだいたい置いてある。
ちなみに、年齢確認がある現在ではあり得ないが、当時は低アルの誤認が問題となっており、1993年には宝酒造を含めた10社が国民生活センターから注意を受けている。
「ジュースだと思ったらお酒だった」という描写が昔のマンガやアニメには多かった気がする(マンガ『クレヨンしんちゃん』にもそのようなエピソードがあった)が、これは当時の酒造メーカーは低アルをジュースくらい身近に、主婦をはじめとした女性を狙い撃ちしていたことの裏返しだろう。
つまり、もともとは本来の購買層ではなかった女性たちのために、低アルは販売されていたのだが、それから30年近く経った今では、女性だけではなく、日常的にあまり飲酒しない若者をターゲットにするようになったのだ。
ちなみに、1988年9月15日号の『DIME』(小学館)の「ビール大好き女子大生・OL10人が選ぶ ノンアルコール 低アルコール ビールはこれがベスト」という記事では、アルコール度数1%未満の今でいう微アルも低アルとして取り上げられていた。
前記事では「微アル市場ができあがってから3年が経過している」と紹介したが、実は36年も前からすでに、その市場に該当する商品自体は存在していたのである。市場はすでにあったところに、微アルという新たな枠組みを飲料メーカー側が設けたのが実態なのだ。
まだ日本各地に「適正飲酒」の理念は届いていない
このようにRTD市場のはやり廃りは目まぐるしい。そして、酒類メーカーは常に新たな消費者を求めているのだ。今後も身体を壊した者たちが代替品として、飲酒習慣がない者にも興味を持ってもらうためにも、新たな商品が出ては、お気に入りの商品はいつの間にかなくなっていく。
その一方で、課題というと大袈裟かもしれないが、今は完全にノンアルしか飲んでいない筆者が感じたことがある。それは、微アルどころかノンアルを置いてあるかどうかの地域差が激しいのだ。
例えば筆者は東京23区外の住宅街に住んでいるのだが、ここではコンビニやスーパーマーケットには、最低3種類のノンアルと微アルがある。低アルは入れ替わりが激しいくらいだ。

しかし、これが渋谷や新宿になるとノンアルが2種類あればいいほうで、基本的には置いていない。むしろ、ノンアルよりも微アルを探すほうが難しいときもある。単純に繁華街でノンアルや微アルは売れないということだろう。
東京はまだいい。これが地方になると、もはやノンアルですら置いていないこともザラにある。親戚の集まりで地元・福岡に帰ると、ノンアル依存症と化した筆者はゾンビのように、ノンアルビールかノンアルレモンサワーを求めて、博多と小倉を徘徊していた。
まぁ、これも福岡という地域柄かもしれないが……。
ノンアルの選択肢を広げることが先決?
前編の記事では昨今の「適正飲酒」や、あえて飲まない「ソバーキュリアス」という考え方、さらにお酒を飲む人と飲まない人が尊重し合える社会を目指す「スマートドリンキング」などの理念について、筆者なりの見解を述べた。
端的に言えば、「笑止千万」「みんなメディアに踊らされているにすぎない」「そういう理念のもとで、微アルや低アルで満足できる人々は、酒がなくても豊かな人生を送れているはずだ」と一刀両断したわけだが、実態としては、「適正飲酒」の理念はまだまだ日本各地にまで届いていないのだろう。
事業と、社会的責任の両立のため、さまざまな工夫を重ねている酒類メーカー。今後どんな状況になっていくのかは現段階では予想できないが、少なくとも、ノンアル、微アル、低アルという選択肢を広げていくことが先なのは間違いないだろう。












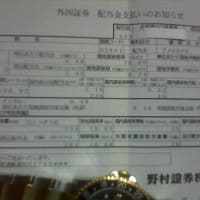

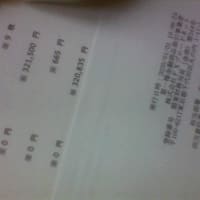
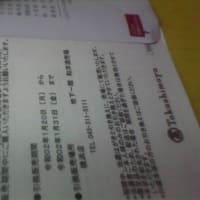

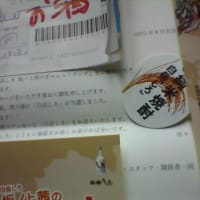

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます