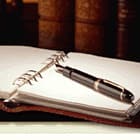
十月半ばには新聞週間があるのですが、その次週、十月下旬から文化の日にかけては読書週間。本の魅力をたっぷり語る特集が新聞などで組まれます。
10月27日付読売新聞朝刊の誌面では、ファンタジー作家の上橋菜穂子先生と、女流ミステリー作家の宮部みゆきさんとが対談。上橋先生は本業が文化人類学の研究者ですので、寡作といえますけど、近作は「本屋大賞」に選ばれていますね。いっぽう、宮部さんはドラマや映画化されることも多い人気作家ですが、最近は現代ミステリーのみならず時代小説にも幅を広げていますよね。NHKの日曜夜にやっているラジオドラマの原作にもしばしば登場しています。
だいたい作家さんがふたり並んで対談すると、お互いの業績の紹介しあいっこになります。でも、そこはあっさりしていて、他の本の紹介がほとんどでした。しょうもないライターどうしが座談形式になると、無意味な褒めあいになって読者が置いてけぼりになってしまうんですよ。『美術手帖』とか、よくわからん文芸誌に載っているインタヴューなんかが、まさにそう。一般人が読んでも面白くないんです。誌的だけれど、要点がわからない。長ったらしいから、無駄に高い。たぶん、あれは作家のブランドで売っているんでしょうけれど、一般の社会人は買わないでしょうね。生活に必要ありませんから。
今回の対談、お二方もザ・ファンタジー作家。
空想物が好きな方は、自分本位でどんどん喋る傾向がありますよね。しかし、そこはさすがにプロフェッショナル。上橋先生の場合、よく『指輪物語』を語られるんですが、宮部さんの子どもの頃の読書のとっかかりはイプセンの『人形の家』なんだそうです。
ネット上でも、デヴューしてそこそこ実績を残した作家に、読書歴をインタヴューした記事がありますよね。とても分かりやすく、その魅力を捕らえているな、と感心して、図書館で借りて読んだことがあります。作家のお気に入りの本というのは、秘密の創作ノートの一部を開け放つようなものでもあります。けれど、それが、ひいては他者の本の購入意欲を喚起して、出版文化の活況にもつながるのです。優れた作家が残した作品の遺伝子が、また、後世にうけつがれ、新たな作家を生んでいくんです。
逆に、すこし非難めいた口調になりますが、自分の創作態度や資料の希少性ばかりを売り込もうとする作家ほど、他人の優れた本の魅力をわかりやすく語ることができない。古典ですでに故人の作家にさえ、めらめらと闘争心を掻き立てられています。生活がかかっているのはわかりますが自作の本を売らなきゃ、という焦燥感が伝わってきて、こちらが引いてしまいますよね。消費者マーケティングは大事ですけれど、読者の反応に頼り切ってしまうと、自分の本当に書きたいテーマが薄くなってしまいせんか。
たとえば、パブロ・ピカソの作品を主題にした論文なり、小説なり、書いたにせよ、自分の論述の旨さとか表現の美しさとかをアピールするのだけど、私が知りたいのは、ピカソがいかに優れているか、という客観的な事実なのです。個人の所感があるのはいいんですよ。でも、ある程度、人文科学の世界でも「わたしがこう思っていますから、正しいんです!」では済まないでしょ。想いを納得のいく理論できっちり語ってくれなきゃ。その作家のファンで、一生ついていきます、というシンパならそうなのでしょうが。絶対に死ぬまで追いかけます、支えます、なんていうのは、運命共同体の自分の配偶者だけではないですか。固定ファンが買ってくれるだけですと、売上伸びませんよね? その文章がうまいのかどうかは、読者の感性や読書量に応じて変わってしまうので、こだわりをあまり前面に出し過ぎると損をするのではないかな、と思います。何年も寝かせて書いた500頁ぐらいのお話でも、社会人の読者は忙しいですから、響くものがなければ数時間で読み捨てますし。とくに、最近は大量の情報をさばく時代ですから、作家の本があまりていねいに読まれなくなってきています。
上橋先生の読書歴が面白いのは、ファンタジー作家だからアニメとかゲームとかではなくて、医学や生理学などの、自分の専門分野ではないところからも積極的に学ぼうとしているところですね。理系の専門家からすれば浅いのかもしれませんが、ふんわりと妄想するのが好きなファンタジー好きたちを、現実的な関心ごとや、人間としていかに生きるべきか、へと誘うのも、知のエリートたるべき作家の使命ではないでしょうか。
作家は本のキュレイターでなくてはならない。これは真理です。ソムリエみたいに、オススメ! 買いなさいよ! という押しつけじゃなくて、こんな見方がありますよとさわりを示すだけのキュレイターです。
読書の秋だからといって、本が好きだと思うなよ(目次)
本が売れないという叫びがある。しかし、本は買いたくないという抵抗勢力もある。
読者と著者とは、いつも平行線です。悲しいですね。





























