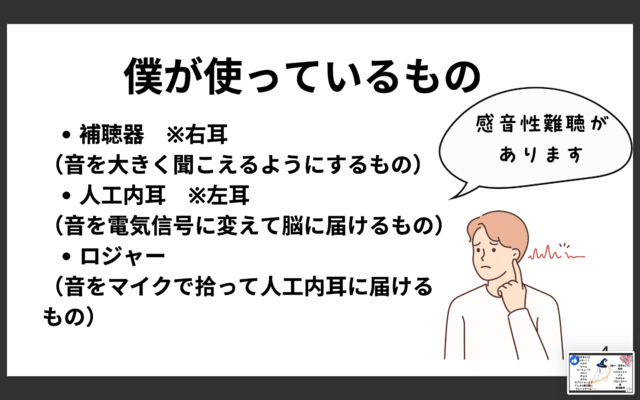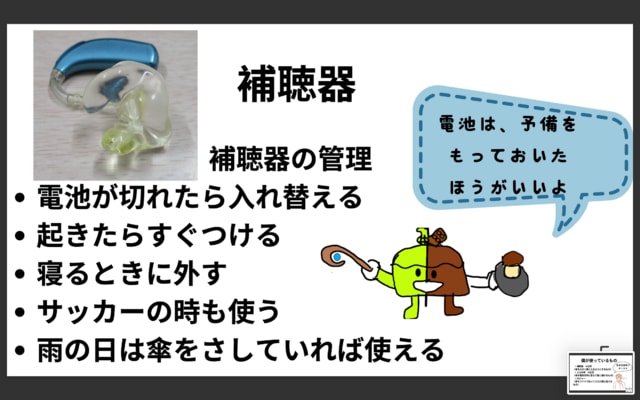MISAさん メガネ関係会社21年勤務 42歳 右58→85dB、左92→110dBスケールアウト 右のみ補聴器装用
MISAさんは、何年か前に、療育施設時代のみんなで集まりましょうと声をかけてくれ、ずっとご無沙汰していた人たちとの楽しい食事の場を作ってくれた。音声を使う人と手話を使う人の間の通訳もしてくれた。自分自身もデフフットサルで仲間と交流し、いつも人の輪の中にいる印象がある。
今回、忙しい中の合間をぬって、インタビューに応じてくれた。これまでの人生で、めまいや聴力低下の発作がありながらも、その時々で楽しみを見つけ、ポジティブに生きてきた様子がわかる。チャキチャキしていて、はっきりものを言う女性だ。その強さの秘密はなんだろう。彼女自身の言葉から読み取っていただけると嬉しい。
【 MISAさんのストーリー 】
<きこえの程度>
幼児期の聴力 右58dB 左92dB
現在の聴力 右85dB 左110dBスケールアウト
※聴力型は、高音域よりも低音域の方がよいタイプ
<幼児期のこと 〜なんでも楽しんでいた〜>
3歳の時、妹の1歳児健診について行った際、保健師さんに「お姉ちゃん、しゃべらないね。」と言われたのがきっかけで、難聴が判明した。補聴器装用して、療育施設に通い始めた。初め、箱型補聴器を装用して、その後耳掛け式補聴器に変わったことは、覚えているが、どう思ったかなどはよく覚えていない。特に抵抗なく補聴器を装用していた。
療育施設は、同じ年齢の友だちが女の子1人、男の子2人いて、4人で楽しく遊んだ。あと、時々個別指導の時間があったが、全体として、楽しかったという記憶しかない。幼稚園も楽しく通っていた。
<小学校 〜最初のめまいの発作〜>
地元の小学校に入学し、これも楽しく通い始めたが、初めての小学校の遠足(5月頃)の当日にめまいの発作を起こし、楽しみにしていた遠足に行けなくなって、大泣きしたことを覚えている。めまいはするし、耳もきこえなくなるしで、とても遠足に行ける状態ではなかった。病院に行くと、即入院となった。入院治療で聴力は70%くらいは戻ったが、100%は戻らず、右耳しか使っていなかったので、前よりきこえなくなったことは、子ども心にショックだった。
入院中は、担任の先生が何度かお見舞いに来てくれた。担任の先生には、色々とご心配をかけたが、「私は、大丈夫、先生は、そんなに私のためにしなくていいのになあ」などと、子どもながらに恐縮していた。その先生は、骨折した時も色々と心配してくださった。若い先生だったし、補聴器をしている児童は初めてで、一生懸命になってくださったのだと思う。
小学校は、学年が変わって、クラス替えする度に、自分は耳が悪いので、大きめの声で、はっきり喋ってくださいなどと、お願いした。自然と、はっきり話してくれる友だちと付き合うようになった。声の小さい子とは、あまり付き合わなかった。話していることがわかりにくかったからかもしれない。特にいじめられた経験もないし、勉強も困ったことはなかった。成績は悪い方ではなかった。
校内放送は、きこえていなかったかもしれないが、不便は感じていなかった。とにかく困ることはなかったと思う。
一度だけ、4年生か5年生くらいの時に、仲良しの二人の友だちに、話があると連れていかれ、そこで、「どうして耳が悪いのに、ろう学校に行かないの?」ときかれたことがあった。どうしていきなりそんなことをきかれるのかいぶかしく思ったし、びっくりしたが、「耳もきこえるし、お話もできるからだよ」と答えた。そのことを妙に覚えているのは、なんか嫌な気がしたからだろうと思う。
ことばの教室は、他校のことばの教室に通った。給食を食べてから、母に連れられて行ったと思う。ほとんど個別指導で、たまにイベントの時などに友だちに会った。普段の学校生活とは、別空間という感じで、仕方なく通っていた感じだった。
<中学校 〜青春の濃い楽しい3年間〜>
中学校3年間は、濃い3年間だった。部活は剣道部に入った。面をかぶる時、補聴器が面とぶつかるので外したほうがよかったのだろうが、やはりきこえる方を選んで、なんとか外さずに面をかぶった。
いじめられることもなかった。クラスが変わるごとに、自分のきこえについては、自分で説明した。はじめが肝心だと思う。声の小さい子の話は、わからないので、言わなきゃダメだと思っていた。自分から言わなきゃどうにもならないと思う。
学力に差がでてくる時期だったが、自分は学習面も特に問題はなく、ちょっとがんばれば、よい成績が取れた。むしろ友だちに「わからないから教えて」と頼まれることが多く、どちらかというと教えてあげる方だった。
ただ、ALTの英語の先生の授業は、全員立たされて、先生の英語の問いに答えられた人から順番に座るというやり方で、英語がききとれなくて緊張した。いつも最後の方になったが、なんとかがんばった。そのような方式の授業でなければ、あまり困ることはなかった。
<高校時代 〜またしても聴力低下、初めてろうの世界と出会う〜>
北辰のテストで第一希望の高校がB判定だったので、一つ落とした高校を受験し受かった。入った高校は、普通科の他に、美術科とか書道科とか音楽科など色々な科があるユニークな高校だったが、その普通科に入った。女子が多く、共学なのに、1年と2年は女子クラスだった。全体に学力のレベルが高かった。1年生の初めての中間テストは、クラスで下から3番目だったので、これはまずいなと思った。しかし、赤点を取ったことはなかった。視力も落ちてきたのもあり、前の方の席にしてもらった。
部活は、友だちと一緒にソフトテニス部に入ったが、それほど楽しくなくて、1年生の夏休み前に辞めた。
そして、1年生の時のクリスマス前、やはりめまいに襲われ、聴力低下を起こした。ストレス、寝不足からきたかなと思った。特に寝不足は自分でもよくないと思っている。12月に入院し、翌年2月上旬に退院した。入院中は、補聴器もはずしていて、コップが落ちる音もきこえず、筆談でコミュニケーションを取っていた。やっとできた高校の友だちも長期の入院で、少し離れてしまった。
高校2年生となり、クラスも変わり、きこえも悪くなり、すごく仲のいい友だちはできず浅い付き合いの友だちしかいなかった。勉強面もきこえる子たちとの差が出てきたのを感じた。高2からコンビニのバイトを始めたが、コンビニでの接客は楽しかった。
高2の夏休みに関コン(関東ろう学生懇談会:全日本ろう学生懇談会の関東支部)から郵便が来た。夏休みに都内のオリンピックセンターで宿泊で「高校生教養講座」を開催するのでご参加くださいというものだった。本当は東京の高校生対象だったようだが、参加者が足りず、埼玉の難聴児を持つ親の会に声がかかり、親の会から紹介されたようだった。面白そうだと思って、親にお願いして、参加することになった。自分で電話で申し込んだが、後できくところによると、FAXじゃなくて電話で申し込んだのは、私一人だったようだ。
「高校生教養講座」に参加して、初めて手話に出会った。すごく楽しくて新鮮だった。こんなに色んな人がいるんだと思った。たくさん知り合いができた。健聴育ちだったのでろうの世界に初めて触れたことになる。高校よりこっちの方が楽しいと思った。知り合った友だちとFAXや手紙で連絡し合うようになった。今でも連絡しあっている友だちがいる。
高3で人文コースの文系の4大の受験コースのクラスになった。クラスに男子が10人いて、新鮮だった。女子クラスの時よりもちょっと男の子を意識する学校生活になった。でも、補聴器を隠すことは、一度もなかった。隠すなんて絶対だめだと思っている。ただでさえ、きこえにくいことは、見ただけではわかりにくいのだから、説明が必要だし、説明できないんだったら、きちんと補聴器を見せることが大事だと思うし、その姿勢は一度もブレたことはない。
さて、高3で、進学先を考えなくてはならなかったが、行きたい大学には行けそうになかった。看護師になりたいと思って、先生に伝えると、相当努力しないと無理だと言われた。例えば、生物のテストでがんばって60点取った時も、自分ではよくがんばったつもりだったのに、先生には「もっとがんばらないと・・」と言われた。それで、こんなにがんばってもダメなんだと、なんか力が抜けてしまった。意欲が減退した。
英語のリスニングテストは、みんなと同じ部屋の一番後ろで、カセットデッキを机の上に置き、CDの音をききなさいと言われた。しかし、きき取れず、勘でやった。大学受験では、リスニングは別室受験だったので、それなりに配慮があったが、細かいことはよく覚えていない。
< 高校卒業後 〜結婚、出産というスピーディーな展開〜 >
高校卒業となった。短大が一つ決まっていたが、高校時代に知り合った人と結婚、出産というスピーディな展開となり、短大は、入学式に行っただけとなった。
しばらく子育てしながら、子どもを夫に預けられる土日だけコンビニのアルバイトをしていたが、20歳で夫とは別居そして離婚となり、子どもと一緒に実家で世話になることとなった。そこで、経済的に自立するために、ハローワークで障害枠で仕事を探した。
<そして就職>
ハローワークで、東京で障害者のための合同面接会があるから行ったらどうかと言われて、そこに出かけた。この合同面接会がタイミングよく開催されていたことは、本当によかった。合同面接会での面接では、次のように伝えた。「接客は、コンビニならできるが、できればデスクワークを希望する。仕事上の電話はできない。日常でも1回ではきき取れないことがある。大きめの声でゆっくり話してほしい。難しい内容の伝達は、文面で行なってほしい。」
このような内容のことを伝えて、結局、その面接会で3社受けて、2社から採用の返事をもらった。そのうちの一つの会社に今でも勤めている。もう20年以上勤めていることになる。
<会社での仕事>
就職したばかりのころは、最初の上司がパソコンのシステムに詳しく、それをしっかり教えてくれて、とても助かった。私自身、白紙状態だったのが良かったのかもしれない。段々と仕事を覚えていった。上司は、話はききとりにくかったが、教えてくれたことは、仕事上とても役に立っている。
会社はメガネ関係の会社で、私の仕事に関しては、個人的な作業なので、会議やミーティングがほぼなく、それは楽だった。例えば店舗から注文があるとその商品の値札を発行した
り、新しいメガネが出たら、会社のシステムにそれの商品登録をしたりという仕事などがある。
初めのうちは、店舗からの依頼は、電話やファックスが多かったが、段々とメールになっていって、メールだと効率もよく、間違いもなく、やりやすく、助かった。
会社の同僚とは、初めは、後ろから話しかける人もいたが、段々とわかってくれたと思う。なんとかやりとりできているが、やはり、リアルタイムですべて話をききとるのは難しい。まわりの人に100%理解してもらうのは、無理だと思っている。80%くらいわかってもらえば、あとは自分の努力でなんとかする感じだ。コロナ下では、皆マスクなので、何を言っているのか全くわからず、自分はしゃべるけど、相手には、時間はかかるが、書いてもらっていた。
基本職場での付き合いは、仕事上の付き合いと割り切っている。
<3回目のめまいの発作>
23歳の時、11月だったが、休日出勤もあり、忙しかったためか、まためまいを起こし、1ヶ月半の入院、3、4ヶ月の病休となった。やはりストレスと寝不足がよくないなと思った。聴力も少し低下した。しかし、今度は、息子がまだ4歳だったので、一刻も早く退院したかった。母が毎日埼玉から都内の大学病院まで息子を連れてきてくれた。母は、仕事を午後休んできてくれていて、とてもありがたかった。母には本当に感謝している。
<オフを楽しむ現在>
今は息子も20歳も越え、大人になり、専門学校も卒業したので、親としての責任は果たしたかなと思う。今後は自分の生活を楽しもうと思っている。オフは、推し活やデフフットサルを楽しんでいる。推し活は、コロナの時期をきっかけに始めた。ちょうどその頃、補聴器を新しくして、よくきこえに合わせて調整してもらい、音楽がよく楽しめるようになったこともある。テレビから流れる人の声も色々な声があることがわかるようになって、楽しめることが増えた。昔からジャニーズが好きだったが、本格的に推し活するようになった。
また、デフフットサルも同じ療育施設出身の友人に勧められて始めたら、楽しくてはまってしまった。チームにも入って、試合もしている。仲間とのコミュニケーションも楽しい。同じきこえにくい仲間として大切な仲間だ。
<息子のこと>
息子は、私のきこえにくさについて一番理解してくれている。手話はできないが、指文字は教えた。以前、授業参観の時、ねむそうにしていたので、指文字で「ねるな」と伝えたら、指文字で「ねむい」と返ってきた。できるじゃんと思ってうれしかった。声がなくても家族で通じ合える方法があることは、とてもうれしい。二人で旅行した時は、母親の私がホテルの人の話を聞き返していると、代わりにさっと応答してくれたりする。いつもは、あまりやらないが、いざとなると助けてくれる。
また、息子は、専門学校の卒業制作では、指文字や手話のことについて動画を作っていた。全く知らなかったので、それを見た時は、感動して泣いてしまった。彼は、今就活中だが、彼のやりたいようにまかせている。お互いに自立した人間として、よい関係が築けていると思う。
<あとがき>
MISAさんは、インタビューが終わった後も、推しのライブがあるからと、嬉しそうに帰って行った。
先日は、青梅マラソンにも参加、完走したそうだ。迷う前に申し込むのだそうだ。エネルギッシュだ。スポーツも楽しみ、ライブも楽しみ、息子さんとの旅行も楽しむ。活き活きして活動的だ。
インタビューして、彼女がめまいや聴力低下の発作に3度も襲われ、その度に長期入院をしてきたことを知り、改めてつくづく大変だっただろうなと思った。めまいが続けば、日常生活には大きな支障が出る。聴力の低下への不安も少なくなかっただろう。
幼児期は、比較的補聴効果も良好で、言葉の発達もスムーズだったので、私たち支援者もどちらかと言うと、楽観的に捉えていて、彼女が何度もこのようなめまいと聴力低下に悩まされることになるとは予測していなかった。
現在では、難聴の原因や種類がかなり解明されてきているので、めまい、聴力低下の可能性が予見できることが多くなった。それでも個人差もあり、正確な予見は簡単ではないのだろうと思う。長期的に安定して頼れる耳鼻科の主治医がいることは、大切なことだと改めて思う。
MISAさんの「補聴器は隠しちゃダメ!」、「初めが肝心」、「してほしいことは言わないとダメ」などということばは、わかっちゃいるけど・・ねえ、というのが、多くの人の感じるところではないだろうか。その潔さは、どこからくるか・・・?彼女の話をきいていると、自分に対する自信のようなものが確固としてあるんじゃないかという気がした。
確かにきこえにくいけど、それ以外のコミュニケーションの力や状況理解の力をフルに活用する。周りの人たちの気持ちも汲み取り、自分のこともわかってもらうように働きかけられる。それが彼女の自信の裏付けになっているのではないか。
もう一つは、相手に求めすぎないバランス感覚もある。完全に理解されるのは、無理。80%理解されればいい。理解を求めて努力はするが、あとは自分が努力する。という自助努力の精神も持っている。
バランス感覚と言えば、高校の時、頑張って生物のテストで60点取った。でも、先生がもっと頑張れと言った。そこで彼女は、それ以上頑張ることはやめた。それもバランス感覚だと言ってもいい。先生のいうことをきいて、もっとがんばって、自分を潰すようなことはしないのだ。実は、支援者としては、ここはちょっと複雑だ。高校時代、もっと教員の方々に、きこえのことを理解してほしかったなとは思う。今より合理的配慮は乏しかったのは、やはり残念に思う。
それから、高校時代に、聴力低下を起こし、浅い付き合いの友達しかできなかった時、手話でのやりとりをする付き合いの方が楽しいと思った、というのもバランス感覚だと思う。きこえる人に張り合うとか、同じことをするというこだわりはない。また、彼女のセンサーには、成績で褒められるよりも、自分が楽しいことを発見する感知力があり、それを素直に選択できる力があるといえるのではないだろうか。それからご家庭も彼女の選択に強引に介入することはなく、彼女の選択を尊重したのだろうと推測する。
息子さんを、女手一つで大人になるまでちゃんと育てあげた責任感も強いし、息子さんを大人として尊重し、就職活動への口出しもしないという姿勢も、あっぱれと思う。もちろん背後にご実家の支えがあったと思うが、彼女の姿勢には、我々が学ぶものがたくさんあるような気がする。
若くして子育てを終えたわけなので、これからは、彼女が自分のために思い切り楽しみを見つけ、もっともっと楽しい人生を送るのを応援していきたい。
動画を視聴した方々にお寄せいただいた感想は、次の回にアップします。