本突き鑿八分・清久作
普通の「面取り」でも「鎬」でもない、「山蟻型」の突き鑿です!
別打ちと言う部類に入るのかな?

しかも、普通の山蟻鑿のコバの角度は60度なのですが、この鑿は違います。
お願いして??度に作ってもらいました。
何故この角度なのか?
男前だから(≧ω≦)bって理由もありますが、一番の理由は、「シャチ栓道」を刻む際、かなり早く正確に刻めるからです(^^)
シャチ栓継ぎで、この山蟻型本突き鑿は手放せまん(≧ω≦)b
ホゾ穴の中の、僅かな滑り勾配の刻みで、素晴らしい活躍をしてくれる。
もうー気持ち良いくらいズバズバと素早く、正確に刻める。

この見事な、糸コバ!
そして、切れ味の男前さ!この鑿を注文した当時は、どれだけ大変かまったく知らなかったが、今はそれなりに、少しは分かるつもりです(^^;;
??度なんて、細かい注文を聞いて頂き、清久さんには感謝の気持ちで一杯です!
大工人生が大きく変わるキッカケになった、「清久作」
注意・・・この本突き鑿をお願いした当時は、本突き鑿で家紋バージョンはまだ採用されていませんでした。
しかし、突き鑿の焼き戻し温度なのです(^^)
続く
ランキングに参加してます!
出来ればポチ↓と応援お願いします!ポチ↓
 にほんブログ村
にほんブログ村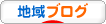 にほんブログ村
にほんブログ村
普通の「面取り」でも「鎬」でもない、「山蟻型」の突き鑿です!
別打ちと言う部類に入るのかな?

しかも、普通の山蟻鑿のコバの角度は60度なのですが、この鑿は違います。
お願いして??度に作ってもらいました。
何故この角度なのか?
男前だから(≧ω≦)bって理由もありますが、一番の理由は、「シャチ栓道」を刻む際、かなり早く正確に刻めるからです(^^)
シャチ栓継ぎで、この山蟻型本突き鑿は手放せまん(≧ω≦)b
ホゾ穴の中の、僅かな滑り勾配の刻みで、素晴らしい活躍をしてくれる。
もうー気持ち良いくらいズバズバと素早く、正確に刻める。

この見事な、糸コバ!
そして、切れ味の男前さ!この鑿を注文した当時は、どれだけ大変かまったく知らなかったが、今はそれなりに、少しは分かるつもりです(^^;;
??度なんて、細かい注文を聞いて頂き、清久さんには感謝の気持ちで一杯です!
大工人生が大きく変わるキッカケになった、「清久作」
注意・・・この本突き鑿をお願いした当時は、本突き鑿で家紋バージョンはまだ採用されていませんでした。
しかし、突き鑿の焼き戻し温度なのです(^^)
続く
ランキングに参加してます!
出来ればポチ↓と応援お願いします!ポチ↓
ちょっと思うところがあり、米松を削った。
鉋は広島の鍛冶屋、石社さんの鉋刃
研ぎ方を変えたり押さえ金の利かせ方を変えたり
押さえ金の利かせ方で引き具合は重くならない
引きの重さは、削る木の種類・刃の出具合・研ぎ上がり方・など影響が大きい
1番影響が大きいのは「刃の研ぎ上がり」
時々、大工道具の本に書いてある、押さえ金を利かすと引きが重いと言うのは正解とは違う。
単純に考えて、一枚鉋は仕上げ削りで使い、逆目や刃口の関係で刃は僅かに出す使い方。
しかし二枚鉋は、仕上げ削り以外でも使い、逆目も出にくく刃口が広くても使え、刃も出し気味にでも使える。
この違いで、一枚鉋は引きが軽く、二枚鉋は引きが重い=押さえ金が重さの原因と解釈してしまった可能性が高い。
昔、押さえ金の耳を立てると引きが重くなると聞いた事がある、その頃から疑問を感じていた。
押さえ金の耳の高さは関係ないと思う。
多分、押さえ金の耳を立て固めにし、鉋の刃先に押さえ金を攻めると、鉋刃の出具合も変わり押さえ金の影響と勘違いした人が多い?
また、仕込みが緩い鉋の場合は、押さえ金が固いと鉋刃が押されて、仕込み勾配も若干きつくなり、引きの重さに繋がる。
故に目が悪い事も影響すると思う
平らな上で、カタカタ言いってるぐらい歪んだ鉋台で、台直し鉋も持たず、刃口が3mm以上開いた仕上げ鉋を使って、鉋を語るなと言いたい。
鉋は広島の鍛冶屋、石社さんの鉋刃
研ぎ方を変えたり押さえ金の利かせ方を変えたり
押さえ金の利かせ方で引き具合は重くならない
引きの重さは、削る木の種類・刃の出具合・研ぎ上がり方・など影響が大きい
1番影響が大きいのは「刃の研ぎ上がり」
(刃の出具合が同じ場合)
他にも影響する事な多くある
しかし同じ条件なら二枚鉋の利かせ具合は引きの重さに関係ない。
他にも影響する事な多くある
しかし同じ条件なら二枚鉋の利かせ具合は引きの重さに関係ない。
時々、大工道具の本に書いてある、押さえ金を利かすと引きが重いと言うのは正解とは違う。
単純に考えて、一枚鉋は仕上げ削りで使い、逆目や刃口の関係で刃は僅かに出す使い方。
しかし二枚鉋は、仕上げ削り以外でも使い、逆目も出にくく刃口が広くても使え、刃も出し気味にでも使える。
この違いで、一枚鉋は引きが軽く、二枚鉋は引きが重い=押さえ金が重さの原因と解釈してしまった可能性が高い。
昔、押さえ金の耳を立てると引きが重くなると聞いた事がある、その頃から疑問を感じていた。
押さえ金の耳の高さは関係ないと思う。
多分、押さえ金の耳を立て固めにし、鉋の刃先に押さえ金を攻めると、鉋刃の出具合も変わり押さえ金の影響と勘違いした人が多い?
また、仕込みが緩い鉋の場合は、押さえ金が固いと鉋刃が押されて、仕込み勾配も若干きつくなり、引きの重さに繋がる。
仕込みが緩いのに押さえ金で上から押さえると、仕込み溝から離れて浮いた状態になり刃が安定しないので重く感じる。
引きの重さに一番影響するのは刃の出具合。
引きの重さに一番影響するのは刃の出具合。
故に目が悪い事も影響すると思う
目が悪いと刃先の僅かな調整が見えない
それと、鉋台の台下を半年に一度ぐらいしか手入れしない、狂った鉋台を使って削る方は論外(笑)
それと、鉋台の台下を半年に一度ぐらいしか手入れしない、狂った鉋台を使って削る方は論外(笑)
平らな上で、カタカタ言いってるぐらい歪んだ鉋台で、台直し鉋も持たず、刃口が3mm以上開いた仕上げ鉋を使って、鉋を語るなと言いたい。





























