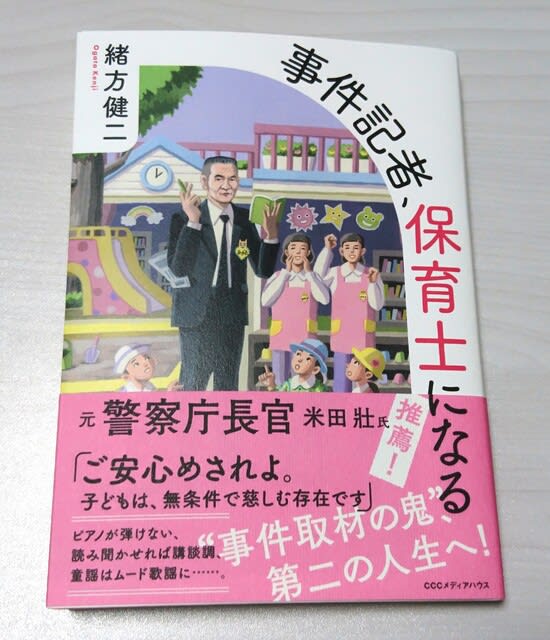このブログ、実はぷらら時代からやっていたんですが
「X」を始めてから、すっかりおろそかになってしまい、おサボリブログになっています。
携帯電話がスマートフォンに替わってからは、SNSが著しく発展し、
指先をちょっと動かせば、あれやこれやと情報がサクサク入ってきて、正直、退屈なんてものは皆無。
ニュースはもちろん、動画なんてYouTubeを開けば、アルゴリズムにより、自分が興味あるモノを提供してくれる。
SNSでメッセージを発信すれば、世界中の誰かとつながることができたり
今では、日々の生活に欠かせないアプリの登場で、スマホ1台が手元にあるだけで完結できるような便利さに。
こどもの時に描いていた〇十年後の未来。
自動車は空を飛んではいないものの、時計がコンピューターになったり、メガネがダイナミックな映像を見せてくれたり
ドラえもんのような世界が、少しずつ現世界に近づいている感に驚きつつ、自分もそれだけ年を重ねてしまった
時間の長さを感じられずにいられません(笑)
自分が好きなことの中に「読書」がありますが、その読書も今ではスマホやタブレットで読む人も増えています。
でも自分はどちらかというと、紙で読みたい派。
ページをめくる作業が好きなのと、紙の匂いが好きですw
本屋さんへ行くと、独特の紙の匂いがあって、書店の入口の自動ドアが開くといつもワクワクしっぱなしです。
冒頭が長くなりましたが、今回書き記しておきたいと思った本は・・・

福場将太さんの『目の見えない精神科医が、見えなくなって分かったこと』 サンマーク出版
医学部時代の臨床実習中に目の病気が見つかり、32歳の時に視力を失った著者。
お医者さんなのに目が見えない。
一般人としては、致命的な出来事なのではと思うのですが、
目が不自由なお医者さん、看護師、心理士、理学療法士、言語聴覚士など、
医療や福祉関係で活躍されている方々の存在を知り、精神科医を志したとのこと。
目が見えるからこそ、見えるもの。
目が見えるからこそ、見えないもの。
目が見えないからこそ、見えないもの。
目が見えないからこそ、見えるもの。
この4つ、深くないですか?
目が見えるからこそ、当たり前のように見える
目が見えているのに、気付いていない、あえて見ようとしない
目が見えないからこそ、見たくとも見られない
目が見えないからこそ、何かに気付く、感じたりする などなど。
著者は、本の中で、こんなことも綴っています。
「SNSって見る必要ありますか?」
著者は、見えないけれど、特段に困ることはないとのこと。
日々の生活にかなりの比重を占めている感のあるSNS社会。
例外なく、自分もどっぷりハマっている1人です。
スマホやPCを覗いては、さまざまな情報が目に飛び込んできますが
その中には不確定情報やデマもあり、そんな情報ほど広く拡散されてしまい
時には疑心暗鬼になり、不安になり、心が疲弊してしまう。
自分は「X」でもこのブログと同様にボヤくのがメインですが
動画を見て、日々の学びのためにも利用しています。
でも情報の過剰摂取でアンバランスにならないように、気をつけねばと、ハッとした1文でした。
また著者は、医師国家試験を不合格になり、リベンジした経験をしています。
やりたいことをやってみよう、会いたい人に会ってみようなど
自分の好奇心の思うままに行動し、自分ができることは何か?と模索し、再度合格を勝ち取りました。
チャレンジとバイタリティーあふれる著者のエピソードを読んでいると
目が見えなくても、心が診えるお医者さんの言葉は、
目が見えていても、他人の心をちゃんと見ていないかもしれない自分にとって、凄く注意喚起づけられるものばかりでした。
SNSを開くと、痛々しい言葉で、スマホの向こうにいる見えない相手を傷つける投稿を見ることもあります。
その言葉はまさに鋭い刃のよう。
よく耳にする「メディアリテラシー」を深めたり、より理解をすることも必要ですが
その中に少しだけでも「思いやり」を加えることも大事なのかなと。
目に見えないからこそ、気付くことがあるのなら
目に見えるからこそ、気付けることがある
読了後はそんなことを感じた1冊でした。
では、どうもおじゃまいたしました、へっくしょん。