牛山博士がやったとおりの事を牛山博士の立ち会いの下で、公開実験してみること。
そして、みんながそれを覗く。
こんな簡単なことを「どうして」やれないのだ。
という話なのですが。じつに簡単、「鼻くそ論」だと一笑して吐き捨てる癌研の権威者がその鼻くそ論を「一刀両断に切り捨てる」機会を国費を出してやるからやれと言うのに、
絶対にそれをやらなかった、厚生省と癌研の権威。
40年も持たしてきたというのは、やっぱり一般大衆がアマちゃんだからでしょうか。
こんなにだましやすいニッポンのイッパンタイシュウは世界一!!
!!
なのか?
え? イッパンタイシュウは完全に信者ですから? 自分では考えないんですよ。
与えられた教義(医学)にこれっぽちでも疑いも無い、純真無垢なのですよ。
ほう、純真ねえ? 裏返せば・・・無能○○?
うううむ。これは自分に来るなあ・
宗教信者の体験はこういう事がよく分かる。教義に、教祖に疑問を持つものは真の信者では無い・・なのだ。
自分で判断することを止めてしまうのだ。だから一つおかしな事が起こっても、それは無視してしまう。
理屈など要らないのだ。ただただ「信じ切って生きる」こと。
これが信者の神髄なのだから。
とすると、
イッパンタイシュウ人もこの厚生省と医学界のお偉いさん方も同じなんだろうか?
それはちょっと違うだろう。
一般の医師達はそうであっても、上の方は別の理由があるのだろうね。
ーーーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーーーーーー
○齋藤(憲)委員
それは、SICをいじった人はたくさんあるんですよ。
SICの否定論というものは、私はやってみた、私はやってみたなんだ。そうじゃないんです。
私の要求しているのは、なぜ牛山博士にやらせぬかということです。
ガラス張りの中で。
一体あらゆる生産事業というものは、特許権よりはノーハウが大切なんです。
それを、SICを取り扱ったこともない者が、どういう観点でもってSICの実験をやるのかわからぬ。
それでマイナスだという。
それは発明者を冒讀するものです。
なぜ一体発明者にやらせないんだ。
だから私が要求しておるのは、
ガラス張りの中でSICの発明者である牛山博士にやらせなさい。
そうして、顕微鏡はみんなでのぞけばいいじゃないか。
ところが、
私やりました、私やりましたというが、
一体だれが証人としてそれを見ておったのです。
そういうことは発明者を冒讀する実験というものです。
なぜ一体ガラス張りの中ではっきりした体制でもってやれぬのか。どうなんです。
○塚本説明員 私がいま申し上げましたのは、牛山さんがおつくりになったSICを使って、確かなガン患者に用いて、その効果を見たという意味で、これは別に牛山氏のそのつくる過程についていろいろ議論したわけではございませんけれども、その結果がネガチブだったということを申し上げたのであります。
○齋藤(憲)委員
私が言っておるのは、
SICが病人にきいたとかきかないということを問題にしておるんじゃない
ということを言っておるのでありまして、
SICをつくる過程において、
点菌が球菌になり、球菌が桿菌になって、
そうして、その代謝産物の精製物がSICになっておるんだ
という牛山博士の主張に対し、田崎博士は、
そんなばかなことはない、点菌が球菌になり、球菌が桿菌になるなんていうことは、カエルがヘビになったのと同じことだから、それは鼻くそだと言った。
その実験をやりなさいと言っておる。
それをやらないのです。
だから、
それだけ学問上において大きな差異を来たしておるところのものに対して調整費を出すから実験をやってくれ、
しかもガラス張りでやってくれ、
その発明者がみずから立って実験をやるやつを、
周囲から正当な実験であるか実験でないかということを
はっきり監視しながら立ち合い実験をやってくれ
というのに、
厚生省はやれない。
そういうことがあったんでは私は研究費というものははっきりした体制において使われていないのじゃないかと思うのです。
それはセンターの病院長としてどうお考えになりますか。
○塚本説明員 どうもSICに関してしろうとだものですからお答えがあまりうまくできないかもしれませんが、いまのように球菌が桿菌になったり、また、それがどうなるとかいうようなことが、そういう実験の間に行なわれ、それがガンにきくというような、そういうことまでわれわれの常識は進んでおりませんので、それは、つまりできたもの自身が効果があるないでこの段階では判定するよりしようがないじゃないかと思います。ただ、細菌学的には非常にそういうことは奇妙なことで、おそらくそういう意味で故田崎博士がそういう極言を使ったという形であらわしたのではないかと想像いたします。
○齋藤(憲)委員
これは水かけ論になりますからやめますが、
点菌が球菌に成長し、球菌が桿菌に成長するということがないと言うなら、
それは、ダーウィンの進化論というものはのっけから否定してかからなければならぬ。
そうでしょう。
そういうことがあり得るかあり得ないかということを確かめるのが実験なのですから、
SICがガンにきくとかきかないとか、そんなものはわれわれ問題にしていません。
そういうことでこの論争を科学技術振興対策特別委員会で取り上げたんじゃないのです。
はたしてそういう現象というものが微生物の世界に
あるのかないのか
ということを追求しよう
ということが論争の焦点であった。
それを厚生省がやれないというなら、
微生物というものの進化というものに対して
厚生省は何らの責任も興味も持っていないということだな、
逆から言うと、
やらないんだから。
尾崎医務局長に対してこれは執拗に迫っておるが、
どうしてもやると言わない。
そうして最後に尾崎医務局長が私に言ってきたのは、
何とかプライベートにやらしてくれ。
私は、プライベートに実験なんかやってもらう必要はない、
やはり公式の実験をやってもらうということを要求したが、
とうとうやれなかった。
だから、これは今後もひとつ問題として残しておきたいと思います。
〔内海委員長代理退席、委員長着席〕
いずれ文書なり何なりで大臣あてに要望しておこうと思っておりますから、あまりこういう問題で時間をとるというと本論に入らないことになりますからやめます。
ところが、この
第五十一回国会科学技術振興対策特別委員会の議事録第十四号
というのを読みますと、
きょう参考人としておいでを願いました森下敬一博士の参考人としての陳述がここへ出ておるのでありますが、
これを読みまして、一体こういう陳述がこの委員会で行なわれたのに対し、どうして問題にならないでこれがほっておかれるかということです。
というのは、当時の文部事務官の渡辺大学学術局情報図書館課長も来ておられます。
これはどういう関係で来られたか。
厚生事務官の公衆衛生局企画課長の宮田千秋さん、
厚生事務官、医務局総務課長の中村一成さん、
厚生技官の国立がんセンター病院長、
それから牛山さんと、いろいろな人が出ておられますが、
ここで森下博士が陳述をしておられるのです。
これは私落選しておるときですから、知らなかったのです。
そうしたところが、こういう本を私は手に入れたのです。
こういう「血液とガン」という本があるから手にとってみたところが、社会党の原代議士が委員長の席についておる。
これはまさしく部屋も国会の委員会ですね。
ところが、うしろをひっくり返してみたところが、
第五十一回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録と書いてある。
それで非常に興味を持って私は読みました。
ところが、これはたいへんなことが書いてある。
一体なぜこれが物議の種をかもさないで平穏に過ごされておるのかということであります。
それでお忙しい中を御本人の森下博士においでを願って、きょうはわずかな時間でありますけれども、ここでひとつ論争の種を植えておきたい。
きょう一回で終わらないですよ、大問題ですから。
第一に、森下博士の国会における陳述というのは、
「このガン問題というのは、私たちが十年ほど前から提唱しております新しい血液理論というものを土台にしなければ、ほんとうの対策というものは立てられないのではないかというような考え方を持っております。」
こう述べておられるですね。
そうして、
血は骨髄でできるものではない。
骨髄で血ができると考えておるのがいまの医学のガンだ、血は腸でつくられるのだ、
こういうことが一つですね。
それから、
ガン細胞は分裂増殖しない。
それから、
赤血球は可逆的な作用を持っておる。
まだほかにも書いてございますが、時間もございませんから私なるべく簡潔にきょうの焦点をしぼりたいと思うのでありますけれども、
森下博士に伺いたいのですが、一体われわれしろうとは、食ったものが血になるのだと、こう考えておる。
それは食ったものが血になるのでしょう。その食ったものが血になるということは、胃と腸とでもって血をつくるのだと、
こう考えておる。
なぜ一体事新しくここへ血は腸でできるのだということ、いわゆる腸の血造説を持ち出しておられるのか。
ほんとうに現在の医学では、血は骨髄でできると考えておるのですか、それをひとつ伺いたいのです。
-----------------------以上引用終わり--------------------------------
第058回国会 科学技術振興対策特別委員会 第6号
昭和四十三年三月二十一日(木曜日)
URL:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0560/05803210560006c.html
そして、みんながそれを覗く。
こんな簡単なことを「どうして」やれないのだ。
という話なのですが。じつに簡単、「鼻くそ論」だと一笑して吐き捨てる癌研の権威者がその鼻くそ論を「一刀両断に切り捨てる」機会を国費を出してやるからやれと言うのに、
絶対にそれをやらなかった、厚生省と癌研の権威。
40年も持たしてきたというのは、やっぱり一般大衆がアマちゃんだからでしょうか。
こんなにだましやすいニッポンのイッパンタイシュウは世界一!!
!!
なのか?
え? イッパンタイシュウは完全に信者ですから? 自分では考えないんですよ。
与えられた教義(医学)にこれっぽちでも疑いも無い、純真無垢なのですよ。
ほう、純真ねえ? 裏返せば・・・無能○○?
うううむ。これは自分に来るなあ・
宗教信者の体験はこういう事がよく分かる。教義に、教祖に疑問を持つものは真の信者では無い・・なのだ。
自分で判断することを止めてしまうのだ。だから一つおかしな事が起こっても、それは無視してしまう。
理屈など要らないのだ。ただただ「信じ切って生きる」こと。
これが信者の神髄なのだから。
とすると、
イッパンタイシュウ人もこの厚生省と医学界のお偉いさん方も同じなんだろうか?
それはちょっと違うだろう。
一般の医師達はそうであっても、上の方は別の理由があるのだろうね。
ーーーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーーーーーー
○齋藤(憲)委員
それは、SICをいじった人はたくさんあるんですよ。
SICの否定論というものは、私はやってみた、私はやってみたなんだ。そうじゃないんです。
私の要求しているのは、なぜ牛山博士にやらせぬかということです。
ガラス張りの中で。
一体あらゆる生産事業というものは、特許権よりはノーハウが大切なんです。
それを、SICを取り扱ったこともない者が、どういう観点でもってSICの実験をやるのかわからぬ。
それでマイナスだという。
それは発明者を冒讀するものです。
なぜ一体発明者にやらせないんだ。
だから私が要求しておるのは、
ガラス張りの中でSICの発明者である牛山博士にやらせなさい。
そうして、顕微鏡はみんなでのぞけばいいじゃないか。
ところが、
私やりました、私やりましたというが、
一体だれが証人としてそれを見ておったのです。
そういうことは発明者を冒讀する実験というものです。
なぜ一体ガラス張りの中ではっきりした体制でもってやれぬのか。どうなんです。
○塚本説明員 私がいま申し上げましたのは、牛山さんがおつくりになったSICを使って、確かなガン患者に用いて、その効果を見たという意味で、これは別に牛山氏のそのつくる過程についていろいろ議論したわけではございませんけれども、その結果がネガチブだったということを申し上げたのであります。
○齋藤(憲)委員
私が言っておるのは、
SICが病人にきいたとかきかないということを問題にしておるんじゃない
ということを言っておるのでありまして、
SICをつくる過程において、
点菌が球菌になり、球菌が桿菌になって、
そうして、その代謝産物の精製物がSICになっておるんだ
という牛山博士の主張に対し、田崎博士は、
そんなばかなことはない、点菌が球菌になり、球菌が桿菌になるなんていうことは、カエルがヘビになったのと同じことだから、それは鼻くそだと言った。
その実験をやりなさいと言っておる。
それをやらないのです。
だから、
それだけ学問上において大きな差異を来たしておるところのものに対して調整費を出すから実験をやってくれ、
しかもガラス張りでやってくれ、
その発明者がみずから立って実験をやるやつを、
周囲から正当な実験であるか実験でないかということを
はっきり監視しながら立ち合い実験をやってくれ
というのに、
厚生省はやれない。
そういうことがあったんでは私は研究費というものははっきりした体制において使われていないのじゃないかと思うのです。
それはセンターの病院長としてどうお考えになりますか。
○塚本説明員 どうもSICに関してしろうとだものですからお答えがあまりうまくできないかもしれませんが、いまのように球菌が桿菌になったり、また、それがどうなるとかいうようなことが、そういう実験の間に行なわれ、それがガンにきくというような、そういうことまでわれわれの常識は進んでおりませんので、それは、つまりできたもの自身が効果があるないでこの段階では判定するよりしようがないじゃないかと思います。ただ、細菌学的には非常にそういうことは奇妙なことで、おそらくそういう意味で故田崎博士がそういう極言を使ったという形であらわしたのではないかと想像いたします。
○齋藤(憲)委員
これは水かけ論になりますからやめますが、
点菌が球菌に成長し、球菌が桿菌に成長するということがないと言うなら、
それは、ダーウィンの進化論というものはのっけから否定してかからなければならぬ。
そうでしょう。
そういうことがあり得るかあり得ないかということを確かめるのが実験なのですから、
SICがガンにきくとかきかないとか、そんなものはわれわれ問題にしていません。
そういうことでこの論争を科学技術振興対策特別委員会で取り上げたんじゃないのです。
はたしてそういう現象というものが微生物の世界に
あるのかないのか
ということを追求しよう
ということが論争の焦点であった。
それを厚生省がやれないというなら、
微生物というものの進化というものに対して
厚生省は何らの責任も興味も持っていないということだな、
逆から言うと、
やらないんだから。
尾崎医務局長に対してこれは執拗に迫っておるが、
どうしてもやると言わない。
そうして最後に尾崎医務局長が私に言ってきたのは、
何とかプライベートにやらしてくれ。
私は、プライベートに実験なんかやってもらう必要はない、
やはり公式の実験をやってもらうということを要求したが、
とうとうやれなかった。
だから、これは今後もひとつ問題として残しておきたいと思います。
〔内海委員長代理退席、委員長着席〕
いずれ文書なり何なりで大臣あてに要望しておこうと思っておりますから、あまりこういう問題で時間をとるというと本論に入らないことになりますからやめます。
ところが、この
第五十一回国会科学技術振興対策特別委員会の議事録第十四号
というのを読みますと、
きょう参考人としておいでを願いました森下敬一博士の参考人としての陳述がここへ出ておるのでありますが、
これを読みまして、一体こういう陳述がこの委員会で行なわれたのに対し、どうして問題にならないでこれがほっておかれるかということです。
というのは、当時の文部事務官の渡辺大学学術局情報図書館課長も来ておられます。
これはどういう関係で来られたか。
厚生事務官の公衆衛生局企画課長の宮田千秋さん、
厚生事務官、医務局総務課長の中村一成さん、
厚生技官の国立がんセンター病院長、
それから牛山さんと、いろいろな人が出ておられますが、
ここで森下博士が陳述をしておられるのです。
これは私落選しておるときですから、知らなかったのです。
そうしたところが、こういう本を私は手に入れたのです。
こういう「血液とガン」という本があるから手にとってみたところが、社会党の原代議士が委員長の席についておる。
これはまさしく部屋も国会の委員会ですね。
ところが、うしろをひっくり返してみたところが、
第五十一回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録と書いてある。
それで非常に興味を持って私は読みました。
ところが、これはたいへんなことが書いてある。
一体なぜこれが物議の種をかもさないで平穏に過ごされておるのかということであります。
それでお忙しい中を御本人の森下博士においでを願って、きょうはわずかな時間でありますけれども、ここでひとつ論争の種を植えておきたい。
きょう一回で終わらないですよ、大問題ですから。
第一に、森下博士の国会における陳述というのは、
「このガン問題というのは、私たちが十年ほど前から提唱しております新しい血液理論というものを土台にしなければ、ほんとうの対策というものは立てられないのではないかというような考え方を持っております。」
こう述べておられるですね。
そうして、
血は骨髄でできるものではない。
骨髄で血ができると考えておるのがいまの医学のガンだ、血は腸でつくられるのだ、
こういうことが一つですね。
それから、
ガン細胞は分裂増殖しない。
それから、
赤血球は可逆的な作用を持っておる。
まだほかにも書いてございますが、時間もございませんから私なるべく簡潔にきょうの焦点をしぼりたいと思うのでありますけれども、
森下博士に伺いたいのですが、一体われわれしろうとは、食ったものが血になるのだと、こう考えておる。
それは食ったものが血になるのでしょう。その食ったものが血になるということは、胃と腸とでもって血をつくるのだと、
こう考えておる。
なぜ一体事新しくここへ血は腸でできるのだということ、いわゆる腸の血造説を持ち出しておられるのか。
ほんとうに現在の医学では、血は骨髄でできると考えておるのですか、それをひとつ伺いたいのです。
-----------------------以上引用終わり--------------------------------
第058回国会 科学技術振興対策特別委員会 第6号
昭和四十三年三月二十一日(木曜日)
URL:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0560/05803210560006c.html












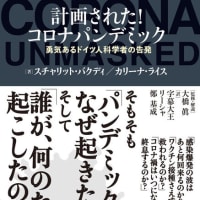
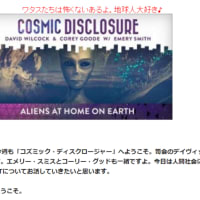
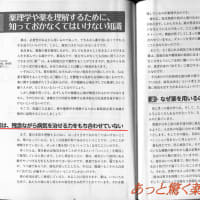
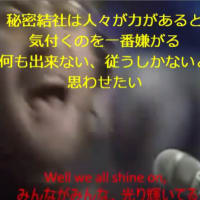
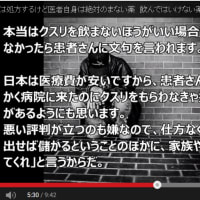

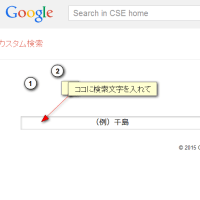
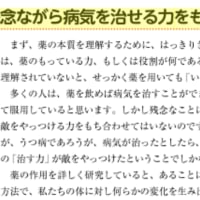







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます