感染症は「意志のある細胞」と微生物とのコラボレーション
もうイイって言うので出しました。(天の弱)
先回の引用のつづきです。
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
細胞に刻まれる人生
自己の形成において重要な時期である思春期についても、細胞の世界から定義すれば、「脳において、つなぎ換えが活発に行われる時期」ということができます。
思春期にもっとも劇的に変化するのは、体型でも性器でもなく、じつは脳です。
シナプスが多いといっても子どもの脳は、いわば「タコ足配線状態」です。不必要に冗長なつながりになっている神経細胞が少なくありません。そうした子どもの脳を大胆に整理するというのが、細胞の世界からみた思春期の大事な一面です。
ここまでみてくると、私たちの個としてのありように、細胞が深く関わっていることが明らかになってきたと思います。
私たちは個として生まれ、個としての体験を積み、個の特徴を磨き、そして変容させていきます。その変化を含めて、個性ということができるでしょう。
よく人生は川にたとえられますが、細胞世界から眺めると、人間もまた川のようなものです。
川の本質はそこを流れる水にあります。水がなければ、それは川でも何でもありません。大地に刻まれた溝にすぎません。しかし、本質を担う水はきわめて移ろうものです。上流から流れてきては下流へと去っていきます。二度と同じ水とはめぐり会いません。そんな動的なものが本質を担い、そして、川という実体をつくりあげているのです。
細胞も次々と移ろいます。再生系といわれる体細胞は代謝で入れ替わります。そのスピードはかなりのものです。入れ替わる細胞は1日3000億個といわれていますから、単純に計算すると、200日でほとんどすべての細胞が入れ替わっているということになります。
非再生系である神経細胞もめまぐるしく変わるという点では同じです。体験に応じてネットワークを柔軟につくり替えていました。
そうした変化を含んでなお、私たちは個として成り立っています。川と同じように、その存在を実体として感じることができます。いえ、そうした変化があるからこそ、私たちは個として成り立っているのかもしれません。動的なことこそ、生きているということではないでしょうか。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
よく分かんない?
ボクもデス。
全文よめば分かるかも・・
とにかく、細胞とは多田の部品ジャナイと佐藤さんも言うのです。
じゃ、佐藤の部品か?
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
ここでひとつ、細胞のさらに内側の世界を覗い、てみましょう。
理化学研究所生命システム研究センター長の柳田敏雄博士は、およそ40年間、細胞のなかの運搬役として知られる分子ミオシンの姿を捉えることに挑んできました。
細胞のなかには、さまざまある小器官のあいだを結ぶようにアクチンと呼ばれる構造物が張りめぐらされています。その上を動くのがミオシンです。小器官のあいだでタンパク質を運び、細胞の機能を維持する役割を担っています。
ミオシンは2本足の構造をもっており、その足を交互に出して「歩く」とされていました(図21)。その動きは規則正しく、あたかも精密機械のように動くという予測もありました。しかし、実際にアクチンの上を歩くミオシンの様子は誰もみたことがありませんでした。
壁になったのはその小ささです。ミオシンが動く様子を観察するには、生きたまま水溶液に入れた状態でなければなりません。しかし、シャーレの底にミオシンが乗ったアクチンを並べても、どうしても水やゴミなどがその上で動き回り、邪魔をしてしまいます。
「1分子ですからね。非常に邪魔物がたくさんあるので、ゴミのなかで1個のダイヤモンドを探すという感じなわけです」 柳田博士は、動く1分子を観察できる顕微鏡の開発から取り組みました。25年かけてつくりあげたのが「全反射照明蛍光イメージング顕微鏡」です(図22)。
顕微鏡といっても、大きな机いっぱいに広がる代物です。その机には、レーザーの太さを調整する絞りがいくつも並べられています。この顕微鏡の強みは、絞りによってレーザーの光をきわめて精密に調整できることです。発振器から出たレーザーは絞りを最大5回通って、20マイクロメートルまで細くされたのち、顕微鏡のなかに送り込まれます。そしてガラスに当たって反射します。このとき、わずかな光だけがガラスの上に染み出します。これが、顕微鏡の名前についている「全反射照明」ということになります。
柳田博士は、この光で限られた厚みだけ照らして、蛍光分子で標識したミオシンを浮かび上がらせたのです(口絵5)。その成果をもとに、ミオシンの移動するモデルがつくられました。
そのモデルを映像化してみると、「ミオシンの移動は規則正しいものだろう」という予想は大きく覆りました。その移動する様子は精密機械とは程遠いものでした。いいえ、それ以上に、妙に人間くさい歩き方でした。
ゆらゆら揺れながら、まるで踏み出す足を迷っているように進んでいきます。1歩1歩、不規則な動きをしながら、結果として少しずつ前に進んでいる感じなのです。たとえとしては、千鳥足という表現がぴったりです(図23)。
不規則な動きになる理由は、ミオシンが何もないところを動いているわけではないからです。細胞のなか、ミオシッのまわりには水分子など、さまざまな物質が詰まっています。そのなかで、足を踏み出して、次に進める場所を探しているからだと柳田博士はいいます。
「ミオシン分子がどれぐらいのスピードでどれぐらいの力を出せばいいかという指令はありません。つまり、誰かにコントロールされることもなく、ミオシン白身が決めないといけないわけです。自分自身で決めるときに一番いい方法というのは、やっぱり試行錯誤するということです。すなわち、ふらふらするという運動は試行錯誤には非常に有効であったということです」
この映像は、「細胞=部品」と考えることが、いかに実態とは違うか、能弁に語っています。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
なんだかよく分かんないけど。
「細胞=部品」じゃないってことを強調しています。
細かなことは本でも読んで、
「細胞には意思、意志がある」ということが分かれば
どうして、体内にいつも同居しているウイルスや細菌と付き合っているか、さらに身体の外からどうして取り込むのか?
どうして、細胞自身を破壊したり、微生物に破壊させたり、ウイルスに目印を付けさせたり(目印のある細胞を実行部隊である自己免疫細胞が破壊する)、どうして特定のウイルスだけが特定の部位(細胞群)に入り込めるのか?
どうして?どうしてなの?ねえ、どうしてなのよ?~~~~
そりゃあ、アンタ、娘っ子が戸を開けて待っているからじゃよ~(娘の両親談)
ただし、結ばれてめでたしめでたし? とならないけどね。
だって、夜這い野郎と一緒に娘っ子は壊れて逝ったとさ。
これでイッチガポ~~ントサケタ~(←これわかる人)
追記 (2019/01/20)
「癌と免疫ブログ」様より
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
ウイルスの感染メカニズムはいくつかあるのですが、
圧倒的に効率が高い通常の感染方法はこういうものです。
まず感染される特定の細胞は、特定ウイルスを受け容れる
レセプターをもっているのです。
ウイルスは、何でもかんでも感染するのではなく、
目印のレセプターにとりつき、そこから細胞に感染します。
特定のウイルスが通常パターンで感染する場合、
相手の細胞は特定のものと決まっているのです。
細胞の方から、ちゃんとウイルスを招き入れる仕組みをもっているのです。
ーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
ね、ウイルス夜這い論も当たらずとも遠からずでしょ。
窓開けていなければ入ってこないですよ、娘っこも招き入れる覚悟というか期待があるんですね。
でわ、どういう細胞がお出でお出でをしているのか?
もちろん、腐敗細胞、つまり毒素の多い細胞でしょうね。
そういう細胞が多いほど感染度も高く症状も激しくなりますね。
強毒性ウイルスとか毒性の強いウイルスなどと平気で言うい医療関係者はなにをもってウイルスに毒があるのか説明してください。無いんだから説明しませんでしょうけど。
毒があるのは身体の細胞にあるんでしょ。
そういう意味で感染症は僕たち次第なんですよ。
一番軽くて済むのはやっぱり風邪でしょう。
ときに、風邪がきっかけで死に至る人はかなりの毒を持ち合わせているのかも知れません。もしくは治療そのもの(薬毒を入れるから)が悪化させているのも一因でしょうね。
ボクらは微生物の海の中で生息中なんですから、もう絶対に逃れられないのですよ。
ならば、彼ら(彼女ら)に可愛がってもらうしかないでショ。
ウッフン~~~♪ 愛してチョウダイ!
「なにカンチガイしてんの? 最初っから愛してるジャン!。 発酵も腐敗もアナタ次第なのよ。腐敗も愛してる証拠なのね。ダメになってもまた出直して来なさい♪」
ということで、微生物曰く「これがワタシらの仕事です」
インデー婦 じゃない、In Deepブログ様より
人間にとって最も日常的で慈悲深い治療者は「風邪ウイルス」かもしれないこと。そして、薬漬け幼児だった私がその後の十数年経験した「免疫回復戦争」の地獄体験記
が急所を突いています。
ちょっと引用ーーーーーーーーーーーーー
ホイル博士は、「ヒトという種の進化のため」だという立場を持ち、
ちっぽけなウイルスが大きな生物を騙すのではなく、生物が自らの利益のために ----- 進化するために ----- 進んでウイルスを招き入れるのだ。
われわれは、免疫機構に対する考えを改めなければならない。免疫機構は、常に新参者を探しているが、それはわれわれの遺伝システムがそれを取り込むことが進化論的立場から価値があると認められるような新参のウイルスを探すためなのだ。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
意志のある細胞が自らアポトーシスを実現させるために特定のウイルスを選んで呼び込んでいる。
だれでもイイってわけじゃないっての。ワダスはあの人が入ってくるのを待つわ♪ 田舎夜這いむすめ談
ところで、正式の夜這い論として
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
男は前もって女に対し夜這いに行くことを通告しなければならなかったし、部屋の戸を開けるか開けないか受け入れるか受け入れないかの選択権は女の方にありました。
出典夜這いのある(あった)地域の父親は、娘の貞操をどう思っているのだろう? ... - Yahoo!知恵袋
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
選ぶ主権は娘(細胞)にあるのは共通しているとして、
まあ、オトコとオンナの夜這いは最終的には一緒になって子孫繁栄、一家繁栄、めでたしめでたし。
となるのですが、
ウイルスと細胞の夜這い論では、一緒になって滅んで行く美が、結局一家にとってはめでたしめでたし・・なんですが、難産というか苦しみが伴う美なんですねえ。
そこが分かんないと、夜這い野郎(ウイルス)はいつまでも嫌われものとしての立場があります。
熱は下げてはいけない、高熱になるとウイルスが退治されるので・・・という説も、あくまでウイルス悪者論ですよね。とにかくウイルスが悪い(細菌の方もですが)という固定観念が強すぎてねえ。
高熱になるとウイルスも役目が終わるって考えないのかな?
高熱になると、自身の免疫力(自己治癒力)だけで解決(自力)できる、だから高熱とウイルスの関係はよく出来ているのでしょう。どうして?って・・
そりゃ、そういう風に出来ちゃってるんだからショウガナイでしょ。
おおきな目でみないと「利益になるウイルス感染」ということが分からないんですねえ ドウシマショ?
まあ、分かるまでやるしかないでしょ・・・徹底的に逆襲くらうまで・・












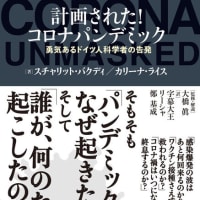
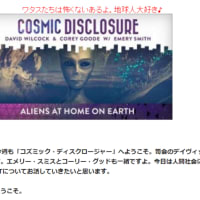
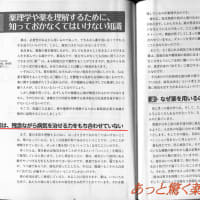
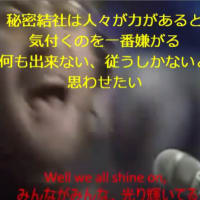
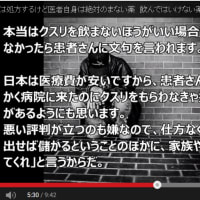

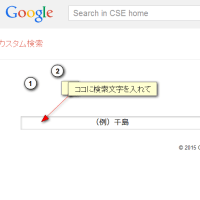
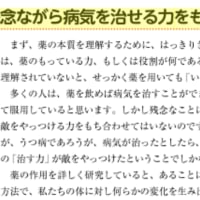








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます