
空前のボヘミアンラプソディーのヒットを受けて、すでにいろんなアーティストの同様の映画の制作が続々と発表されている。Netflixとはいえモトリークルーの伝記映画が出来ると聞いたときには耳を疑った。
ひで氏です。
ホイットニーヒューストンの映画もすでに公開されているそうだが、なぜあまり触手が動かないのかとふと考えてみると決定的な違いに気づいた。当たり前のことなのに、今まであまりちゃんと考えてこなかった、とても重要なラインが音楽伝記映画にはある。
それはドキュメントものとストーリーものの境界線だ。
この手の映画はやはりドキュメントシーンがどのくらいを占めるかでエンターテイメント映画としての位置付けが変わる。
ドキュメント要素が強い=実際の当時の映像使用率が高い
ということだと思う。これは一見良さそうだ。なぜなら、そのアーティストのファンはおそらくそういう見たことのない映像を見たいと思っているからだ。
だから作る方も「○○時間にも及ぶ未公開映像からアーティストの知られざる素顔に迫る!」という売り文句をつけて世に放ってくる。
これは一見制作側とファンにとってWin-Winに見えて実はそうでは無いのだ。というのも、思い返してみると、ドキュメンタリー形式のミュージシャン伝記映画の満足度というのはたとえコアなファンの間でも満足度が上がりにくい。
それはひとえに、「細切れ」だからだと思う。
実際の映像にこだわりそれを謳い文句にしている以上、もともと映画にするなどという目的で撮られていないものをなんとか一つのストーリーにしようとするのだから、どうしても同じような場面が何回も出てきたり何かが抜けたような瞬間が生まれたりする。そして足りない部分は誰かのインタビューで補足する。最初はおお、と思って見始めるが2時間もたない、というのが正直なところだ。結果、せめてファンは見てくれるはずと思って確実なマーケットを狙ったつもりがファンの間でも不発、ましてやファンでない人にヒットするはずもなく、映画史に名を残すこともなく消えていく…
単なる記録映像としての役割ならそれで充分かもしれないが、あくまで作品としての出口は興行が絡む「映画」なのだから、やはりアイデアが出た段階でドキュメント寄りにするのか、再現役者を使ったストーリーものに寄せるのかは何よりも大事な分かれ道となる。
ではストーリーものにするのが常に正解じゃあないか、と言われるかもしれないが、そうシンプルでもない。
ストーリーものに仕上げる場合は必ず「実際より美談」とか「実際はもっとひどかった」というような難癖がつくリスクが常について回る。今回のボヘミアンラプソディーにも、史実と違う点が色々と取り沙汰されているわけだが、
■現存メンバーの監修をかなりちゃんとうけている
■再現役者が神がかり的に似ている(特にメイ)
■ライブシーンをラストに、かつ惜しみなく集約した
■主人公の性的嗜好の揺れ動く様を物語の中心に置いた
というような要素が多少の現実とのギャップを全部吹き飛ばすくらい素晴らしかった。
まあ後からこうやってごちゃごちゃ言うのは簡単である。
尊敬すべきはゼロから作った製作者で、とても丁寧に仕事をした結果できた良い映画だったと思う。またQueenという「まあ知ってるけど詳しくはない」という人が圧倒的に多い完璧なバンドを選択したのではないかとも思う。これがフリートウッドマックだったら例えドラマチックさでQueenの50倍はすごいとしても、とてもこんなキレイに収まらないだろうと思う。
しかしボヘミアンラプソディが何もこういう映画の初めての成功例というわけではない。
そんなわけで私ひで氏が選ぶ、「ストーリー形式(ドキュメントでない)ロック伝記映画」2作品を紹介したい。
La Bamba (ラ・バンバ) - 1987年
ロックンロールという音楽がグイグイ来はじめたころ、リッチー・ヴァレンスがメキシコの民謡「La Bamba」をアレンジして一躍スターダムに登り詰める…という映画で、まーなんせサントラが素晴らしく、私ひで氏がこのサントラに入っている超絶スタンダードなロックナンバー、それもロスロボスをはじめブライアンセッツァーなんかがカバーするそれらの楽曲に中学生の頃に出会えたというのは本当に人生においてラッキーだったなと思う作品。またリッチー役を演じるルー・ダイアモンド・フィリップスそっくりの同級生がいて、めちゃくちゃカッコよくて羨ましいと思った笑。ちなみにこの映像で歌っているOoh My Headが私ひで氏の青春の1ページに加えられてからずっと後、Led Zeppelinの「Boogie with Stu」を聞いて「え?マジで?」となった。これはこれで何か色々問題があったらしい。興味がある人は聞き比べてみてください。
The Rose(ローズ) - 1979年
ジャニス・ジョップリンをモデルとした、Roseという破天荒な女性をベット・ミドラーが演じるという異常な映画。でもベットミドラーがジャニスを演じるという感じではなく、完全にローズという新しいキャラに設定して「これって完全にジャニスやんね」という暗黙の了解の元に描かれた異色の伝記スタイル。たぶんそうしないと、ベットミドラーの個性がジャニスの個性を越えてしまうからという判断があったんじゃないかと思う。衝撃のラストシーンは今も頭から離れる事はなく、もはやスタンダードになった超のつく名曲「Rose」はもちろんのこと、ライブシーンでの「When a Man loves a Woman」のMCからの入り…なんなん、この伸びは。シビれる!
音楽っていいね、と思う。歌いたくなる。
今月は盛りだくさん、ぜひ生音を聞きに来てください。
2月4日(月)ハウリンバー「The WAREHOUSE」
2月11日(月祝)中崎町コモンカフェ「The WAREHOUSE」
2月21日(木)The Alan Smithy Band presents Throwback Thursday


ひで氏です。
ホイットニーヒューストンの映画もすでに公開されているそうだが、なぜあまり触手が動かないのかとふと考えてみると決定的な違いに気づいた。当たり前のことなのに、今まであまりちゃんと考えてこなかった、とても重要なラインが音楽伝記映画にはある。
それはドキュメントものとストーリーものの境界線だ。
この手の映画はやはりドキュメントシーンがどのくらいを占めるかでエンターテイメント映画としての位置付けが変わる。
ドキュメント要素が強い=実際の当時の映像使用率が高い
ということだと思う。これは一見良さそうだ。なぜなら、そのアーティストのファンはおそらくそういう見たことのない映像を見たいと思っているからだ。
だから作る方も「○○時間にも及ぶ未公開映像からアーティストの知られざる素顔に迫る!」という売り文句をつけて世に放ってくる。
これは一見制作側とファンにとってWin-Winに見えて実はそうでは無いのだ。というのも、思い返してみると、ドキュメンタリー形式のミュージシャン伝記映画の満足度というのはたとえコアなファンの間でも満足度が上がりにくい。
それはひとえに、「細切れ」だからだと思う。
実際の映像にこだわりそれを謳い文句にしている以上、もともと映画にするなどという目的で撮られていないものをなんとか一つのストーリーにしようとするのだから、どうしても同じような場面が何回も出てきたり何かが抜けたような瞬間が生まれたりする。そして足りない部分は誰かのインタビューで補足する。最初はおお、と思って見始めるが2時間もたない、というのが正直なところだ。結果、せめてファンは見てくれるはずと思って確実なマーケットを狙ったつもりがファンの間でも不発、ましてやファンでない人にヒットするはずもなく、映画史に名を残すこともなく消えていく…
単なる記録映像としての役割ならそれで充分かもしれないが、あくまで作品としての出口は興行が絡む「映画」なのだから、やはりアイデアが出た段階でドキュメント寄りにするのか、再現役者を使ったストーリーものに寄せるのかは何よりも大事な分かれ道となる。
ではストーリーものにするのが常に正解じゃあないか、と言われるかもしれないが、そうシンプルでもない。
ストーリーものに仕上げる場合は必ず「実際より美談」とか「実際はもっとひどかった」というような難癖がつくリスクが常について回る。今回のボヘミアンラプソディーにも、史実と違う点が色々と取り沙汰されているわけだが、
■現存メンバーの監修をかなりちゃんとうけている
■再現役者が神がかり的に似ている(特にメイ)
■ライブシーンをラストに、かつ惜しみなく集約した
■主人公の性的嗜好の揺れ動く様を物語の中心に置いた
というような要素が多少の現実とのギャップを全部吹き飛ばすくらい素晴らしかった。
まあ後からこうやってごちゃごちゃ言うのは簡単である。
尊敬すべきはゼロから作った製作者で、とても丁寧に仕事をした結果できた良い映画だったと思う。またQueenという「まあ知ってるけど詳しくはない」という人が圧倒的に多い完璧なバンドを選択したのではないかとも思う。これがフリートウッドマックだったら例えドラマチックさでQueenの50倍はすごいとしても、とてもこんなキレイに収まらないだろうと思う。
しかしボヘミアンラプソディが何もこういう映画の初めての成功例というわけではない。
そんなわけで私ひで氏が選ぶ、「ストーリー形式(ドキュメントでない)ロック伝記映画」2作品を紹介したい。
La Bamba (ラ・バンバ) - 1987年
ロックンロールという音楽がグイグイ来はじめたころ、リッチー・ヴァレンスがメキシコの民謡「La Bamba」をアレンジして一躍スターダムに登り詰める…という映画で、まーなんせサントラが素晴らしく、私ひで氏がこのサントラに入っている超絶スタンダードなロックナンバー、それもロスロボスをはじめブライアンセッツァーなんかがカバーするそれらの楽曲に中学生の頃に出会えたというのは本当に人生においてラッキーだったなと思う作品。またリッチー役を演じるルー・ダイアモンド・フィリップスそっくりの同級生がいて、めちゃくちゃカッコよくて羨ましいと思った笑。ちなみにこの映像で歌っているOoh My Headが私ひで氏の青春の1ページに加えられてからずっと後、Led Zeppelinの「Boogie with Stu」を聞いて「え?マジで?」となった。これはこれで何か色々問題があったらしい。興味がある人は聞き比べてみてください。
The Rose(ローズ) - 1979年
ジャニス・ジョップリンをモデルとした、Roseという破天荒な女性をベット・ミドラーが演じるという異常な映画。でもベットミドラーがジャニスを演じるという感じではなく、完全にローズという新しいキャラに設定して「これって完全にジャニスやんね」という暗黙の了解の元に描かれた異色の伝記スタイル。たぶんそうしないと、ベットミドラーの個性がジャニスの個性を越えてしまうからという判断があったんじゃないかと思う。衝撃のラストシーンは今も頭から離れる事はなく、もはやスタンダードになった超のつく名曲「Rose」はもちろんのこと、ライブシーンでの「When a Man loves a Woman」のMCからの入り…なんなん、この伸びは。シビれる!
音楽っていいね、と思う。歌いたくなる。
今月は盛りだくさん、ぜひ生音を聞きに来てください。
2月4日(月)ハウリンバー「The WAREHOUSE」
2月11日(月祝)中崎町コモンカフェ「The WAREHOUSE」
2月21日(木)The Alan Smithy Band presents Throwback Thursday














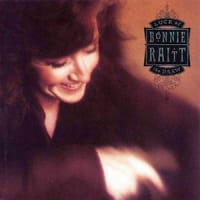


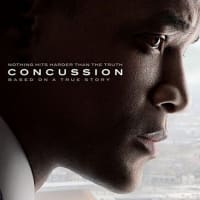
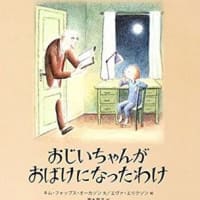


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます