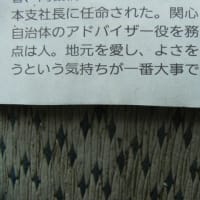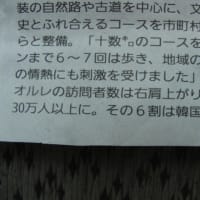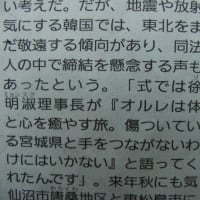天皇の本分は一に祭祀、ニに祭祀 他は不要です
h
ttp://blog.goo.ne.jp/mannizawa/e/8a7358483f90b0b0c3e15418a2996bd1より 一部抜粋
・・・・・・・ここから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宮中祭祀の基本姿勢は、13世紀前半の順徳天皇(第84代)が著された『禁秘抄』の冒頭に掲げてございます。
「一、賢所(かしこどころ)。凡(およ)そ禁中の作法、神事を先にし、他事を後にす。旦暮あけくれ敬神之叡慮解怠(えいりょけたい)無く白地(あから)さまにも神宮竝(なら)びに内侍所(ないしどころ)の方を以て、御跡(みあと)と為(な)さず」
すなわち
「宮中の作法はまず第一に神事、その後に他のことがあって、朝夕に神を敬い、かりそめにも伊勢の神宮、また賢所に足を向けて休むようなことがあってはならない」
そして、先帝の方々のご遺訓は守らねばならぬ、と詠まれたのが明治天皇です。
上つ世の御世のおきてをたがへじと 思ふぞおのがねがひなりける
御遺訓(おきて)を違わぬようにと心がけるのが、朕の願いである、という意味ですね。
宮中祭祀には、15世紀後半の応仁の乱以降は中絶したものがあり、また明治維新直後は途切れていたのですが、明治41年の皇室祭祀令で新しい祭祀が創出され現在に至ります。
それぞれの祭祀に対応する国の祝祭日が定められ、たとえば収穫祭である新嘗祭は、勤労感謝の日としてそもそもの意味を喪失しています。
(中略)
伝統の希薄化は、民族としてのアイデンティティの消滅への道であり、まさに71年前、GHQが目論んだ通りの道筋を宮中は辿っているようです。
明治天皇にも、昭和天皇にも国を祈り、民を想い祈るお歌がたくさんございますが、平成になってあまり見かけません。次代がどういう名称になるか解りませんが、次代には新天皇が祈りの和歌を詠まれることは絶えるのではないでしょうか。
・・・・・・・・・・ここまで・・・・・・・・・・・・