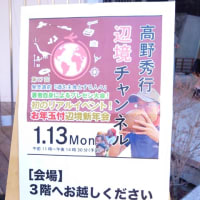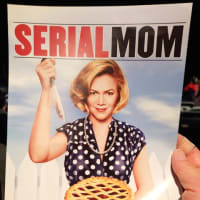最初は東博で狩野永徳の「檜図屏風」を見ようかと思っていたのだが、教職員証を忘れてきたんで、急遽向かいの東京都美術館へ(笑)
しかし、会場は大変混雑しています、の立て札が…。
むむ~。
確かに。
ぱっと見ではそんなに混み混みではないんですけどね。
なにせ、東京都美術館にありがちな、入場前の行列もないし。
じっと我慢しながら、粛々と流れに沿っていかないとまるで見えない、というほどでもなく。
でも。
絵の全体を見るには人が群がりすぎてるかも!
もちろん、他の技法の絵以上に、近くに寄って細かく観察するというのが必要。
なので、人が群がるのもやむなし。
とはいえ、他の技法以上に、かなり遠くから観察しないと、その技法の真価もわからないと思うんだな。
ま、点描画法に限らず、新印象派の前史というか参考みたいな位置づけで、冒頭にモネの作品が並んでいたけれど、1メートルの距離からでは、ただ絵の具が乱雑に塗られてるようにしか見えない。
でも3メートル、4メートル離れると、突然、恐ろしく透明感のある海の水が!!
ここ大事じゃん?
絵の具を混色すればするほど、色が濁ってしまう。
色を濁らせないためには、混色せず、そのままキャンバスにおいていって、目の中で色が混ざるようにすれば良い。
そのための技法なんだからさ。
ここんとこをうまく解決できる展示方法って、誰か編み出してくれませんかねぇ?
という不満を常に抱えたまま鑑賞…f(^_^;
今回、国内外の様々な美術館や個人からかき集めてきた、新印象派とその前後の作品をずらっと並べている点では、実に豪華だし、なかなかのもんじゃないですかね?
展示方法としては、時代順に並べて、どのように始まり、どのように変化し、どのようにその後の絵画に影響を与えたかがわかりますよ、という、とても教育的な内容。
なんだけど。
各ブロックの冒頭の説明とも、各作品の説明とも別に、展示室の所々に掲げられている背景説明のような文章が、妙に下手なレトリック満載の厨二文学みたいな感じで、読んでいてケツの穴がむずむずしますf(^_^;
さて、点描を始める前のスーラにしろ、ピサロにしろ、あまり面白くない(笑)
けど、順番的に、ここから始めるのが妥当なんでしょうね。
でもって、次のベルト・モリゾの「ブージヴァルの庭」が自由すぎf(^_^;
そして、今回の目玉だな、というのが、やはりスーラ。
というか、まさに、新印象派の中で最も重要な画家ですからね。
シスレーやシニャックと違い、若死にしてしまったために、新印象派絵画しか残っていない、とも言う…。
ポスターやチケットにも使われている「セーヌ川、クールプヴォワにて」は、「グランドジャット島の日曜の午後」に連なる作品。
ただし完成作であり、かつ、独立作品だというのは重要ですな。
だって、その後、「グランド…」の習作4枚が並んでいるけれど、さすがに習作だけあって、点描も粗い。
で。
本物は来ない、という…f(^_^;
この素晴らしいまでの肩すかし感(笑)
次の、理論的説明の展示は、見覚えのあるものが並んでいる。
当然、以前の新印象派展でも展示されていたから、前にも見た。
ってか、色相環って、常識なんだと思ってた(笑)
でも、ルイ・アイエの「灰色の空の習作」は三つとも面白い。興味深い。
で、スーラが夭折してしまったせいで、ここからはずっと、その後の新印象派。
中でも、マクシミリアン・リュスの「ルーヴルとカルーゼル橋、夜の効果」は、実に綺麗!!
まさに、混色しない効果を発揮していると言っていい。
光が本当に輝いて見える。
ジョルジュ・モレンの「日没」は、比較的風景画が多いように思える新印象派の中では、珍しいテーマかも。
もう一つのメイン、ポール・シニャックの「髪を結う女、作品227」。
これ、もう、TVで見ちゃったからなぁf(^_^;
よくわかるのはいい面でもありつつ、つまらなくもありつつ。
しかも、ここにはかなり人が固まっていて、じっくり見るのには不適。
さらになぜか、解説を読んで、ヘンないちゃもん(?)をつけてる人がいたり(笑)
と。
テオ・ファン・レイセルベルヘの「マリア・セート、後のアンリ・ヴァン・ド・ヴェルド夫人」がスゴイ!
点描で、ここまで精緻な人物画!!
この布の質感!!
と思ったら、すげー!!と思う人物画は、まだあった(笑)
この裏にズラ~リ!
このあたり、いくつかのコーナーを行きつ戻りつし、遠く近く眺めていると、実に楽しい♪
さて、2階に上がると、だんだんと点描の理論からはずれはじめ、好き放題の様相(笑)
アンリ=エドモン・クロスなんて、強烈すぎる色彩f(^_^;
でも、これが、フォービズムに繋がる、フォービズムを生んだ、というのは、非常に納得。
最後の、マティスやドランが、同じ延長線上にあることが、実によく理解できる。
美術史上の、壮大な実験だった、という感じかな?