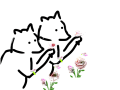小さい頃から、あれこれするのが苦手だ。
小学校の授業で、一時間毎に教科が変わるのにも、時間が来たらハイ終わりというのにも慣れなかった。
一日中算数とか一日中図工とかだったら良いなあと思っていた。
でも我慢はしていたので、学校では優等生とか言われて余計に疲れる事になった。
まあ勉強も好きなようにやめられないなら、それも苦痛だろうけど。
そういえば髙倉先生の教場では、進度もその人なりだったし、決まった稽古の時間内だったらいつ行っても良いし、いつ帰っても良かった。
でも、ひと通り稽古してそろそろお終いにしようかなと思っていると先生が「では〜を出してきて」とかおっしゃって次の稽古に進んだりする。
そういう時は決まって、ちょっと余裕があるけどまあそろそろお終いにしようかと思っている時だった。
気持ちがバレバレなのがいつも不思議だった。
たくさん稽古をしたあと教場の門を出て外の風に当たる。その時の爽快感が素晴らしかった。ただ帰りの駅の階段がつらかった。膝がガクガクした。
「一通り動いて疲れた後の稽古が本当の稽古になる」とそんな言葉を覚えているのだが、そういう事だったのだろう。
早く帰りたければ「今日は用事がありますので、終わりに致します」と言えばよかった。
それで先生が気を悪くなさることは決してなかった。
今は食事の支度だけ時間に間に合えば良いから幸せだ。何かを途中でやめなくて良いのが幸せ。
というわけで、今日もまた草取り三昧を楽しみたいと思います。