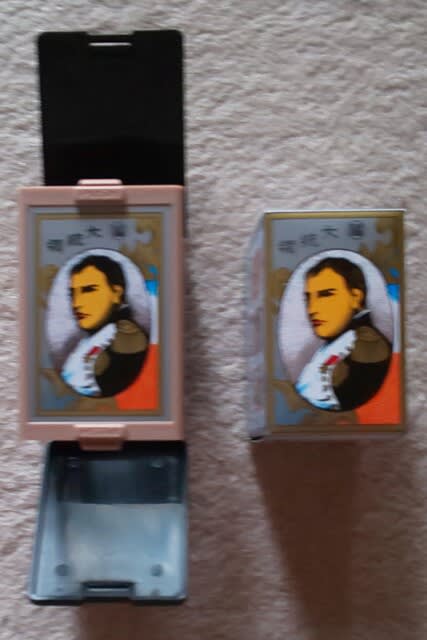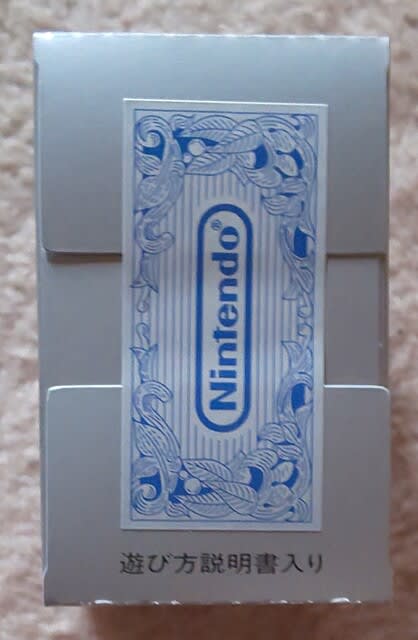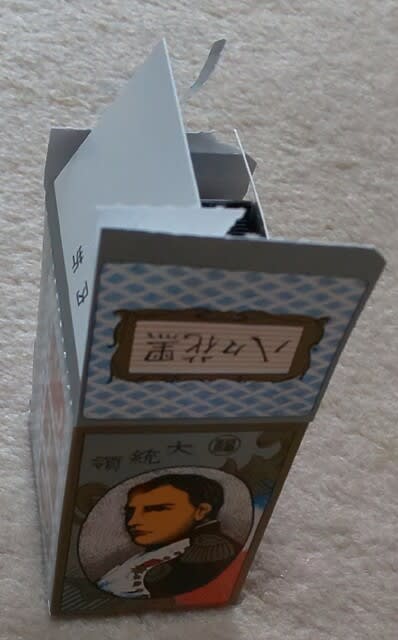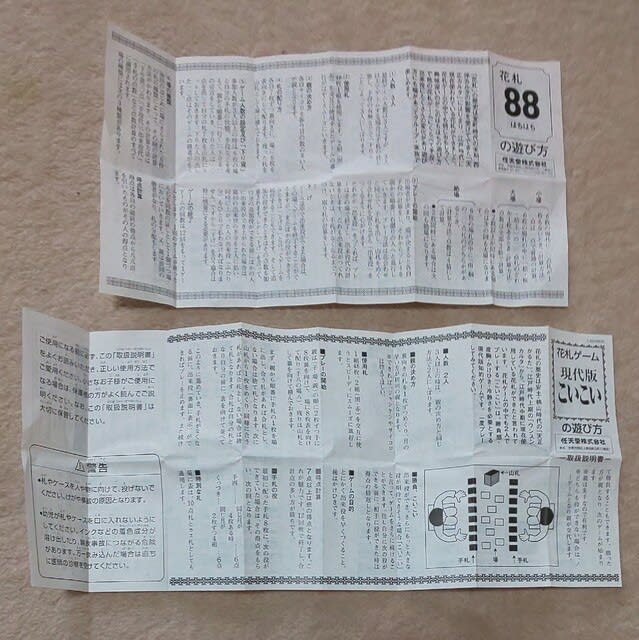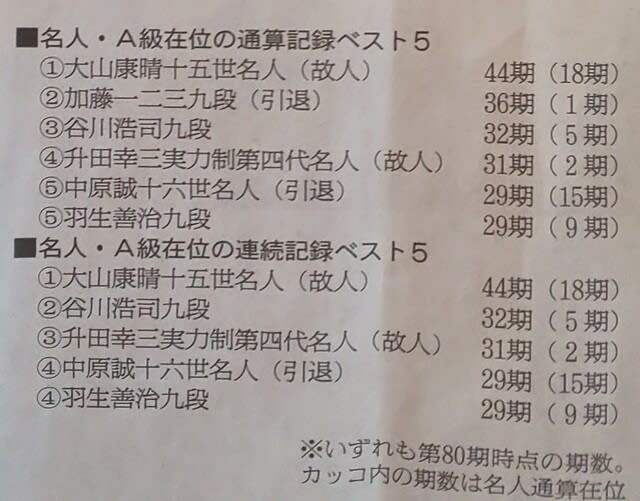今月、4月7日の日曜に、予定通り、千駄ヶ谷の将棋会館道場へ行ってきました。
令和2年3月1日の日曜以来、約4年振りの将棋道場通いとなります。これからは月2回、隔週で将棋道場通いを再開します。
自宅を午前11時過ぎに出て、まっすぐ千駄ヶ谷へ行けばいいものを、電車の中で急に心変わりし、ついでの買い物を先に済ませてしまおうと、西武新宿駅で下車し、楽器店でクラッシックギターの弦、ディスクユニオンでCD、世界堂でF50号の仮縁(組み立て式の棒縁)を買ってから向かいました。
着いたのは確か午後2時前後。千駄ヶ谷の将棋会館、昔のまんまですね。懐かしい。訪れるの、30数年振りじゃないのかなあ。
さて受付で初めてだと告げると(大昔に2、3度来たことはあるんですけどね)、どれぐらいの棋力か聞かれるわけでして、持っていった新宿将棋センターの棋力証(四段)を提示。
これを参考に、受付が対戦相手を決め、数局指し、ここでの私の棋力判定をしてもらいました。
5局指し、4勝1敗で参段の認定。これで正式に将棋会館道場では、私は参段で指します(ちゃんと参段の棋力証をもらいました)。
その後、参段で2局指し、計7局、5勝2敗の成績。夜6時30分に引き上げ、7時30分に帰宅。
対局内容を簡単に報告。
最初は棋力不明者としての対戦なので、全て振り駒で先後を決めます。
1局目(勝ち):対1級、先手番。私の四間飛車に、右四間飛車。私は腰掛け銀にせず。
2局目(勝ち):対初段、先手番。私の四間飛車(藤井システム)に、急戦。うまくお茶を濁す。
3局目(勝ち):対参段、先手番。相振り飛車(私の向かい飛車に、三間飛車)。飛車交換の攻め合いに。
4局目(負け):対四段、後手番。相振り飛車(私の三間飛車に、中飛車)。序盤で致命的なミス、取り返しつかず。
5局目(勝ち):対参段、後手番。相振り飛車(私の向かい飛車に、三間飛車)。相手は攻めが切れ、投了。
ここまで、5局指し、4勝1敗。参段に認定。
6局目(勝ち):対参段、後手番。私の四間飛車に、変則船囲い持久戦。序盤で優勢に。中盤で相手が投了。
7局目(負け):対弐段、後手番。私の四間飛車に、左美濃。中盤で致命的ミス。終盤追い上げるも足りず。
以上ですが、正直、あまり内容が良くないです。やっぱり手が読めてない。だから負けた2局みたいなことが起こる。あれでは挽回できません。お粗末。
今回は棋力判定をしてもらうため、新宿将棋センターの棋力証(四段)を提示した手前、不得手な居飛車を指し、あまり不様な結果になるというのはどうよ、ということで指し慣れた振り飛車で戦いました。
また棋力判定には数局指さないといけないそうなので、3局で帰るわけにもいかず、また比較的短時間で終わった対局も多く、余力もあったので、7局も指せました。
さて、この将棋会館道場の印象ですが、子供たちが多く、大人は少ないです。私だけだったんじゃないの? 50代なんて(子供の保護者を除いて)。
また、そのせいでしょう、嫌味な常連客は皆無で、雰囲気も穏やかで、ぎすぎすしてなくて好感が持てます。これには、ほっとしました(たちの悪い客にはうんざりです)。
これなら通いやすいかな。飲料の自販機もたくさんあるし、トイレもちゃんと掃除されてますし。それとちょっと贅沢なのが、対局で使う駒がプラスチックではなく、ちゃんとした彫り駒なこと。贅沢で、嬉しい気分。
ただ、子供たちが中心で、あまり私のようなおじさんは歓迎されないのかも(受付は内心そう思ってたりして)。その辺、どうなのかなあと。まあこれについてはしばらく通っていればわかることだと思いますが。
これで次回からは、いよいよ予定通り、相居飛車を狙って指します。そして3局指したら帰る方針ですが、今日みたいに疲れてないなら、多少対局数を増やしてもいいかなと思いました。
隔週通うので、今月はあと1回、21日に行ってきます。
帰るときに受付で聞いてみたんですが、やっぱり平日(月曜から金曜)は人が少ないみたいです。だから行くなら、土、日、祝日ですかね(私の場合は日曜になります)。
また夕方5時に大半の客が帰ってしまったところをみると、できるだけ早く、開店直後に行くのがいいのかも。その方がより対局相手が決まりやすいはず。
月2回で十分ですかね、将棋会館道場へは。淡々と通って、数局指して帰ってくる、そんな感じで。
4年振りに将棋を指しましたが、思っていたよりも深刻ですね、私のボケっぷり。楽観的に考えていたんですが、吹き飛びました、随分と甘かったなあと。
今後は継続して通いますので、いずれボケは治るでしょうが、今のところ事態は深刻なり。早期に何とかせねば。
付)結果論ですが、今回は振り飛車を指して良かったです。まずは復帰に当たり、自分の指し慣れた戦法の状態を知っておくのは大事なことでした。
注)突貫工事で習得した居飛車の定跡、次回行くまで2週間あるので、しっかり復習しておかねば。
蛇足)千駄ヶ谷駅から将棋会館へ向かう途中に、ファーストフード店やコンビニ、喫茶店があるので、食事には困らないとわかり、安心しました。
令和2年3月1日の日曜以来、約4年振りの将棋道場通いとなります。これからは月2回、隔週で将棋道場通いを再開します。
自宅を午前11時過ぎに出て、まっすぐ千駄ヶ谷へ行けばいいものを、電車の中で急に心変わりし、ついでの買い物を先に済ませてしまおうと、西武新宿駅で下車し、楽器店でクラッシックギターの弦、ディスクユニオンでCD、世界堂でF50号の仮縁(組み立て式の棒縁)を買ってから向かいました。
着いたのは確か午後2時前後。千駄ヶ谷の将棋会館、昔のまんまですね。懐かしい。訪れるの、30数年振りじゃないのかなあ。
さて受付で初めてだと告げると(大昔に2、3度来たことはあるんですけどね)、どれぐらいの棋力か聞かれるわけでして、持っていった新宿将棋センターの棋力証(四段)を提示。
これを参考に、受付が対戦相手を決め、数局指し、ここでの私の棋力判定をしてもらいました。
5局指し、4勝1敗で参段の認定。これで正式に将棋会館道場では、私は参段で指します(ちゃんと参段の棋力証をもらいました)。
その後、参段で2局指し、計7局、5勝2敗の成績。夜6時30分に引き上げ、7時30分に帰宅。
対局内容を簡単に報告。
最初は棋力不明者としての対戦なので、全て振り駒で先後を決めます。
1局目(勝ち):対1級、先手番。私の四間飛車に、右四間飛車。私は腰掛け銀にせず。
2局目(勝ち):対初段、先手番。私の四間飛車(藤井システム)に、急戦。うまくお茶を濁す。
3局目(勝ち):対参段、先手番。相振り飛車(私の向かい飛車に、三間飛車)。飛車交換の攻め合いに。
4局目(負け):対四段、後手番。相振り飛車(私の三間飛車に、中飛車)。序盤で致命的なミス、取り返しつかず。
5局目(勝ち):対参段、後手番。相振り飛車(私の向かい飛車に、三間飛車)。相手は攻めが切れ、投了。
ここまで、5局指し、4勝1敗。参段に認定。
6局目(勝ち):対参段、後手番。私の四間飛車に、変則船囲い持久戦。序盤で優勢に。中盤で相手が投了。
7局目(負け):対弐段、後手番。私の四間飛車に、左美濃。中盤で致命的ミス。終盤追い上げるも足りず。
以上ですが、正直、あまり内容が良くないです。やっぱり手が読めてない。だから負けた2局みたいなことが起こる。あれでは挽回できません。お粗末。
今回は棋力判定をしてもらうため、新宿将棋センターの棋力証(四段)を提示した手前、不得手な居飛車を指し、あまり不様な結果になるというのはどうよ、ということで指し慣れた振り飛車で戦いました。
また棋力判定には数局指さないといけないそうなので、3局で帰るわけにもいかず、また比較的短時間で終わった対局も多く、余力もあったので、7局も指せました。
さて、この将棋会館道場の印象ですが、子供たちが多く、大人は少ないです。私だけだったんじゃないの? 50代なんて(子供の保護者を除いて)。
また、そのせいでしょう、嫌味な常連客は皆無で、雰囲気も穏やかで、ぎすぎすしてなくて好感が持てます。これには、ほっとしました(たちの悪い客にはうんざりです)。
これなら通いやすいかな。飲料の自販機もたくさんあるし、トイレもちゃんと掃除されてますし。それとちょっと贅沢なのが、対局で使う駒がプラスチックではなく、ちゃんとした彫り駒なこと。贅沢で、嬉しい気分。
ただ、子供たちが中心で、あまり私のようなおじさんは歓迎されないのかも(受付は内心そう思ってたりして)。その辺、どうなのかなあと。まあこれについてはしばらく通っていればわかることだと思いますが。
これで次回からは、いよいよ予定通り、相居飛車を狙って指します。そして3局指したら帰る方針ですが、今日みたいに疲れてないなら、多少対局数を増やしてもいいかなと思いました。
隔週通うので、今月はあと1回、21日に行ってきます。
帰るときに受付で聞いてみたんですが、やっぱり平日(月曜から金曜)は人が少ないみたいです。だから行くなら、土、日、祝日ですかね(私の場合は日曜になります)。
また夕方5時に大半の客が帰ってしまったところをみると、できるだけ早く、開店直後に行くのがいいのかも。その方がより対局相手が決まりやすいはず。
月2回で十分ですかね、将棋会館道場へは。淡々と通って、数局指して帰ってくる、そんな感じで。
4年振りに将棋を指しましたが、思っていたよりも深刻ですね、私のボケっぷり。楽観的に考えていたんですが、吹き飛びました、随分と甘かったなあと。
今後は継続して通いますので、いずれボケは治るでしょうが、今のところ事態は深刻なり。早期に何とかせねば。
付)結果論ですが、今回は振り飛車を指して良かったです。まずは復帰に当たり、自分の指し慣れた戦法の状態を知っておくのは大事なことでした。
注)突貫工事で習得した居飛車の定跡、次回行くまで2週間あるので、しっかり復習しておかねば。
蛇足)千駄ヶ谷駅から将棋会館へ向かう途中に、ファーストフード店やコンビニ、喫茶店があるので、食事には困らないとわかり、安心しました。