今朝、版木を乗せて皺にならないようにしておいた摺り終えた版画を見てみると、皺になっていなかった。良かった。ただし版木からはみ出している部分は皺が若干寄っている(当たり前か)。とはいえ試し摺りならこの乾かし方でもいいと思った。
さて、そのはみ出している部分、余白と言えばいいか、を1.5センチほど残してあとは切り落とした。問題はどこへしまうか、つまりどこに保管するかだ。今回はA4サイズ(今後も当面はA4サイズ)で試し摺りの紙を使って3枚摺った。大きくはないので場所は取らない。そこでいつも描きあげた水彩画を保管しているB3のポートフォリオ(世界堂新宿本店で売っている)に入れることにした。これで安心。
ようやくこれで初めての木版画制作全行程を終えたことになる。あとは額装ぐらいか。額装は額装でまた記事にするとして(まだ額を買ってませんが)、いくつか感じたことを書いてみたい。
まず木版画用具置き場の確保が必要。これにはやっぱりカラーボックスがいいと思う。ただし棚板を好きな位置に移動できるもの(棚板が固定されていない、可動式のもの)で棚板は最低2枚は必要。棚板2枚で3段になるので、最上段は版木や版画紙の置き場にする、中段は彫刻刀や砥石、椿油、バレン、糊、ハコビ、刷毛、水彩絵具、絵皿など、必要な道具を入れる。最下段は、ビニール袋に入れた柔らかく清潔な布を置く。これは濡れた砥石や研いだ彫刻刀の水気を拭き取ったり、洗った絵皿やハコビ、刷毛などを拭くのに使う。
もちろん、どう使うかはその人次第だし、カラーボックスを使わなくたっていいが、あったら便利。しかも安価だ。使わない手はないと思う。私は今のところ、本棚として使っている背の高いカラーボックスの最上段を空け、そこに版木と版画紙を、別のガラスの引き戸つきの背の低いカラーボックスもどきに、版画道具とビニール袋に入れた布をしまっているが、いずれカラーボックスを買ってちゃんとしたいと考えている。
次に摺りあげた版画の保管だが、先に述べた通り、ポートフォリオに入れて保管するのがいいと思う。っていうか現実問題としてこれしか解決方法はないんじゃなかろうか。部屋がよっぽど広くてお金持ちなら、オフィス用のマップケースを買うとか、いくらでも方法はありますが。
最後にハコビは一度使ってみるのを推奨。ハコビじゃなくて筆でも一向に構わないのだが、ハコビの水を含ませたときの柔らかさは一度体験しておくのがいい。試しに1本買うだけだから高くつかないので、未体験者は是非。
最後にもうひとつ。初心者が制作する大きさについてですが、私はA4でしたが、A4でも大きいと思った。もっと小さくていいかもしれません。でもあんまり小さいと彫りづらいし、その辺どうなんだろうか。小さくして彫りづらいと嫌なので、私は当面A4にするんですが。案外B5ぐらいがいいかもしれません。
付)「美術書全般、美術番組」のカテゴリー記事で紹介した、「木版画の世界」は本当に役立つ本です。辞書代わりになります。私も制作の途中よく参考にしました。もちろん今後も役立ちます。初心者かどうかを問わず、木版画制作者の頼れる味方です。
それと木版画の次回作については、あれこれまだ思案中です。またその話は別に書きたいと思っています。とはいえいつまでも考えているわけにもいかないので、来週末には制作開始予定です。
さて、そのはみ出している部分、余白と言えばいいか、を1.5センチほど残してあとは切り落とした。問題はどこへしまうか、つまりどこに保管するかだ。今回はA4サイズ(今後も当面はA4サイズ)で試し摺りの紙を使って3枚摺った。大きくはないので場所は取らない。そこでいつも描きあげた水彩画を保管しているB3のポートフォリオ(世界堂新宿本店で売っている)に入れることにした。これで安心。
ようやくこれで初めての木版画制作全行程を終えたことになる。あとは額装ぐらいか。額装は額装でまた記事にするとして(まだ額を買ってませんが)、いくつか感じたことを書いてみたい。
まず木版画用具置き場の確保が必要。これにはやっぱりカラーボックスがいいと思う。ただし棚板を好きな位置に移動できるもの(棚板が固定されていない、可動式のもの)で棚板は最低2枚は必要。棚板2枚で3段になるので、最上段は版木や版画紙の置き場にする、中段は彫刻刀や砥石、椿油、バレン、糊、ハコビ、刷毛、水彩絵具、絵皿など、必要な道具を入れる。最下段は、ビニール袋に入れた柔らかく清潔な布を置く。これは濡れた砥石や研いだ彫刻刀の水気を拭き取ったり、洗った絵皿やハコビ、刷毛などを拭くのに使う。
もちろん、どう使うかはその人次第だし、カラーボックスを使わなくたっていいが、あったら便利。しかも安価だ。使わない手はないと思う。私は今のところ、本棚として使っている背の高いカラーボックスの最上段を空け、そこに版木と版画紙を、別のガラスの引き戸つきの背の低いカラーボックスもどきに、版画道具とビニール袋に入れた布をしまっているが、いずれカラーボックスを買ってちゃんとしたいと考えている。
次に摺りあげた版画の保管だが、先に述べた通り、ポートフォリオに入れて保管するのがいいと思う。っていうか現実問題としてこれしか解決方法はないんじゃなかろうか。部屋がよっぽど広くてお金持ちなら、オフィス用のマップケースを買うとか、いくらでも方法はありますが。
最後にハコビは一度使ってみるのを推奨。ハコビじゃなくて筆でも一向に構わないのだが、ハコビの水を含ませたときの柔らかさは一度体験しておくのがいい。試しに1本買うだけだから高くつかないので、未体験者は是非。
最後にもうひとつ。初心者が制作する大きさについてですが、私はA4でしたが、A4でも大きいと思った。もっと小さくていいかもしれません。でもあんまり小さいと彫りづらいし、その辺どうなんだろうか。小さくして彫りづらいと嫌なので、私は当面A4にするんですが。案外B5ぐらいがいいかもしれません。
付)「美術書全般、美術番組」のカテゴリー記事で紹介した、「木版画の世界」は本当に役立つ本です。辞書代わりになります。私も制作の途中よく参考にしました。もちろん今後も役立ちます。初心者かどうかを問わず、木版画制作者の頼れる味方です。
それと木版画の次回作については、あれこれまだ思案中です。またその話は別に書きたいと思っています。とはいえいつまでも考えているわけにもいかないので、来週末には制作開始予定です。











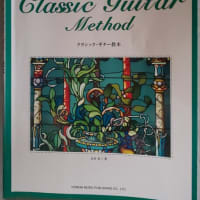





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます