
ハラスメントという言葉は、当初「セクシャルハラスメント(セクハラ)」で一般化した言葉だと思うが、その後「パワーハラスメント(パワハラ)」という言葉も出てきた。
今では、セクハラもパワハラも一般用語として、すっかり定着している。
それに関する訴訟も多く見受けられるようになり、セクハラやパワハラが社会問題のひとつとして広く世の中に認識されているのは、ご存知の通り。
やがてその後、続々と「ハラスメント」という言葉で色々な種類が出てくるようになった。
ドクターハラスメント(ドクハラ)。モラルハラスメント(モラハラ)。
そしてマタニティハラスメント(マタハラ)。他にもあるのでは。
このぶんでいくと、今後もどんどん新たなハラスメント言葉が出てきそうだ。
ちょっと種類が増えすぎてるんじゃないか・・と思うぐらい。
まあ、それだけ世の中には様々なハラスメントが横行しているということなのだろう。
この一連のハラスメントという概念に共通しているのは、それをやられた側がどう感じるか・・ということ。
受け取る側がそれをハラスメントと受け取ればハラスメントになる。
同じことをやられても、やられる側がそれをハラスメントと感じなければ、ハラスメントにはならない。
このへんが、曖昧であり、事態をややこしくしている気はする。
いっそ、ハラスメントの定義を決めたほうがよくないだろうか。
いや、ネット上で調べてみると、それなりに定義はあるようではある。
だが、その定義は、実際に自分が当事者になってみないと分からないものが多いかもしれない。
ハラスメントのやっかいなところは、加害者が自分が加害者であるという自覚がないことだとはよく言われる。
自分が相手に対してやっている行為や、言っている言葉が、ハラスメントであるという自覚がない・・ということ。
だから時には無意識のうちに繰り返されたりするのだろうし、被害者がおとなしくしていると、加害者の言動はエスカレートしていったりする。
その結果、訴訟になったりして、それが公になることで、その様に世間の人が驚いたりすることもある。
やはり、ハラスメントを受ける側がどう感じるか、どう思うか次第で、それがハラスメントになったり、ならなかったりする・・という曖昧な基準がやっかいなのではないだろうか。
受け取る側の感じ方次第・・ということだと、ハラスメントに該当するものを受ける側と、ハラスメントに該当することをする側の関係が良好な時は、それはハラスメントにならなくても、いったん両者の関係が悪くなってしまうと、それまでハラスメントにならなかった行為を、受け取る側がハラスメントと受け取れば、一転ハラスメントになってしまうことになる。たとえ同じ行為であっても・・だ。
人間同士の関係は、たとえ良好な関係であっても、それが生涯続くとは限らなかったりする。
関係が良好だった人たちが、何かのきっかけで険悪になってしまうこともある。
また、部下に自分は嫌われていないとか、好意をもたれていると思い込んでいる上司が、その部下に対して、「自分は嫌われてはいないはずだから、こういうことを言ったり、やったりしても大丈夫だろう」と思いこんで言ったり、行ったりした行為が、実はその部下はその上司に対して良い感情を持っていなかったりすると、その上司がその部下に対して言ったことや行った行為は、ハラスメントということになってしまう。
そんなこともあるので、ハラスメントの定義を、「受け取る側の感じ方次第」ではなく、たとえ良好な人間関係であっても、それをやるとハラスメントにあたる・・というふうに、定義をはっきりさせてしまったほうが、分かりやすい気がする。
曖昧なままでは、中々減らないと思う。
立場が弱いと、会社をやめる覚悟がない場合は、被害者は中々上司にむかってハラスメント指摘はしにくい場合もあるだろうし。
たとえ会社をやめないまでも、その後の会社内で仕事がやりづらくなる場合もあるだろうし。
なにより、なにをやったらハラスメントになるか、何を言ったらハラスメントになるか、曖昧なままだと、中々減らない気はする。
てっとり早いのは、ハラスメントの定義を法化することだが・・。
法化すると、職場の雰囲気や人間関係に閉塞感が出るという意見もありそうだが、やっかいなのはエスカレートであることを考えると、エスカレートを防ぐためには、仕方ない気もする。
ハラスメントのエスカレートは、被害者を自殺に追い込んだり、肉体的虐待につながったりもする。
加害者は更に悪質化する可能性もある。
現に、パワハラのエスカレートぶりが表面化し、それがニュースで報道されるケースはちょくちょくある。
それらの事件の報道を見たり聞いたりしてると、そのパワハラのエスカレートぶり、ちょっと信じられないぐらいの内容もあったりする。
一番やっかいなのは、そのエスカレート・・なのだ。
それと、被害者の中に、嫌悪感やストレスがどんどん積もっていくことだ・・。
よく、子供同士のいじめで、それがエスカレートして、被害者の子供を自殺に追い込むことがあるが、大人のやってるハラスメントは、子供のいじめと変わらない・・いや、それどころか子供同士のいじめよりたちが悪いことがある。
だとすると、ハラスメントを続行させてる大人が、子供のいじめ問題を批判してもなあ、、、。
子供のいじめを批判する前に、自身のハラスメントをまずやめないと、何を言っても説得力は・・ない気もする。それが、一見正論っぽい言葉であればあるほど。
パワハラの場合、加害者は被害者よりも仕事上の身分や立場が上であり、それを利用しておこなういやがらせ。加害者の身分の方が上だから、被害者はうかつに逆らえない。まあ、それを見越して加害者はいやがらせをするから、相手がさからえないことをいいことに、エスカレートしていってしまう。
「いじめ」は、同等の立場で行ういやがらせ。それでも、被害者がおとなしくしていると、エスカレートしていってしまう。
「パワハラ」と「いじめ」には、そのへんの違いはあるだろう。
だが、「いやがらせ」という意味では共通していると思う。
「いじめ」と「ハラスメント」を別々の種類のものと考えるのなら、いっそ、子供のいじめを「チャイルドハラスメント」などの言葉で、ハラスメントの1種類として認識してしまえば、いじめとハラスメントが同罪のことであることを実感できるかもしれない。
同罪という意味では、 例えばそれは、殺人犯が別の殺人犯に向かって「殺人は、けしからん。」と説教してるようなもの、、、と言われても仕方ないのでは。
そうなると、会社でパワーハラスメントなどを行っている人は、子供のいじめ問題に対して、うかつなことは言えないのではないか。
なぜなら、まず自分自身が会社で「いじめ」をやっているわけだから。
そんなことを考えると、日本は・・・子供も大人もハラスメントをやっている・・ということになる・・。
根は深い・・・ということなのだろうか。










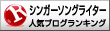

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます