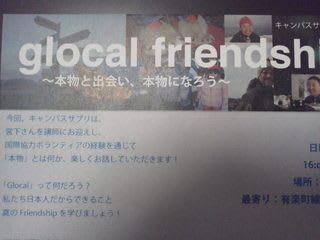観てきました(^o^)
ずっと観たかった印象派の作品の数々。
特に気になってたあの作品も!
エドゥアール・マネの「笛を吹く少年」1866年、第二帝政期、ルイナポレオンか君臨してた頃描かれた絵です。
友人であった軍の高官が連れて来た、近衛軍鼓笛隊員ですが、一説によると顔の部分だけ、マネの息子のレオンであると言われ、大きな瞳に、あどけなさを残す表情が印象的。
この作品はジャポニスムの影響が見られるということで有名。
遠近感なく、人物の動きを最小限にとどめ、コントラストの強い色を平面的に用いている様は浮世絵の技法だとも言われてるそう。
そばで見ると、迫力ある一枚です。
しばらく進むと、なんと、少年が吹いてる楽器を再現したものがあるではないですか!!!
三響フルート製作所さんによる、8孔のもので、一つだけグラナディラ製、洋銀のキーでつくられてます^^
この笛はファイフという楽器(横笛)で、軍隊の鼓笛隊で使われたものだそう。
行進の統制や、点呼、戦術で兵士に合図を送る役割を担っていたとか。
音色は、フルートよりはかたい、きれいな音というよりは通る音だったようです。
ピッコロみたいなものを想像してみた^^
絵のモデルになったのは、フランス皇帝の近衛隊直属の少年兵でしょうか。
顔の中身は、マネの息子だともいわれています。
ところで、ファイフという楽器自体は、スイスの傭兵によってもたらされ、1515年に正式に導入されるようになったのだそう。
国王つきの音楽隊、王のファイフ奏者ー「Fifle du Roi 」という役職ができるほど、重要なミッションがあったのですね。
さまざまな式典や祝祭でも演奏されてきた楽器で、19世紀半ばにはパリ高等音楽院にも軍楽隊養成を専門とする教育機関も整備されるようになったらしい。
宮廷と音楽、切り離せない関係にありますね。
美術館、時空を越えた歴史の中に入り込める不思議な空間です。