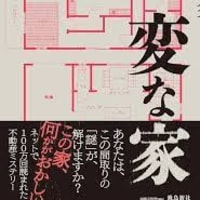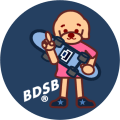今年はNHK大河ドラマ『べらぼう』で江戸時代が大きな盛り上がりを見せているが、江戸時代というのは何とも魔訶不思議で面白い時代である。260年も平和な時代が続いた江戸時代は、戦う必要がなくなったことで文化・文明が華やかに開花した時代だったわけだが、当時江戸の人口が100万人/八百八町という、世界一の巨大都市で、我々の先祖である当時の江戸の人々が送っていたライフスタイルは、知れば知るほどかなり面白いのだ。

僕は日本史で言えば、元々戦国時代と安土桃山時代が好きだったのだが、江戸も昔から興味のある時代だった。如何に江戸が世界一の都市に成長していったのか、そして当時庶民がどのようなライフスタイルを送っていたのかはとても興味深いテーマであった。そして、2016年に『江戸はスゴイ』という新書本を購入して読んで、その興味は益々深まったのだが、この本は堀口茉純という女優もやっているYou Tuberが出版した本で、かなり刺激的で面白い本であった。

そして今年の大河ドラマにも合わせて、堀口茉純が最新刊、『大江戸24時』という魅力的な本を出版したので、思わず本屋で見つけて購入した。タイトル通り、江戸の庶民の生活を24時間の中で時系列的に取り上げながら、江戸の人々がどんな暮らしをしていたのかを様々な風俗エピソードで解説してくれる本である。まさに蔦屋重三郎が活躍した時代に、彼のプロデュースで活躍した多くの浮世絵師たちや、当時庶民の生活やエンタメがどうだったのか、如何に江戸の文化が花開いたかを見事に捉えたエンタメ本となっている。大河ドラマと合わせてみると、江戸時代の理解が更に深まるので、おススメ・イチオシの本である。それにしても江戸をテーマに取り上げた堀口茉純の本は読みやすいし、内容もマニアックで面白い。

そして今日、『べらぼう』の第3回放送を観たが、蔦屋重三郎が如何に『吉原細見』や『一目千本』を企画・プロデュースし、ハードルなどを超えながら浮世絵師たちを世に送り出して成功して行ったかがとてもダイナミックに描かれていて、まだ第3回ながら、とても気持ちのいい放送回であった。まさに現代の広告・メディア手法が江戸時代から既に始まっていたのだという思いと、人口100万人というマスメディアを相手に、平賀源内や浮世絵師たちの“キラーコンテンツ”を駆使して、時流を見ながら如何に人々にリーチしていったのかが見事に描かれている点で、今までにない躍動感のある、なかなか斬新な大河ドラマになっているのではないかと感じているので、これからの展開も楽しみだ。


関連することでもう一つ、1月9日にBS朝日で放送された『あなたの知らない京都旅』で、中村雅俊が旅人(ナビゲーター)を務めた放送回だったが、その内容が面白かった。江戸時代中期に、江戸では版元の蔦屋重三郎が歌麿、写楽、北斎などの天才絵師をプロデュース。一方で、その頃京都では円山応挙、伊藤若冲などの絵師が西で活躍していたことを中心に取り上げたが、江戸の写楽・北斎などは版画による大衆向け大量出版型で、まさにシルクスクリーンで多くのプリントを制作したポップアーティストスタイルの先駆者でもあったと言えるが、一方で応挙や若冲は“1点もの”とされる日本画をセルフプロデュースしながら制作したことから、当時の江戸と京都では、絵師の仕事スタイルが全く異なっていたというのが実に興味深かった。


僕は円山応挙も好きで、特に応挙の描くワンちゃんの絵が何ともキュートで好きだ(以前ブログでも、応挙の絵が多く載った、こちらの『子犬の絵画史』を取り上げた)。幕府に検閲・管理されながらも、大量消費型・マスメディア社会向けに大きく発展していった当時の江戸に対して、西の京都は、江戸よりもアーティストたちが自由な環境で絵を描くことが出来たのだろう。この違い・対比というのは今まであまり認識・意識したことが無かったので、とても面白い気付きとなった。

大河ドラマによって、今年は様々な形でまた江戸時代がクローズアップされるだろうが、改めて江戸時代を研究してみると、日本の歴史上、衣食住などのライフスタイルが実に興味深い発展を遂げた時代であったことがわかるので面白い。またエンタメの世界も、幕府に管理された独特な風俗世界の吉原、日本古来のスポーツである相撲、アイドルや“推し“の原点とも言える歌舞伎、ポップアートカルチャーの原点とも言える浮世絵など、100万人のエンタメ欲を満たすべく急速に進化し花開いたたわけだが、現代日本のルーツとも言える華やかで楽しい世界が広がっていた江戸時代は、まさに最高の”スーパーシティー“だったことが良くわかる。今後の東京、そして日本を占う意味でも、今年は江戸時代をじっくり楽しみたいと思う。