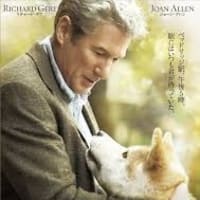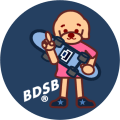遅ればせながら、ようやく映画『PERFECT DAYS』を観賞した。日本では昨年12月から公開されたヴィム・ヴェンダース監督作品で、カンヌ映画祭で主演男優賞(役所広司)を受賞したことでも大きな話題となった作品である。ずっと観たいと思っていたが、劇場公開のタイミングで思わず見逃してしまった。しかし、今月ようやくWOWOWでの放送が始まり、やっとじっくり観賞することが叶ったのだ。

映画を観終えた率直な感想として、期待していた以上に心に響いた、素晴らしい傑作であった。何とも素朴な映画だが、“幸せとは何か?”を問いかける作品で、大都会東京の『光と影』、そして『幸せの定義』を考えさせられる何とも言えない深い“余白”と“余韻”のある映画であり、個人的には心に響く映画であった。

映画は、渋谷区内17か所の公共トイレを刷新する日本財団のプロジェクト、『THE TOKYO TOILET』をベースに長編映画化した異色作品。東京のトイレを舞台に、トイレ清掃員の日常を追った、まるでドキュメンタリーのような作品で、相当地味な映画である。しかし、小津安二郎を尊敬するヴィム・ヴェンダース監督らしく、この映画で描いた世界観は、どこか『東京物語』にも似た、日本の良さをフィーチャーしながら、淡々とした平凡な日常のルーティンと、繊細な心の機微を見事描くことに成功した作品だ。この映画の主人公、平山の日常におけるルーティンは大変興味深いので、ポイントを下記の通り纏めてみた。


1) 朝のルーティン
役所広司演じる主人公の平山は、スカイツリー近くの下町にあるボロアパートに住むトイレ清掃員。平日は毎朝決まって早朝に起床し、車で公共トイレを周り、ひたすら清掃していく単調な日々を送っている。この日常のルーティン描写が実に見事であった。毎朝近くの神社で箒を履く音で目を覚まし、軽く布団を畳んで歯を磨く。植木に水をやり、制服に着替え、玄関に置いてある鍵などを取って(ここに腕時計もあるが、平日仕事の時はしていかない)家を出て、空を嬉しそうに見上げる。そこからアパートの外にある古びた自販機でBOSSの缶コーヒー(カフェオレ)を買って仕事用の軽のミニバンに乗り込み、その日の気分でカセットテープをかけながら仕事場のトイレへと向かう。この一連のルーティンでわかるのが、① 何とも時間に正確で、規則正しい、几帳面な生活を送っているということ、② 植木はどうやら趣味であるということ、③ 朝食はこの缶コーヒー1個だけで済ましていること、④ カセットテープを通して、音楽の趣味が70年代の洋楽であること、そして④ このルーティンをどこか楽しんでいるということだ。


2) 仕事のルーティン
公共トイレに到着すると、実に無駄なく、手際よくトイレ清掃をこなしていく。トイレの裏まで隅々をキレイに清掃していくが、まさに外国人が驚く日本の丁寧な清掃サービスがここに凝縮されている。ここから複数のトイレをまわって同じ単調な作業を繰り返していく。仕事でのルーティンも朝家を出る時のルーティンと同じように淡々と進んでいくが、トイレの場合には時に誰かがトイレを使用する為に立ち寄るので、想定外に時間を取られたり、外で待つようなことも起こるし、子供が迷子になってトイレにいたところを、母のもとに返してあげたりなど、ルーティンを変える小さな出来事が起こる。またここでの主役は、斬新なデザインのトイレたち。『THE TOKYO TOILET』プロジェクトで手掛けられたトイレだけあって、どのトイレもオシャレなデザイン。隈研吾が手掛けたものもあり、日本のトイレ文化と清掃サービス、そしてトイレの斬新なデザイン性が映画を通して海外にも伝えられる点はとても嬉しいし、この映画の着眼点の素晴らしさにも感心してしまう。






3) 昼のルーティン
お昼はコンビニでサンドウィッチと牛乳を買って、いつも訪れる神社のベンチで食べる。ここでいつもフィルムカメラを取り出し、木々の“木漏れ日”を毎日撮影するのが日課だ。ここで、カメラで写真を撮るのも趣味であることがわかり、また神社で時々小さな木の苗などを見つけては新聞紙で作った小さな器に入れて持ち帰る姿も描いているが、やっぱり植木も趣味であり、小さな命を大切にしていることを確認出来る。そして、ここでこの”木漏れ日“がとても印象的に登場する。毎日同じような天気でも、木漏れ日の差し方が微妙に違い、日の高さによっては異なる表情を見せる筈だが、毎日同じような時間にお昼を食べているであろう正確なルーティンを象徴している部分でもあり、またその瞬間を毎日カメラでとらえることに喜びを感じている様子が垣間見れる。また後述するが、この木漏れ日は大都会東京の光と影のメタフォアでもあると感じた。


4) 夜のルーティン
仕事が終わると、ミニバンでアパートに戻り、自転車に乗り換えて下町の古い銭湯に行き、お風呂に入る。アパートにはお風呂は無いというわけだ。いつも常連さんが通う銭湯で、淡々と体を洗うシーンが登場するが、かなり痩せている体も印象に残る。そしてお風呂から出ると、決まって訪れるのが浅草駅地下のディープな居酒屋で、ジャイアンツの野球中継を見ながらハイボール1杯とツマミ(お通し?)を楽しむ。家にはテレビが無いので、この時間も外界との接点という意味ではかなり貴重ではないかと思う。恐らく金銭的に余裕が無いので、贅沢は出来ないのだろう。しかし、ここで食べる僅かな料理が夕食だと思うと何とも質素であり、お風呂屋で確認出来る平山の痩せた体も頷ける。そして、夜は寝る前に少しだけ本を読みながら早めに就寝するのだが、『木』という名の本を読んだりしており、植木が余程好きなのがここでも確認出来る。




5) 週末のルーティン
週末は果たして何をするのだろうと思って見ていたが、週末も比較的早く起き、平日と違って週末だけは腕時計を付けて、自転車でコインランドリーに向かい、清掃用の制服や、平日の服などを纏めて洗う。しかし、見た感じ洗濯物はそう多くない。服も制服以外は大して必要ないのである。洗濯を待つ間、毎週必ずカメラ屋さんに立ち寄り、撮った写真のフィルムを現像に出し、前の週末に出していた写真を引き取る。家に帰ると、撮った写真をチェックし、気に入ったものは整理して、年毎に整理されている缶ケースに収納していく。そして、いらないものはその場で破いて捨てる。これも毎週末必ず行うルーティンである。しかし、写真が趣味とはいえ、木漏れ日の写真ばっかり撮って、集めて何か面白いのだろうと思いながら、この時は見ていた。その後いつも立ち寄る古本屋で100円の文庫本を買う。夕方は、いつも決まってとあるスナックを訪れる。このスナックのママを演じているのが石川さゆり。平日はディープな居酒屋で安く済ませ、週末はこのスナックでちょっと奮発してハイボールとポテサラを食べるというのが、平山のささやかな贅沢なのであろう。そして、このママのことを気に入っており、週末にママの顔を見るのがささやかな楽しみと日常へのモチベーションになっていることも伝わってくる。



上記の通り、平山という人間の一週間には幾つかの正確なルーティンが存在するのだが、総じて何とも地味で質素な生活である。テレビもなく、スマホもなく(ガラケーを使用)、パソコンもなく、デジタルからは程遠いライフスタイルを送っている (Spotifyをどっかのお店かと勘違いしてしまうくだりもあって、アナログ人間であることがより強調される)。しかし、彼には全く悲壮感がなく、むしろこの規則正しいシンプルな生活パターンと、アナログで素朴な生活環境を気に入っているようであり、その中で、BOSSの缶コーヒー、カセットテープから流れる音楽、木漏れ日の写真、スナックのママ、植木、100円の文庫本などによってささやかなことに日々喜びを感じている。お金に余裕はなく決して裕福ではなさそうだが、これはこれで幸せな日々なのかも、と思ってしまうような日常描写が淡々と描かれていて実に面白い。そして平山のアパートは確かに“ボロい“アパートなのだが、部屋の中はきちんと整理整頓されており、むしろ禅にも通じるミニマリズム的で美しい小宇宙として存在しているのだ。今や文明が進化して便利になり、何不自由なくデジタル社会の中で生活している我々だが、改めてどこか懐かしい人間らしいシンプルな営み、昔ながらの素朴な生活の尊さと美しさみたいなものを再認識してしまった。


映画の中で、ルーティンに全く変化が無いかと言われればそうでもない。このルーティンな日常を“邪魔”する人間が少しずつ登場する。トイレ清掃の仕事で同じシフトを手伝うタカシ(榎本時生)や、彼が口説こうとしているガールズバーのアヤ (アオイヤマダ)などが平山の一日に関わってちょっとした気持ちの変化をもたらす。また、平山の姪っ子(妹の娘)が家出して平山のアパートに転がり込んできたりするが、ここでも通常の生活ルーティンが少しだけ変化していく様子がまた面白い。そして、それまで1人でのルーティンだったので殆ど会話が無いシーンが続いていたが、ようやく他人との関わりの中で、僅かではあるが、平山の声を初めて聞くことになる。寡黙な男なのであって、しゃべれないわけでは無かったのだ。



ここで秀逸なのは、この姪っ子の登場により、それまで“謎のトイレ掃除おじさん“だった平山に関する情報量もさり気なく増えていく点にある。姪っ子との会話から、今では平山は妹との関わりが殆どなく、“おじさんは住む世界が違う”ということを妹が姪っ子に伝えていることも知る。しかし、姪っ子本人は、今の何不自由ない裕福な生活にどこか閉塞感みたいなものを感じているのかもしれず、平山の質素で地味な生活には逆に自由を感じ、羨ましく映る点も見逃せないポイント。そして“今“という時間を大切であることを知る。姪っ子はかなり裕福な暮らしをしていても、それが必ずしも幸せということではないのかもしれないし、幸せの定義とは気の持ち様、人によって違うのだということもメッセージとして伝わってくる。



映画の中では詳細があえて語られないが、妹(麻生祐未)が娘を迎えにドライバー付きで黒塗りのハイヤーが平山のボロアパートまで迎えにくるシーンがある。ここでわかることとして、やはり姪っ子はとても裕福な環境で生活を送っているということだ。そして、僕も大好きな鎌倉のお菓子“クルミっ子”が妹から平山にお土産として渡されるが、これによって鎌倉のいいとこの家なのだろうことが推測される。また、クルミっ子を平山に渡しながら、“これ好きだったでしょ?”と妹が言う。そして平山は泣きながら妹を抱きしめるのだが、この短いやり取りに過去あったであろう出来事が凝縮されている。平山も恐らく昔は妹と同じような裕福な世界に住んでいたことも示唆されているわけで、どのような出来事があって今のトイレ清掃員の生活をするようになったのかわからないが、この点は見事“余白”を残して描かれている。

普通、トイレ清掃員と言われれば“落ちぶれた”生活として捉えられて、勝手に同情してしまうかもしれない。平山より裕福な生活を送る人の方が圧倒的に多い華やかな大都会東京という環境の中で、平山の一見侘しい生活との大きなコントラストで表現されている。ここでも本当の幸せとは何か?ということを問いかけられているような気がするのだ。


映画の後半に、三浦正和演じるスナックのママの元夫が登場する。これまたどこか裕福な男のように見えるが、実はガンを患っていて、どうやら先はあまり長く無さそうだ。そんな裕福でも人生を終えようとしている男と、裕福ではないが、毎日ささやかな幸せを感じながら淡々と生きる平山の間でも大きなコントラストが表現される。この2人の人生が僅かに交叉する中で、やっぱり“幸せとは何か?”を問いかけずにはいられないのである。

前述した“木漏れ日”がこの映画では大きな象徴として描かれている。映画の最後に日本語の“Komorebi”の定義がスクリーンに示されるが、確かにこの木漏れ日というニュアンスはあまり英語では表現しにくいものかもしれない。幸せの定義、そして大都会東京での”光と影“は、まさに写真が捉えた”木漏れ日“でと同じであり、この木漏れ日を敏感に感じることが出来る余裕のある人、豊かな感情を持っている平山は幸せな人間なのかもしれず、ここにも幸せの一つの定義が示されているように思えるのだ。そして、最後は首都高を車で走らせながら涙する平山のシーンで映画は終わりを迎えるが、これは悲しい涙ばかりではなく、幸せの涙なのかもしれない。そして幸せとは何か?を考えながら、この映画のタイトルである『PERFECT DAYS(完璧な日々)』の意味についても考えさせられるのであった。


『PERFECT DAYS』は決して派手さは無いし、何かドラマチックな出来事が起きる映画でもない。しかし、この映画は平山という人間を通して我々がどこかに忘れてきた素朴な幸せを思い出させてくれる作品であり、幸せとは何かを考えさせられる作品で、とても人間愛に満ち溢れた傑作であったが、何度も観賞したくなるような映画であった。