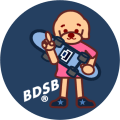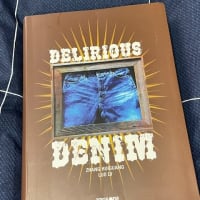先日書店で可愛い本を見つけて、思わず衝動買いしてしまった。
その本は、『子犬の絵画史~楽しい日本美術』というタイトル。金子信久という江戸時代絵画史を専門に研究している方が編集した本であった。金子さんは、慶応義塾大学文学部出身なので僕の先輩にあたるが、以前『ねこと國芳』という本を購入したことがあったのを思い出した。江戸時代絵画の中に登場する動物などに関心が高いようである。



動物の中でも犬が特に好きな僕だが、時々、“江戸時代の犬の暮らしや、人間との関係はどうだったんだろう”と考えてしまうことがある。もしも、きなこが江戸時代に生きていたとしたら、どんな生活を送ることになるのだろう・・と。そんなこともあって、江戸時代に描かれた犬たちに焦点を当てたこの本を手にとった時に、思わずそこに遠い江戸時代を生きた多くの犬たちに触れたような不思議な気持ちになり、何だか心が暖かくなった。


この本は、江戸時代の有名な絵師、円山応挙が描いた犬を中心に取り上げている。それも、殆どが可愛い子犬たちだ。そこにはワンワンうるさく吠える野犬の姿でもなく、今にも人に危害を加えそうな凶暴な野犬でもない。とにかく可愛くて癒される子犬たちである。



時には雪の中で、他の子犬たちとじゃれて遊んでいるが、とてもリアルに描かれているものの、その目や口元はどこか擬人化されているし、コロコロと丸みを帯びているその愛くるしい姿は、時代を超越して今にその可愛らしさを伝えている。これは想像から描いたものではなく、写実によるものだと言われている為、実際に応挙が描いた際、子犬たちを前に筆をとったのである。つまり、江戸時代にも当然ながら“可愛い子犬たち”が確実に存在していたし、人間の生活にも近い存在であったことも伺い知ることが出来る。



江戸時代の犬たちは、今のペットブームのように、家の中で溺愛されながら飼われてはいなかったかもしれないが、江戸の人々の癒し的な存在、そして人間に一番近い存在として共存していたのであろう。そして、絵を見ていると、そこには確実に幸せな余生を過ごしたであろう江戸のワンちゃんたちもたくさんいたのではないかと思わせる風景があった。


絵画的な素晴らしい理由として、恐らくモデルの子犬たちが実際に可愛いかったもあるだろうが、絵を眺めていると、応挙による絵師としてのテクニックに加え、子犬たちへの応挙の優しい眼差しが絵に反映されていることが見る者に伝わってくるところが最大の魅力であるように感じた。応挙は絵師の中でも、今でいう“ゆるキャラ”デザイナーの先駆者でもあったと言えるだろう。その意味でも大変参考になった。


今回、また金子信久氏の本に触れ、円山応挙の描いた可愛い子犬たちを初めてちゃんと見ることが出来て、大いに気持ちが癒されたのと同時に、またきなこをベースにしたイラストへの創作意欲も湧いてきたので、今回この本を手にとったのは正解であったし、とても良いインスピレーションとなった。心が求めていたものに誘導され、僕の方からこの本に吸い寄せられたのかもしれない。