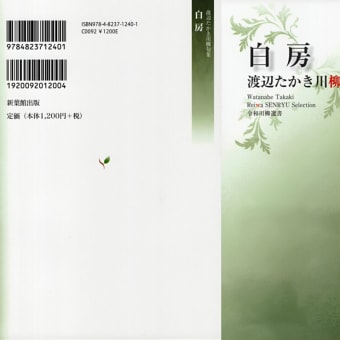□本日落語一席。
◆三遊亭歌武蔵「茶金」(TBSチャンネル『落語研究会』)。
東京三宅坂国立劇場小劇場、令和3(2021)年4月26日(第634回「TBS落語研究会」)。
歌武蔵が「落語研究会」で「茶金」をかけるのは、これが二度めである。同じ落語会で同じ演者が同じネタを出すのは皆無でないものの、やはりめずらしい。ちなみに、以前は、平成21(2009)年12月24日(第498回「TBS落語研究会」)である。十二年前だ。かなり間隔があいているので、抵抗感はきわめて少ないけれど、どうしてかな?という疑問はちょっとある。京須偕充のリクエストだったのだろうか。
自分はその当時の高座ついて、「京人物の言葉をリアルに演じようとしたために、ところどころかんでしまうところがあった……やはり不自然……江戸の油屋の言葉にまでも、妙に影響して、時折台詞まわしに失敗していた」とか、「京言葉と大阪弁とのちがいがわかっていないと思われ……京人物に大阪弁の『~でっせ』などとも言わせていた」というような感想を記していた。
そして、結論として、東京の落語家が「茶金」を演る場合は、五代目古今亭志ん生のように、なまじ上手く関西弁をあやつろうなどとせずに、むしろ適当に演っておいたほうが無難なのかもしれないと記した。
あれから十二年。今日聞いた歌武蔵の「茶金」は、十二年前よりも進歩していたようだった。やはり歌武蔵は(関西弁を)適当に演ることをよしとしなかったということなのだろう。今回は「~でっせ」も出ていなかったように思う。たぶん。
完璧とまでは言わないが、かなり自然と聞けるくらいになっていた。唯一、ちょっとだけ地語りのなかに関西弁がまじってしまうところがあったのは、ケアレスミスといったところか。
油屋が茶店の親父に渡す金は三両だが、それに加えて、五両分の油と油道具も置いてくる。なので、油屋は茶店の親父から八両で茶碗を買ったことになり、茶金も油屋に八両を渡すことになっている。ちなみに、買い取るのでなく、あるとき払いの催促なしで貸すということにしていた。上方落語「はてなの茶碗」では、茶金が買い取ると言うも、油屋のほうから借りると申し出る型である。
また、茶碗の見込み額と実際に売れた額は、六百両(これは茶金が茶店で六回首をひねったから)となっていたが、上方落語「はてなの茶碗」では千両である。
上記のような相違は、東京と上方で常態化してあるものっだろうか。たとえば、両者には和歌についての相違もあるが、これは明らかに東京と上方で常態化している相違である。
今日気がついた子細な相違はまた今後の宿題にしておこう。ただ、東京の落語家では、これをさまざまな人がかけるという事情にないのだろうか。主として聞くのは、この歌武蔵以外だと、十一代目金原亭馬生と四代目三遊亭金馬である。他に一回だけだが、春風亭正朝でも聞いたことがある程度。
◆三遊亭歌武蔵「茶金」(TBSチャンネル『落語研究会』)。
東京三宅坂国立劇場小劇場、令和3(2021)年4月26日(第634回「TBS落語研究会」)。
歌武蔵が「落語研究会」で「茶金」をかけるのは、これが二度めである。同じ落語会で同じ演者が同じネタを出すのは皆無でないものの、やはりめずらしい。ちなみに、以前は、平成21(2009)年12月24日(第498回「TBS落語研究会」)である。十二年前だ。かなり間隔があいているので、抵抗感はきわめて少ないけれど、どうしてかな?という疑問はちょっとある。京須偕充のリクエストだったのだろうか。
自分はその当時の高座ついて、「京人物の言葉をリアルに演じようとしたために、ところどころかんでしまうところがあった……やはり不自然……江戸の油屋の言葉にまでも、妙に影響して、時折台詞まわしに失敗していた」とか、「京言葉と大阪弁とのちがいがわかっていないと思われ……京人物に大阪弁の『~でっせ』などとも言わせていた」というような感想を記していた。
そして、結論として、東京の落語家が「茶金」を演る場合は、五代目古今亭志ん生のように、なまじ上手く関西弁をあやつろうなどとせずに、むしろ適当に演っておいたほうが無難なのかもしれないと記した。
あれから十二年。今日聞いた歌武蔵の「茶金」は、十二年前よりも進歩していたようだった。やはり歌武蔵は(関西弁を)適当に演ることをよしとしなかったということなのだろう。今回は「~でっせ」も出ていなかったように思う。たぶん。
完璧とまでは言わないが、かなり自然と聞けるくらいになっていた。唯一、ちょっとだけ地語りのなかに関西弁がまじってしまうところがあったのは、ケアレスミスといったところか。
油屋が茶店の親父に渡す金は三両だが、それに加えて、五両分の油と油道具も置いてくる。なので、油屋は茶店の親父から八両で茶碗を買ったことになり、茶金も油屋に八両を渡すことになっている。ちなみに、買い取るのでなく、あるとき払いの催促なしで貸すということにしていた。上方落語「はてなの茶碗」では、茶金が買い取ると言うも、油屋のほうから借りると申し出る型である。
また、茶碗の見込み額と実際に売れた額は、六百両(これは茶金が茶店で六回首をひねったから)となっていたが、上方落語「はてなの茶碗」では千両である。
上記のような相違は、東京と上方で常態化してあるものっだろうか。たとえば、両者には和歌についての相違もあるが、これは明らかに東京と上方で常態化している相違である。
今日気がついた子細な相違はまた今後の宿題にしておこう。ただ、東京の落語家では、これをさまざまな人がかけるという事情にないのだろうか。主として聞くのは、この歌武蔵以外だと、十一代目金原亭馬生と四代目三遊亭金馬である。他に一回だけだが、春風亭正朝でも聞いたことがある程度。