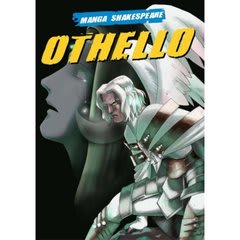一昨日(火曜日)の夜、夏学期のクラスのシラバスがやっとアップされました!
コースはモジュール形式でそれぞれのモジュールに課題が出ています。
モジュールは全部で14あるので14の課題を提出することになります。
これでスケジュールにそって課題に取り組めると思ったら・・・・
このクラス、
課題の提出期限がないんですよ~!
シラバスには、
「モジュールを仕上げるのに期限はもうけていないので、各自のペースにそって、
尚且つそれぞれのモジュールに十分な時間配分を考慮して、課題を提出すること。
1週間に1つか2つのモジュールを仕上げるのが理想的。
このペースで進めばコースの内容をちゃんと理解出来るはず。
学期末にまとめて多数の課題を提出した場合、
まともなフィードバック、成績は期待しないこと。」
と書いてありました。
そして、そして、去年の春学期にこのドクターW・Hのクラスを受けた時もそうでしたが、
彼女の院クラスでは与えられた最低限の課題をこなすと成績はB。
でもAがほしかったらペーパーを書かなければなりません。
シラバスにも書かれてありました。
If you have had me for a graduate course before, you know my "A" policy.
「前に私の院のクラスを取ったことがあれば、Aを取るためのポリシーは知っているはずね。」
はいはい、わかっていますとも。
(ドクターW・Hの“Aポリシー”はこちらのブログ記事に詳しく載ってます)
このペーパーは“モジュール15”としてアップされています。
今回のペーパーは去年の春学期以上に苦しみそう。
ドクターW・Hがペーパーの参考文献として承認した本のリストがシラバスに載っているのですが
あんまりチョイスがないのに加え、私の興味をそそるようなトピックがないんですよ~。
早くトピックを決めて書き始めないと!
でも嬉しいことに学期中、週末に3回位キャンパスで授業をやるのです。
オンラインクラスを取るたびにつくづく“私はオンライン向きじゃないな~”と思うんですよ。
オンラインだと孤独になってしまうんです、私。
わからないことなどすぐ質問できて、すぐ答えが返ってくる状況に身を置いていないと
落ち着かないんです。
それにドクターW・Hのキャラクターが大好きなんで。話も面白いし。
去年の春学期最後の授業の後で長々と井戸端会議しちゃったし。
来週末、第1回目の授業があります。今からクラスメートやドクターHに会うのが楽しみ!
コースはモジュール形式でそれぞれのモジュールに課題が出ています。
モジュールは全部で14あるので14の課題を提出することになります。
これでスケジュールにそって課題に取り組めると思ったら・・・・
このクラス、
課題の提出期限がないんですよ~!
シラバスには、
「モジュールを仕上げるのに期限はもうけていないので、各自のペースにそって、
尚且つそれぞれのモジュールに十分な時間配分を考慮して、課題を提出すること。
1週間に1つか2つのモジュールを仕上げるのが理想的。
このペースで進めばコースの内容をちゃんと理解出来るはず。
学期末にまとめて多数の課題を提出した場合、
まともなフィードバック、成績は期待しないこと。」
と書いてありました。
そして、そして、去年の春学期にこのドクターW・Hのクラスを受けた時もそうでしたが、
彼女の院クラスでは与えられた最低限の課題をこなすと成績はB。
でもAがほしかったらペーパーを書かなければなりません。
シラバスにも書かれてありました。
If you have had me for a graduate course before, you know my "A" policy.
「前に私の院のクラスを取ったことがあれば、Aを取るためのポリシーは知っているはずね。」
はいはい、わかっていますとも。
(ドクターW・Hの“Aポリシー”はこちらのブログ記事に詳しく載ってます)
このペーパーは“モジュール15”としてアップされています。
今回のペーパーは去年の春学期以上に苦しみそう。
ドクターW・Hがペーパーの参考文献として承認した本のリストがシラバスに載っているのですが
あんまりチョイスがないのに加え、私の興味をそそるようなトピックがないんですよ~。

早くトピックを決めて書き始めないと!
でも嬉しいことに学期中、週末に3回位キャンパスで授業をやるのです。
オンラインクラスを取るたびにつくづく“私はオンライン向きじゃないな~”と思うんですよ。
オンラインだと孤独になってしまうんです、私。
わからないことなどすぐ質問できて、すぐ答えが返ってくる状況に身を置いていないと
落ち着かないんです。
それにドクターW・Hのキャラクターが大好きなんで。話も面白いし。
去年の春学期最後の授業の後で長々と井戸端会議しちゃったし。
来週末、第1回目の授業があります。今からクラスメートやドクターHに会うのが楽しみ!


























 )
)