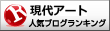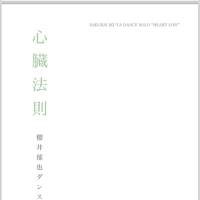【イメージを食べる】
今日1月27日は、基礎クラスの稽古日。
レッスンの途中、「食べるような感じで動いて・・・!」と言いました。
光を食べるように・・・
闇を食べるように・・・
この言葉、ふとした直感から出たまでなのですが、とても良い反応です。
からだを大きく動かしながら、呼吸を全身運動に反映させるエクササイズだったのですが、それまでヨイショっという感じで動いていた人が、「晴れやかにしなる青竹のような動き」に変化しているんです。
「食べる」という、最も身に近しい用語が、各自のもてるイメージ力に連動したに違いありません。
思い返せば、「食べる」という感覚はとてもダンスに重要で、僕自身もよくそんな感覚を抱きながら踊ります。
運動のプロセスに、的確なイマジネーションが与えられると、不要なこわばりがとれ、からだは雄弁で有機的な表現体へと変わっていきます。
呼吸と運動のリズムが、イメージの変化と相互に影響し合いながら、代謝を始めとする内部器官の働きにもリンクし、肌・顔・眼に潤いが現れる。
そうした自らの変化に対する気づきが、また良い循環へと作用する連鎖を生み、「晴れやかにしなる青竹のような動き」を発生させるのでしょう。反対に・・・。
ここが悪い・あそこが気に入らない・何とか直さねば・・・。
等と思っているときのからだは、やはり、こわばって顔面もろともいかめしい感じになります。善し悪し、という言葉、正しい・間違っている、という言葉は、一見具体的ですが、多様なイメージの発展に結びつきにくい抽象的な観念の言葉です。きつい眼をして、あちこちをいじくりまわす矮小な動きが出て、ひずんだ機械のようになってしまいます。これは負のイメージを食べて悪循環と戦っている身体で、孤独な感じがします。稽古ですから、もちろん修正は必要なのですが、「どんな言葉で」修正するかは、もっと大事です。
その言葉を食べてからだが変化するわけですから。
【なぜ食べる?】
そういえば・・・。
「どうして食べないと死んじゃうの?」って、ある時、小さな子どもから尋ねられました。
「ヒトリになっちゃうから・・・」って、答えたら、「ヒトリになったら大変だものね」と返ってきました。
栄養があるとか無いとか、それも大事なんだろうけど、いま食べてるモノ・コトと繋がっていく実感、それが食だと思います。
食べることによって認め・受け入れ、命を保つということ。食は繋がり。
そう思えば、おのずから食事への思いも変化してきます。素材・色彩・質感・温度さることながら食べ物には、つくった人があり、その背景・履歴さえもがありますから、ほんの一品食べるにも、様々な感覚を使って、とてもいろんなモノ・コトと関わる事になります。じっくり食べれば、食物との膨大な情報交換のなかで想像力がかきたてられ、イメージのひろがりを感じます。もしかすると、食はイメージの原動力にもなっているのではないでしょうか。
ともかく、僕らは、色んなものを食べている。口から、眼から、耳から、肌から・・・。
良い繋がりを循環させる事で、僕らは存在の仕方を定めていくのでしょう。
ダンスもまた、そんな「いとなみ」のひとつ。
カラダを動かしながら、あるいは動く身体を見つめながら、様々なイメージを食べているんだと思います。
カラダから入って来たさまざまなイメージ・言葉・音楽などが、血肉を通した表情・温度・輝きとなって再び外の世界に放出されるのがダンス。
植物は、じっさいに光を食べているそうですが、ダンサーはイメージを食べながら成長するものなのかもしれません。
光合成ならぬイメージ合成とでも申しましょうか・・・。
今日1月27日は、基礎クラスの稽古日。
レッスンの途中、「食べるような感じで動いて・・・!」と言いました。
光を食べるように・・・
闇を食べるように・・・
この言葉、ふとした直感から出たまでなのですが、とても良い反応です。
からだを大きく動かしながら、呼吸を全身運動に反映させるエクササイズだったのですが、それまでヨイショっという感じで動いていた人が、「晴れやかにしなる青竹のような動き」に変化しているんです。
「食べる」という、最も身に近しい用語が、各自のもてるイメージ力に連動したに違いありません。
思い返せば、「食べる」という感覚はとてもダンスに重要で、僕自身もよくそんな感覚を抱きながら踊ります。
運動のプロセスに、的確なイマジネーションが与えられると、不要なこわばりがとれ、からだは雄弁で有機的な表現体へと変わっていきます。
呼吸と運動のリズムが、イメージの変化と相互に影響し合いながら、代謝を始めとする内部器官の働きにもリンクし、肌・顔・眼に潤いが現れる。
そうした自らの変化に対する気づきが、また良い循環へと作用する連鎖を生み、「晴れやかにしなる青竹のような動き」を発生させるのでしょう。反対に・・・。
ここが悪い・あそこが気に入らない・何とか直さねば・・・。
等と思っているときのからだは、やはり、こわばって顔面もろともいかめしい感じになります。善し悪し、という言葉、正しい・間違っている、という言葉は、一見具体的ですが、多様なイメージの発展に結びつきにくい抽象的な観念の言葉です。きつい眼をして、あちこちをいじくりまわす矮小な動きが出て、ひずんだ機械のようになってしまいます。これは負のイメージを食べて悪循環と戦っている身体で、孤独な感じがします。稽古ですから、もちろん修正は必要なのですが、「どんな言葉で」修正するかは、もっと大事です。
その言葉を食べてからだが変化するわけですから。
【なぜ食べる?】
そういえば・・・。
「どうして食べないと死んじゃうの?」って、ある時、小さな子どもから尋ねられました。
「ヒトリになっちゃうから・・・」って、答えたら、「ヒトリになったら大変だものね」と返ってきました。
栄養があるとか無いとか、それも大事なんだろうけど、いま食べてるモノ・コトと繋がっていく実感、それが食だと思います。
食べることによって認め・受け入れ、命を保つということ。食は繋がり。
そう思えば、おのずから食事への思いも変化してきます。素材・色彩・質感・温度さることながら食べ物には、つくった人があり、その背景・履歴さえもがありますから、ほんの一品食べるにも、様々な感覚を使って、とてもいろんなモノ・コトと関わる事になります。じっくり食べれば、食物との膨大な情報交換のなかで想像力がかきたてられ、イメージのひろがりを感じます。もしかすると、食はイメージの原動力にもなっているのではないでしょうか。
ともかく、僕らは、色んなものを食べている。口から、眼から、耳から、肌から・・・。
良い繋がりを循環させる事で、僕らは存在の仕方を定めていくのでしょう。
ダンスもまた、そんな「いとなみ」のひとつ。
カラダを動かしながら、あるいは動く身体を見つめながら、様々なイメージを食べているんだと思います。
カラダから入って来たさまざまなイメージ・言葉・音楽などが、血肉を通した表情・温度・輝きとなって再び外の世界に放出されるのがダンス。
植物は、じっさいに光を食べているそうですが、ダンサーはイメージを食べながら成長するものなのかもしれません。
光合成ならぬイメージ合成とでも申しましょうか・・・。