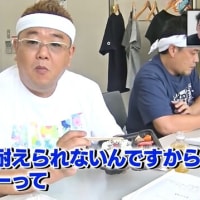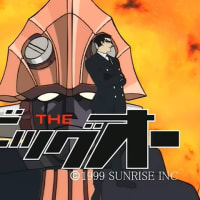タイトルにはいろいろありますが、「新人王」は一生に一度のチャンスしかありません。
今年は2017年中日ドラゴンズドラフト1位の期待のルーキーで、開幕一軍を勝ち取った、鈴木博志選手が新人王の筆頭になると思っていました。
シーズン当初から勝ちパターンの7回や8回で登板、セットアッパーとしてフル回転し、開幕してから9試合連続無失点に抑えるなど、新人離れした活躍をみせ、ホールドポイントを積み重ねていきました。
5月後半には打ち込まれ一時は防御率が4点台を超えましたが、交流戦明けから無失点ピッチングで復調の兆しが見え、7月には不調の田島選手に代わって守護神に大抜擢されました。しかし、8月から打ち込まれ、二軍調整のままシーズンが終わってしまいました。
新人王争いからは、一歩後退した状況です。
さて、史上最年少プロ棋士の藤井聡太七段(16歳)は10月17日、新人王戦優勝最年少記録を31年ぶりに塗り替える歴史的快挙を果たしました。
藤井さんはこだわりが強く、自分が納得できないときには、納得いくまでこだわり抜くタイプだそうです。中学三年生のときに、担任の先生に、「なぜ宿題をやる必要があるのか」と聞かれ、藤井さんと担任先生は、宿題の意義について30分間話し合ったことがあるそうです。
藤井さんが通っていた中学は、名古屋大学教育学部附属中・高校(愛知)は、名古屋大学教育学部の附属学校であり、国立学校では唯一の併設型中高一貫校です。中学校は1学年2クラスの80名、高等学校は1学年3クラスの120名です。
生徒は県内以外に岐阜県、三重県から通っています。中学生にとって、クラスの生徒の出身地区は違います。さまざまな分野で特技を持つ生徒が互いを尊重し、認め合う雰囲気を感じます。
担任先生によりますと、藤井さんはこだわりが強く、自分が納得できないときには、納得いくまでこだわり抜くタイプでした。昨年4月のこと、藤井さんから「なぜ宿題をやる必要があるのか」と聞かれ、宿題の意義について30分間話し合ったことがあるそうです。
「なぜ、やらないといけないのでしょうか」「宿題も授業のうちに入るのではないでしょうか」と聞く藤井さんに、担任先生は「授業の中では理解が十分ではないところもあるので、十分になるように宿題を出している」と説明しました。藤井さんは「理解を助ける上で必要」と、宿題の意義を理解してくれたそうです。
いいですか、小中高のみなさん。ここ↑のところは重要なことですよ。
藤井さんは授業中、最初から最後まで集中していました。謙虚で礼儀正しく、普段の落ち着いた雰囲気が対局にも表れていると感じていたそうです。また、鉄道好きで、学校での休み時間は、友人と電車の話題が中心だったそうです。担任をした当初、将棋のことを話したほうがいいのか迷いがあったそうです。しかし、藤井さんはそれを望んでいないことを感じたそうで、校内では対局を忘れ、学校生活を充実してほしいと思い、クラス全体の一人として接したそうです。クラスの生徒も藤井さんの気持ちを察し、将棋の話題を控えていたそうです。ただ、藤井さんが対局で学校を欠席しているときには、クラスの話題の一つは将棋だったそうです。
それでも、対局前日に声を掛けると、「ありがとうございます。頑張ります」と笑顔で返してくれていたそうです。勝った日の翌日に、クラスメートから「おめでとう!」と言われると、はにかんでいるという、至って普通の中学生の反応だったそうです。
藤井さんは中学三年生の総合的な学習の時間である「総合人間科」にとても興味を持っていたそうです。昨年11月には研究旅行で広島を訪問し、「国際理解と平和」をテーマに平和学習を行いました。藤井さんも事前学習を行い、研究旅行でフィールドワークを実施しました。
研究旅行では、行く先々で声を掛けられていましたが、その中で学習の場であることに気を使っていた方もいたそうです。
今年3月の中学修了式、中学生最後の日。解散後、クラスの生徒が藤井さんとの写真撮影を頼んでいたそうです。日頃は、藤井さんをクラスメートの一人として接してきたクラスの生徒が、その瞬間だけは特別な存在として接していたそうです。
言うまでもなく、新人王戦は若手の登竜門です。将棋界の若手は、いつの時代もみな強け、新人王戦で優勝することは簡単なことではありません。。
現在、高校一年の藤井さんの年齢は、まだ16歳と2ヶ月です。何をしても同時に最年少記録が更新されるという感のある藤井さんが、この後も、何らかの記録をいくつも更新していくことは、ほぼ間違いないでしょう。