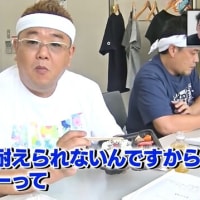中国を中心として新型コロナウィルスのニュースが世界各地のトップニュースになっています。発生地域を見ますと、南アフリカ大陸とアフリカ大陸ではまだ発生は確認されていません。
しかし、アフリカ大陸東部ではバッタやイナゴが大量に発生して農作物や牧草を食い荒らす「蝗害(こうがい)」が深刻な被害をもたらしています。
今回発生しているバッタの大群はエチオピアとソマリアで発生し、ケニアに拡散。ケニアだけで、バッタの大群は縦60km、横40kmという広範囲となっており、風に乗り北側のエチオピアやソマリアにも侵食。エチオピアやソマリアでは過去25年間、ケニアでは過去70年間で最悪の状況になっており、さらにジブチやエリトリアにも侵食しています。
国際連合食糧農業機関(Food and Agriculture Organization = FAO)は、「非常に深刻で前例のない脅威である」「何らかの対処をしなければ、2020年6月までにバッタの数が500倍に増大し、ウガンダと南スーダンにまで被害が拡散するおそれがある」と危惧しています。ウガンダと南スーダンに広がると1961年以来の蝗害発生となります。
発生しているのはサバクトビバッタです。このバッタは体重は約2gと個体は小さいものの、自重と同量の食料を毎日摂取し、1日あたり150kmを移動する能力を持つそうです。
FAOの予測によると、ケニアでは2,400平方kmにわたって約2,000億匹のサバクトビバッタの大群が押し寄せ、すでに約70,000haが被害を受けていたそうです。これだけでは、ピンとこないかも知れませんが、これは、約35,000人の一日分の食料に相当する農作物を毎日食い荒らすことができるということで、今後、繁殖が進めば被害がさらに深刻化する可能性があるのです。また、短期間で繁殖しながら長距離を移動するため、広範囲にわたって脅威となり、地域住民の食料のみならず、家畜用飼料も不足し、農業や畜産業に大きな被害をもたらすのです。
すでにソマリアでは国家非常事態が宣言されており、ケニア、エチオピア、ソマリアなどのアフリカ東部のみではなく、サウジアラビア、イエメン、イラン、インドやパキスタンなどでも同様の蝗害の発生リスクが指摘されています。
発生してた原因として、東アフリカでは2019年10月から12月までの雨季の降雨量が過去40年間で最多であり、高温と大雨が繁殖に適した環境であることから、サバクトビバッタが大量に発生したとみられています。
国連では1月23日、東アフリカでのサバクトビバッタの大量発生に伴う被害への対策として、国連中央緊急対応基金(CERF)から1,000万ドル(約10億8,500万円)を充てることを発表し、FAOでは最も深刻な被害を受けているエチオピア、ケニア、ソマリアの3ヶ国を対象に、防除作業と住民の生活保護に向けて7,000万ドル(約75億9,500万円)の緊急支援を呼びかけています。
このニュースで思い出したのが、「小説現代(講談社)」で1977年9月号から1978年7月号まで連載されていた、西村寿行さんの小説「蒼茫の大地、滅ぶ(そうぼうのだいち ほろぶ)」です。
1977年7月に幅10km、長さ20km、総重量1億9,500万tの中国大陸で大量発生した飛蝗(トノサマバッタ)が日本海を渡り、東北地方に襲いかかって農作物を食い尽くしてしまう・・・というストーリーです。
地球温暖化の加速による気候変動の増大はすでに多様な形で現実化しています。
日本では2019年に大型台風の連続襲来で受けた大規模な自然災害、オーストラリアでの異常乾燥の長期化による森林火災、米国西海岸地域やシベリアなどの森林火災、そして今回のアフリカでの生態系への異常な影響による生物種の過剰発生など。
また、今回、世界各地で感染が広がっている新型コロナウィルス。
地球が警告を発しているのかも知れません。もしかすると、すでに後戻りできないレベルを超えているのかも知れません。