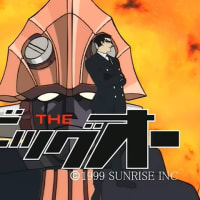審判はあらゆるプレーで迅速かつ正確なジャッジが求められ、ルールの適用で判定しなければなりません。中でも高校野球の審判は与えられた役割と権限が大きく、一度下された判定が覆ることはほとんどありません。最近は審判の権限が強すぎるという声もあるようで、試合進行の黒子であるはずの審判が「高校生らしさ」を求める場面が目につきます。
高校野球では、元々審判の下した判定はたとえ誤審と分かっていても基本的には従わざるを得ません。そもそも高校野球の監督にアピール権がないため、主将が監督の代わりに審判にアピールすることになりますが、大人と子どもの立場でもあり、よほどのことがない限りアピールはとおりません。
中島隆信慶応大教授の著書「高校野球の経済学」(東洋経済新報社)によれば、「高校野球における審判は単に判定を下すだけの存在ではない」とのことで、「高校生たちがルールを遵守し、スポーツマンシップに則って“高校生らしく”野球をやっているかをチェックすることである。それは、試合が単なる遊びではなく、教育の一環になっているかどうかということである」と解説しています。
つまり、高校野球の審判も試合における「教育者」ということになります。となりますと、強いて言えば、高校野球に関係する人、みんなが「教育者」ということなんでしょう。と、その辺の議論は、置いといて。
「高校生らしさ」に高野連がこだわれば、現場の最高責任者ともいえる審判もおのずとプレーやプレー以外のところでの細部にまで見たりして、らしくない球児を見つけては注意を与えなくてはいけません。
昨年、バットをヌンチャクのように振り回す選手が話題となりました。その噂は海を越え、MLBでも真似するくらいでしたが、高野連は「当該校には注意します。遅延行為になりますし、危険行為にもなる。バットが捕手に当たる可能性もありますから。この暑い時期ですし、生徒のことを考えたら、なるべく早く試合を進行させなければならない。ボール回しもしないようにしているぐらいです。それに余計なパフォーマンスをするな、ということで、ガッツポーズも禁止しているぐらい。認めるわけにはいきません」と注意を与えました。
「教育の一環」とする高校野球では、高校野球ならではのルールが多数存在しています。甲子園大会で適用されている「高校野球特別規則」や「周知徹底事項」などにより、以下のように定められています。
・金属バットはツートンカラーは認めない
・大会で使用するユニフォームは1大会1種類(学校名表記が漢字とローマ字の2種類を保有する場合など)
・同一イニングでは、投手が一度ある守備位置についたら、再び投手となる以外、他の守備位置に移ることはできない(これは過去に、地方大会で相手バッターの左右が変わるたびにピッチャーを何度も入れ替えた監督がいて、高校野球らしくないとルール化されたものです。勝負に徹せず、正々堂々と戦うことを求めている?)
・攻守交代時、先頭打者、次打者、ベースコーチはミーティングに参加しない
・サインは複雑なものにしてはいけない
・離塁していない走者への遅延行為とみられるけん制はしない
・内野手が投手に返球する時はマウンドまで行かない
など。
以前には、甲子園での“カット打ち”が議論になり、「打者が意識的にファウルにすること」も事実上禁止となっていますし、マナーについても細かいです。
・本塁打を打った打者の出迎えをしない
・ベースコーチが打者走者の触塁に合わせて“セーフ”のジャスチャーをしない
・投手のウォームアップ時に打席付近に立ってタイミングを測る行為の禁止
・派手なガッツポーズは相手への侮辱につながるので慎む
などなど。
地方大会で問題にならなかったプレーが甲子園では一転、審判から注意を受けるという場合もあります。
近年、甲子園という名のブランドと選手のスター化を社会的に煽っている風潮があるように見えます。
ファンが多くなり、注目を浴びるというのはいいことだとは考えます。
季節ものイベントですからある程度は仕方がないのでしょけど、同じスポーツニュースとして、プロ野球より大きく取り扱わられたり、時には安倍首相の国会答弁よりも先に取り扱われたりと、取り上げ方が「高校生らしく」しているのかどうか。そして、世間は高校野球というものを「教育」しているのかどうか。