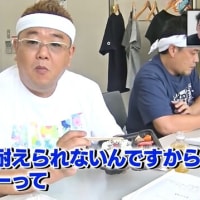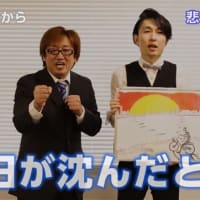以前、報道ステーションに松岡修造さんとメンタルトレーナーの辻秀一さんがレスリングの吉田沙保里選手にインタビューした時に、松岡さんは「ゾーンを目指して必死にメンタルトレーニングをやった」と言っていたのに対して、吉田選手は「修造さん、ゾーンに入ろうとするから、ダメなんですよ」と答えていました。
ゾーンは入ろうとして入れるものではないですから、ボールが止まって見えるような状態の、一生に何回あるかという現象を安易に求めても無理です。仙人ではあるまいし、そう簡単にゾーンには入れません。簡単にゾーンに入ることが出来るのならば、野球で4割を打つことも容易に実現出来るかもしれません。
「そもそもゾーンは偶然性が高く、それを意識してコントロールするのが難しい。そうではなく、ゾーンがやって来るように、日頃から心にエントリーをして心創りをしておくこと。そのマネージメントこそが大切です。意識するべきは、ゾーンの手前の“フロー”という心の状態を作ることです。揺らがず、とらわれず、流れがあり、集中とリラックスが同時に行われているような、一言で言えば“余裕”や“ごきげん”な状態。それがフローです。自分の心をフローの状態に切り替える脳の習慣を持っておき、ゾーンがやってくる可能性がある」
とのことです。ゾーンの手前のフローの状態であるならば、何とかなるかも知れません。
さて、人間の脳の機能の第一に「認知」があるそうです。その認知は「環境」「出来事」「他人」に結びつくそうです。例えば環境というのは天気や試合会場、出来事は試合の展開、他人とは相手選手やチームメート。この3つの要素を脳が認知して「何をやるべきか?」を常時判断します。このブログを読んでいる方でも、今は「へー」とか「何んだかなあ」と何らかの反応をします。人間はこういう認知に長けていて、スポーツが出来る人は特に認知することが発達しているそうです。
このボールを打つべきか、見逃すべきか。打つなら引っ張るか、流すか、それともセンター返しか…認知の脳はこれらを瞬時に判断し、スポーツの技能や戦術を高めてくれます。
一方で認知には厄介なこともあり、勝手に独自の「意味付け」を起こしてしまうそうです。たとえば最終回に5点差で負けていると「ヤバい!」という意味が付く。これが脳が作った意味なのだそうです。「強いチーム」と言うけど、本当は強いチームは世の中に存在しない、あのチームが強いと意味を付けているチームがあるということだそうです。「苦手」という相手も存在せず、誰かが苦手という意味を付けているだけとのことです。
吉田選手が世界選手権で残り3秒で逆転勝ちをした試合について、松岡さんは「ああいうとき、焦ったりしないんですか?」と聞いたら、吉田選手は逆に「みんな焦るんですか?」と聞き返してきて、「ただ一生懸命にやっていればいつも一緒で、それが楽しいんじゃないですか」「今に生きるということだけを意識していればそれでいい」「すべきことにだけ全力を注ぐしかないです」と答えていました。
辻さんは「『意味付けをやめろ』ということではないんです。自分が意味を付けていることに気付くこと。自分の“揺らぎ”や“とらわれ”は、自分自身が勝手に作り出していることだと、“気付く力”が重要なのです」と言っています。
3秒が短いとか最終回の5点差は厳しいとか。相手ピッチャーは150km/hを投げるとかは自分たちが作った意味付けにすぎないと言うことなのですよね。
良い意味付けはそのまま、良くない意味付けをなくすこと。それだけで少しは楽になり、フローの状態へと近づけることでしょう。
コメント一覧

まっくろくろすけ

eco坊主
最新の画像もっと見る
最近の「高校野球」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事