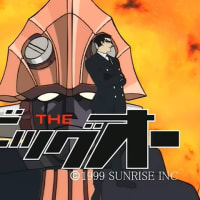沖縄県は美味しいものが多く、私的に沖縄を訪問した際に絶対外せないのが、地元で「そば」、あるいは方言で「すば」「うちなーすば」とも呼ばれている「沖縄そば」です。一口に、沖縄そばといっても、お店によって味のバリエーションも様々で、老舗の味から進化形のお店まであります。
最近は、こちらでも沖縄料理店が増えてきて、沖縄そばを食べることができますが、琉球家屋のお店や、絶景のロケーションで食べることができるお店など、地元という調味料にがプラスされることで、一味違うものになります(私の「食べ歩記」は後年のネタ用に残してあります)。
発祥については諸説ありますが、沖縄での麺料理は琉球王国時代に中国南部から伝来し、中国からの使者をもてなす接待料理に取り入れられたという説があり、小麦粉を原料とした麺料理が一般になったのが、明治後期以降に本土出身者が連れてきた中国人コックが開いたラーメン店が、沖縄そばの直接のルーツともいわれているようです。
その後、一般に食べられるようになったのは大正時代であり、当初は清湯スープ(豚のだし)をベースにした醤油味のスープで、具材も豚肉とネギのみと、本土のいわゆる醤油ラーメン的なものだったらしいですが、その後、沖縄での味覚に合わせた改良が重ねられた結果、現在のようなスープ、三枚肉、沖縄かまぼこ、小ねぎを具材として、薬味として紅しょうがや島唐辛子の泡盛漬けという、独自のスタイルになったようです。
こちらでは、お店以外では気軽の食べることはなかなかできませんが、ときどき、インスタント麺や半生麺がスーパーなどで売られており、その際に購入して、沖縄風を味わっています。
ちなみに、そばとは呼ばれていますが、こちら信州などとは違って、そば粉は一切使われず小麦粉のみで作られ、かん水または木灰(もっかい)と呼ばれる、ガジュマルなどの亜熱帯の樹木を燃やした灰を水に溶かした上澄み液を加えて打つ麺を使用しています。なお、沖縄ではそば粉を用いたそばは、「日本そば」「ヤマトのそば」「黒いおそば」などと呼んでいるそうです。
さて、沖縄といえばステーキも安くて美味しいですが、沖縄でも大手のチェーン店を展開している「ステーキハウス88」を運営する沖縄テクノクリエイトでは、後継者不足で悩んでいた、那覇市の老舗日本そば店「名代蕎麦処美濃作(みのさく)」の事業を承継しました。
2020年6月末で店舗は閉店しており、ステーキハウス88辻本店の2階に移転し、8月8日から営業を再開しています。
美濃作の店主だった小山健さんは東京で日本料理人をしていましたが、知人から浦添市牧港にあったレストランで働かないかと打診を受け、沖縄がまだ米国統治時代の1969年に沖縄に来ました。その後、「沖縄には日本そばを食べさせる所がない。やってみないか」と、糸満市にある食品会社の会長から声を掛けられ、1977年に那覇市に日本そば屋を出店しました。
沖縄そばのイメージが強い沖縄で日本そばを出した当時は仕事や観光で訪れた県外出身者から厳しい視線を浴びたそうです。それでも、研さんに励み、1983年に沖縄ハーバービューホテルで開かれた日本ホテル協会総会のため、沖縄の植物である月桃(げっとう)を練り込んだそばを考案し、月桃の爽やかな香りと深い緑色のそばは評価され、お店の代表メニューとなっていきました。
事業承継により小山さんは、沖縄テクノクリエイトから派遣された金城大輔さんに技を伝授するとともに、「月桃そば」も引き続き提供できることになっています。また、美濃作の看板は変わらず、従業員も引き継がれるそうです。金城さんは「大将(小山さん)が作ってきた歴史ある美濃作の看板を忠実に再現したい。技だけでなく心意気も引き継いでいく」と語り、小山さんは、「涙が出るような言葉をいってくれる。第2の出発にワクワクしている」とのことです。
世界どのお店でも食べることのできない美濃作の日本そば。次回、沖縄を訪問させていただいた時には、寄ってみたいと思っています。
■外出の際は、手洗い、咳エチケット等の感染対策や、「3つの密」の回避を心掛けましょう。
■新型コロナウイルス感染対応を呼び掛けている場所やお店などがある場合は、指示にしたがいましょう。
■お出かけの際は、各施設、イベントの公式ホームページで最新の情報を確認しましょう。
私のブログにお越しいただいてありがとうございます。また、明日、ここで、お会いしましょう。