
人間衰えるってことは誰にも、いつの時でもあるんだろうが
それをハッキリ認識するのは案外簡単ではないのかも知れない。
プロのスポーツ選手なんかは肉体の衰えがスコアとして現れる故に
引退の時期を間違えようもないのだろう。
彼等の場合は随分若い年齢で衰えを認めざるを得ないのは辛いものがあろう。
そういうトップ・レベルの衰えはさておいて
並の人間にも色んな面での衰えが押し寄せて来るのだが
それを柔らかく受け止め、認めて、衰えと共に生きるのが達人の生き方だ。
衰えに抗い、目くじら立ててアンチエイジングだなんてのは
衰えよりも見苦しいのかも知れないな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オイラも15年ほど前は彫金にのめりこんでいた時期。
当時は夜中に目が覚めるとノコノコ起き出してバーナーに点火してた。
何か思いつくとすぐさま、銀の地金からモノを作ってたように思う。
その頃作ってたものを再現しようと思い立ち
チョコチョコやってみるのだが・・・
なんだかうまくいかないのである。
ヤスリの掛け方を忘れてたり
地金を圧延するのに適当な厚さを忘れてしまってたり
ロウがうまく流れなかったり
熱を加えすぎて銀が溶けてしまったり・・・
もう、やることなすこと、昔のように行かないのだ。
失敗しては、またやり直す。
そしてまた失敗する。
これは明らかに技術の衰えなのだと思う。
しかし・・・誰しも衰えるものなら・・・仕方が無いぢゃないか。
腹を立てずにもう一度やればいいぢゃんか?
ここ数日そんなことをしながら暮らしておりました。
トップの小型ペンダントは
最初に使うべきロウの選択を間違えたため
次の溶接時に
黒い赤銅に埋め込んだ銀線の一部が溶けてしまって穴が残った失敗です。
そんなことがあちこちで起きます。

これも銅板に複雑な処理を施したのですけど
ロウが綺麗に流れてくれず
あちこちにロウ引けが起きた失敗です。
ことほど左様にロウ付けってのは何回かに分けて行う場合
最初に使うロウ、次の工程で使うロウ、その次に・・・という具合に
高温でないと溶解しないロウから使い始めて・・・
最後は一番低温で溶けるロウへと移って行きます。
銀ロウでもカバーし切れない場合は半田付けまで登場します。
ロウが溶ける温度(摂氏)は大体次のようです。
二分ロウ・・・820度
三分ロウ・・・780度
五分ロウ・・・750度
七分ロウ・・・720度
早ロウ・・・620度
半田・・・160度
溶解する温度の差が小さいことが判りますね。
5分ロウで何かを溶接しようとしている場合
その前の工程で3分ロウを使ってる場所があると
5分ロウだけでなく3分ロウで付けてあったところまで溶かしてしまうことがある。
それはバーナーの炎の大きさ、供給しているエアの量、そして加熱時間などによります。
そんなことが体験的に身について何時でも適温が与えられるようになると
ロウ付けはスムースにいきます。
それは感覚的なものなので、やはり普段からやりなれてないとうまく行かないんです。
こういう感覚の保持力も老化とともに衰えるのかもしれません。
まぁ~衰えた証拠として残しておいてやれ!と開き直ってはいますけど。
シブトくやってるうちにまぁまぁなのが出来たので
ブローチにしてみました。


しかし、コイツはコイツで革の中央に楕円をカットするのが存外難しくて
ここまで来るのに何枚も無駄な革を出してしまいました。
ぼちぼち行こうかいなと思います。












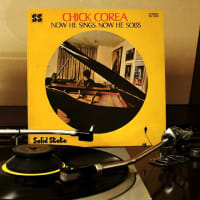







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます