
高村薫さんと考える:今月のテーマ 老後を迎えた団塊世代
<with 藤原健・編集局長>
ベビーブーム、受験競争、学生運動に全共闘、高度経済成長、そしてリストラ……。団塊の世代(注1)を語る言葉を連ねるだけで、時代の断面が見えてくる。数の多さだけでなく、大きな存在感を示してきたその世代が、社会の一線から身を引き始めた。高齢社会の日本で、彼らはどう生きていくのか。高村さんは、後輩として団塊の世代にエールを送った。「メンツはもういい。自分の人生のためにエネルギーを使ってほしい」【構成・若菜英晴】
◇若い世代に道譲り、頑張らない働き方を
藤原健・編集局長 私(1950年生まれ)は団塊の世代と1年しか違わない。大学に入ると東大闘争(注2)をはじめ各大学では学生運動で盛り上がっていましたが、結局敗れて、70年安保を経て社会に入り、高度経済成長を担ったのが団塊の世代。そのちょっと下の世代になる高村さんからは、どのように映っていましたか。
高村薫さん 団塊の世代の人たちが学生運動を激しく展開していた時期、私は高校に入学した時でした。冷めた目で見ていました。何であんなに群れるのかな、と。
藤原 群れるというより人数そのものが多かった。学校は1クラス55人でした。その多さゆえに、常に社会的政策の対象となってきました。その人たちが定年退職を迎えつつあります。
高村 団塊の世代が定年を迎えて、その後も社会的存在でいられるのはせいぜい十数年。そば打ちだとか田舎暮らしだとかメディアはあおっていますが、そんな生活ができるのは一握りで、多くは年金をもらいながらも働かなくてはいけない。ローンが残っていたり、子どもがまだ独立していなかったり、自宅のリフォームもしなくちゃいけない。定年後は決して楽じゃない。そういうシビアな認識を持つことから始めないといけないと思います。
藤原 コマーシャルベースに乗った生き方をする人は少数です。
高村 そういう生き方を否定するつもりはありませんが、悠々自適とはいかない。働かなくちゃいけない。ただ、心の持ち方は変えてほしい。第一線という意識を捨てることです。働かねばならないが、譲っていく、つまり頑張らないということです。
人口減少社会の中で、若い世代と60歳以上の世代で仕事のすみ分けが必要だと思います。日雇いや派遣は60歳以上が担い、若い世代にはきちんとした給料取りになってもらうことです。若い世代が幸せになることは社会全体や団塊の世代のためでもあります。そのために何をしたらいいかを団塊世代の人たちは考えてほしい。
藤原 団塊世代には自分たちが社会を引っ張ってきたという自負心もありますが。
高村 社会の歯車、という思いはありませんでしたか。私にはそう見えて「つらい」と思っていましたが……。
これからは頑張らず、社会の一線に立たず、自分のためにエネルギーを使ってほしい。団塊の世代を気の毒と思うのは、一生懸命働いてそのお金を子どもに多く使ってきたこと。バリバリ稼いで消費する生活ではなく、残りの人生に向けて生活の縮小を考えてほしい。
藤原 人生のいい店じまいの仕方を考えようということですね。
高村 働かなければならないから隠とん生活というわけにはいきませんが、現役時代にはできなかった「ものを考え、人生の整理縮小を図る生活を送る」ことは精神の充実につながります。
藤原 そのような見本の人は、知人や友人におられますか。
高村 田舎に行けば、いつお迎えが来てもいいという心境に自分をもっていく人がいらっしゃいます。
◇今こそリセットのチャンス、一人で生き方考えよう
藤原 私の世代を含め、実は団塊の世代から総理大臣もノーベル賞受賞者も出ていないんですね。これだけ絶対数が多くて競争して勝ち残った人がいるはずなのに。アメリカにはさまざまな矛盾はありますが、クリントン前大統領のようなベビーブーム世代のリーダーが生まれている。
高村 激しい学生運動をして政治意識も高かったはずなのに、不思議ですね。社会人になってからもあの意識を持ち続けていたら、今のような政治にはなっていなかったと思います。
藤原 連合赤軍事件(注3)があって、運動の果てがあれか、というショックはありました。団塊世代はブレが激しいのが特徴ですが、まっとうにやっているんだという自分たちの美学もあった。それで社会に出ると、企業戦士になった。自分たち、あるいは社会が見えていなかったのでしょうか。権力への反発とか学生運動がある種のファッションで、血肉や確固たる思想にはなっていなかったのかもしれませんね。
高村 バブル経済のころ、企業が本業以外の財テクに走った。モノをつくらないでももうかるというのはおかしい、と企業戦士たちは問題意識を持ったはずなのに、異議を唱えることなく、それに乗ってしまった。下の世代から見て違和感がありました。団塊の世代だけを責めるわけではありませんが、人生の理想とか倫理とか、お金にならないことに意味を置いてこなかったし、子どもにもさせてこなかったのではと感じます。
藤原 責任は重いですね。最後に、団塊の世代への提言を。
高村 今が人生リセットのいい機会です。今こそ一人になって家族も会社も脇において、考えてみましょう。あと十数年、どう生きるか、若い世代が幸せになれるために何ができるか、を。そして少し楽になりましょう。もうメンツはいいでしょう。
==============
(注1)いくつかの定義があるが、政府の高齢社会白書は「1947~49年生まれの第一次ベビーブーム世代」としている。出生数は約805万人で、元経済企画庁長官で作家の堺屋太一氏が「団塊の世代」と名づけた。07年から順次、「60歳定年」を迎え、労働力不足や技術の継承など、産業社会へのさまざまな影響が予想されている。
(注2)戦後学生運動のピークを象徴する東大での闘争。68年、医学部の無期限スト以降激化し、東大全共闘を中心に展開された。69年1月、学生が占拠していた安田講堂で機動隊と激しい攻防となり、封鎖は解除された。
(注3)72年2月、連合赤軍のメンバー5人が長野県・軽井沢の浅間山荘に押し入り、管理人の妻を人質にして10日間ろう城。機動隊との銃撃戦で警察官ら3人を射殺した。逮捕後の供述で、71年12月以降、群馬県内の山岳アジトで「総括」と称して、仲間12人に暴行を加えるなどして死亡させ、遺体を山中に埋めたことが明らかになった。社会に大きな衝撃を与え、以後、学生運動は急速に力を失った。
==============
◇幕引きの時
団塊の世代が若い時代、「反乱の世代」とも呼ばれたのは、学生運動の印象が影響している。しかし、この世代の大学生の割合は、まだ25%にも達していなかった。大学進学率が急激に高まるのは、その後の世代だ。「金の卵」として中学校を卒業後、すぐに社会に出るケースも地方では少なからずあった。さまざまな人生の歩みを、安易にひとくくりにして語るのは控えなければならない。
とはいえ、この世代の人口は他の世代のそれより飛び抜けて多いことだけは間違いのないところだ。そして、国際的には冷戦とその崩壊、国内では高度経済成長とその挫折の中で生き、この数年間で一線を退いていく。「上手に生活を縮小してください」。すぐ下の世代に属する高村さんは、団塊の世代の「これからの生き方」に、こう注文をつけた。
数が多ければ、その分だけ社会に与える影響は大きい。競争しながら生き抜いてきた団塊の世代がどのようにして「上手に」幕引きをするか。次の世代に残すメッセージは何か。自らの課題として考え続けていきたい。【藤原健】(毎日新聞)
<with 藤原健・編集局長>
ベビーブーム、受験競争、学生運動に全共闘、高度経済成長、そしてリストラ……。団塊の世代(注1)を語る言葉を連ねるだけで、時代の断面が見えてくる。数の多さだけでなく、大きな存在感を示してきたその世代が、社会の一線から身を引き始めた。高齢社会の日本で、彼らはどう生きていくのか。高村さんは、後輩として団塊の世代にエールを送った。「メンツはもういい。自分の人生のためにエネルギーを使ってほしい」【構成・若菜英晴】
◇若い世代に道譲り、頑張らない働き方を
藤原健・編集局長 私(1950年生まれ)は団塊の世代と1年しか違わない。大学に入ると東大闘争(注2)をはじめ各大学では学生運動で盛り上がっていましたが、結局敗れて、70年安保を経て社会に入り、高度経済成長を担ったのが団塊の世代。そのちょっと下の世代になる高村さんからは、どのように映っていましたか。
高村薫さん 団塊の世代の人たちが学生運動を激しく展開していた時期、私は高校に入学した時でした。冷めた目で見ていました。何であんなに群れるのかな、と。
藤原 群れるというより人数そのものが多かった。学校は1クラス55人でした。その多さゆえに、常に社会的政策の対象となってきました。その人たちが定年退職を迎えつつあります。
高村 団塊の世代が定年を迎えて、その後も社会的存在でいられるのはせいぜい十数年。そば打ちだとか田舎暮らしだとかメディアはあおっていますが、そんな生活ができるのは一握りで、多くは年金をもらいながらも働かなくてはいけない。ローンが残っていたり、子どもがまだ独立していなかったり、自宅のリフォームもしなくちゃいけない。定年後は決して楽じゃない。そういうシビアな認識を持つことから始めないといけないと思います。
藤原 コマーシャルベースに乗った生き方をする人は少数です。
高村 そういう生き方を否定するつもりはありませんが、悠々自適とはいかない。働かなくちゃいけない。ただ、心の持ち方は変えてほしい。第一線という意識を捨てることです。働かねばならないが、譲っていく、つまり頑張らないということです。
人口減少社会の中で、若い世代と60歳以上の世代で仕事のすみ分けが必要だと思います。日雇いや派遣は60歳以上が担い、若い世代にはきちんとした給料取りになってもらうことです。若い世代が幸せになることは社会全体や団塊の世代のためでもあります。そのために何をしたらいいかを団塊世代の人たちは考えてほしい。
藤原 団塊世代には自分たちが社会を引っ張ってきたという自負心もありますが。
高村 社会の歯車、という思いはありませんでしたか。私にはそう見えて「つらい」と思っていましたが……。
これからは頑張らず、社会の一線に立たず、自分のためにエネルギーを使ってほしい。団塊の世代を気の毒と思うのは、一生懸命働いてそのお金を子どもに多く使ってきたこと。バリバリ稼いで消費する生活ではなく、残りの人生に向けて生活の縮小を考えてほしい。
藤原 人生のいい店じまいの仕方を考えようということですね。
高村 働かなければならないから隠とん生活というわけにはいきませんが、現役時代にはできなかった「ものを考え、人生の整理縮小を図る生活を送る」ことは精神の充実につながります。
藤原 そのような見本の人は、知人や友人におられますか。
高村 田舎に行けば、いつお迎えが来てもいいという心境に自分をもっていく人がいらっしゃいます。
◇今こそリセットのチャンス、一人で生き方考えよう
藤原 私の世代を含め、実は団塊の世代から総理大臣もノーベル賞受賞者も出ていないんですね。これだけ絶対数が多くて競争して勝ち残った人がいるはずなのに。アメリカにはさまざまな矛盾はありますが、クリントン前大統領のようなベビーブーム世代のリーダーが生まれている。
高村 激しい学生運動をして政治意識も高かったはずなのに、不思議ですね。社会人になってからもあの意識を持ち続けていたら、今のような政治にはなっていなかったと思います。
藤原 連合赤軍事件(注3)があって、運動の果てがあれか、というショックはありました。団塊世代はブレが激しいのが特徴ですが、まっとうにやっているんだという自分たちの美学もあった。それで社会に出ると、企業戦士になった。自分たち、あるいは社会が見えていなかったのでしょうか。権力への反発とか学生運動がある種のファッションで、血肉や確固たる思想にはなっていなかったのかもしれませんね。
高村 バブル経済のころ、企業が本業以外の財テクに走った。モノをつくらないでももうかるというのはおかしい、と企業戦士たちは問題意識を持ったはずなのに、異議を唱えることなく、それに乗ってしまった。下の世代から見て違和感がありました。団塊の世代だけを責めるわけではありませんが、人生の理想とか倫理とか、お金にならないことに意味を置いてこなかったし、子どもにもさせてこなかったのではと感じます。
藤原 責任は重いですね。最後に、団塊の世代への提言を。
高村 今が人生リセットのいい機会です。今こそ一人になって家族も会社も脇において、考えてみましょう。あと十数年、どう生きるか、若い世代が幸せになれるために何ができるか、を。そして少し楽になりましょう。もうメンツはいいでしょう。
==============
(注1)いくつかの定義があるが、政府の高齢社会白書は「1947~49年生まれの第一次ベビーブーム世代」としている。出生数は約805万人で、元経済企画庁長官で作家の堺屋太一氏が「団塊の世代」と名づけた。07年から順次、「60歳定年」を迎え、労働力不足や技術の継承など、産業社会へのさまざまな影響が予想されている。
(注2)戦後学生運動のピークを象徴する東大での闘争。68年、医学部の無期限スト以降激化し、東大全共闘を中心に展開された。69年1月、学生が占拠していた安田講堂で機動隊と激しい攻防となり、封鎖は解除された。
(注3)72年2月、連合赤軍のメンバー5人が長野県・軽井沢の浅間山荘に押し入り、管理人の妻を人質にして10日間ろう城。機動隊との銃撃戦で警察官ら3人を射殺した。逮捕後の供述で、71年12月以降、群馬県内の山岳アジトで「総括」と称して、仲間12人に暴行を加えるなどして死亡させ、遺体を山中に埋めたことが明らかになった。社会に大きな衝撃を与え、以後、学生運動は急速に力を失った。
==============
◇幕引きの時
団塊の世代が若い時代、「反乱の世代」とも呼ばれたのは、学生運動の印象が影響している。しかし、この世代の大学生の割合は、まだ25%にも達していなかった。大学進学率が急激に高まるのは、その後の世代だ。「金の卵」として中学校を卒業後、すぐに社会に出るケースも地方では少なからずあった。さまざまな人生の歩みを、安易にひとくくりにして語るのは控えなければならない。
とはいえ、この世代の人口は他の世代のそれより飛び抜けて多いことだけは間違いのないところだ。そして、国際的には冷戦とその崩壊、国内では高度経済成長とその挫折の中で生き、この数年間で一線を退いていく。「上手に生活を縮小してください」。すぐ下の世代に属する高村さんは、団塊の世代の「これからの生き方」に、こう注文をつけた。
数が多ければ、その分だけ社会に与える影響は大きい。競争しながら生き抜いてきた団塊の世代がどのようにして「上手に」幕引きをするか。次の世代に残すメッセージは何か。自らの課題として考え続けていきたい。【藤原健】(毎日新聞)






















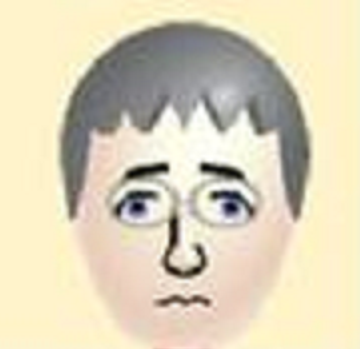





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます