
(日本経済新聞 春秋より抜粋)若者に人気の作家、乙一さんは地方に住んでいた駆け出し時代、打ち合わせで上京すると渋谷の漫画喫茶で夜を明かした。ビジネスホテルに泊まる余裕がなかったからだ。漫画喫茶はその後、ネットやビデオを備え複合カフェやネットカフェを名乗り始める。
▼1500円前後で仮眠を取れるこの種のカフェを定宿とする人は、厚労省の推計では5000人を超すという。なかでも多いのが20代と50代。不況の直撃を受けた団塊リストラ世代と、その子供らのフリーター世代に当たる。
▼13年前、東京の表参道に面しずらりイスを並べたパリ風喫茶が開店。見られる快感が女性に支持され喫茶店とはひと味違う「カフェ」ブームに火をつけた。2年後にスターバックスが上陸し、個人経営者による中古家具カフェ、画廊カフェ、足湯カフェ、うさぎカフェなどが登場。マクドナルドも昨日、自然志向のカフェを開いた。
▼家や職場から離れ自分を取り戻す「第3の場」を提供したのがカフェ人気の理由とされる。こうしたゆとり消費の陰で、同じカフェが「生存」のために利用されていた。今、カフェは世相を鮮やかに映し出す鏡。行くあてのない人々がたどりついた先がネットカフェだったのだろうか。
そうだな、小父さんも気がついたら、「ネット」で遊びながら「カフェ」を飲んでいた。10年前だったら、このような空間は、街にも、職場にも、家庭にもなかったんだ。小学校5年の頃、お金持ちの子が親に5万円の百科辞典を買ってもらったというので、家に行ったら、本棚付きのエンサイクロペディア・ブルタニカみたいな日本語百科が置いてあったので使わせてもらった。今、「ネット」をさわりながら、あれよりもコンパクトで便利なものが目の前にあるんだと、よく思い巡らしている。
10年以前だったら夜、「ネットカフェ」で過ごす人たちに、仕事はあったのかな。第一ネットも無ければ、携帯メールもない。きわめて限られた情報手段しかなかったわけだ。固定電話にポケットベルかな。携帯電話は出はじめで、限られた人だけしか使われていなかった。そうだ、まだ家庭に電話が普及してなかった小学校3年の頃、クラスの親類どうしの子が、学校帰りに片方の家に宿泊することを急に決めて、自分の家に、その連絡の為に電報を打っていたのを思い出した。
10年前だったら「漫画喫茶」以外だと「ファーストフード店」で一晩すごせていたのかな。「ファーストフード店」は複数の知人で過ごすとこだろうけど、「ネットカフェ」は個人の世界だろう。小父さんの10~20代は、友人か自分の家の布団の中が、ファーストフード店の役割を果たし、よく友人と朝まで話し込んでいたもんだ。
よし、午後晴れていたら、屋外のパリ風喫茶でも行ってみるか。






















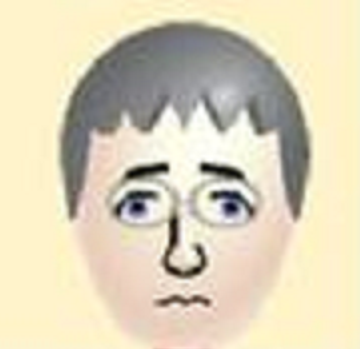





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます