論文IX 1.7 「技術圏」進化の普遍的法則はあるか?
本文~~~
1.7 「技術圏」進化の普遍的法則はあるか?
経済の分析は「技術圏」についてのもっとも原理的な設問をなげかける。
我々はさまざまな経験的な規制もしくは、すべての領域を越えて適用する法則さえも知悉していて、そしてそれらは「技術圏」進化を説明するために人間意思の意向とは独立に使うことができる。
我々はすでに沢山の規制と法則に近い仮説と推測を知っていて、これらは「技術圏」科学の中心に置くことができる。
筆者がすでに述べたところであるが、ネットワーク分析によって確立された仮説について述べたのである。そしてその仮説は、件の経験的ネットワークの然るべき構造的特性についての経験的同定のみを想定しているものである。
たとえば、われわれはべき乗則power lawsという解析ツールを手にしている(Newman, 2006; Gabaix, 2016)。
べき乗則はエコノミストによって最近まで無視されていたのである、この法則の中核なる意義が早くから確立しているような重要な分野があるにも関わらずである。たとえば経済地理学Economic Geographyのような特に都市の進化については確立していたのである(Krugman,1996)。
あきらかに、都市の集積体は「技術圏」の基本的な容姿であるので、都市化を統御しているべき乗則は「技術圏」科学での特定セットの仮説として出現するであろう。
都市集積体Urban agglomerationsもまた、ネットワークに規則性を適用するにもまた、経験的な参照となるのである、なぜなら、それは都市それ自体を「技術圏」として分析することからその規則性が確立してきたからである。
これらは、スケール問題としての経済学的概念に関係しており、べき乗則の別の表現、さらに具体的にいえばアロメトリックなべき乗則allometric scaling lawsで表現されるのである。
自然におけるスケーリングという次元からみて、知識の全体性The entire body of knowledgeには、「技術圏」の中核的構造として都市に焦点をあて、それを理解することは適切である(West,2017):
しかしながら、この研究ですでに述べたように、都市化もまた、超線形性super-linearityの特性の支配をうける明確な法則に従おうとする。ここでの超線形性は、都市技術によって支えられて、人間社会ネットワークの具体的な自己再入力動力学specific self-reinforcing dynamicsを参照している説明することができるのであり、そして、超線形性は「技術圏」および生物圏とは異なっている(Bettencourt, 2013; Alberti,2015)。
すべてこれらの一般化では、経験的な応用は、ネットワーク特性の正確な同定に拠っている。
しかしながら、われわれもまた、ある一般的な存在論的ontologicalな関わりつくり、そしてシステムの特性化をすることもできるのである。それは、そのシステムが「技術圏」においてであったり、あるいは、その技術自身においてである場合である。それらはシステムの形式において普遍的識別の区分できる場合である。
たとえば熱力学的な意味での、開放系と閉鎖系、あるいは動力学的意味での線形系と非線形系の区別化は、「技術圏」で作動する起因系プロセスの形式的特性であるが、これらは有効な特性としての識別差別化をもたらすのである。
筆者はつぎのことを論議したい;ある具体的なタイプのシステムに対して存在論的関与をするのに、ある抽象的な議論がそこにあるというものである。
この関与に立つならば、我々に直ちに迫りくるのは、交差的学際間的にそのタイプシステムとして共通に応用するために実際的な沢山の仮説を集めることである(Sciubba, 2011がこのアプローチを具体的に位置づけている)。
著者の関与はつぎである;「技術圏」は開放系、非線形的非‐平衡系open, non-linear nonequilibrium systemであるとして、そしてそこでの物性は生物圏と「技術圏」とで共有されていて、結果として、地球システム一般性に対して適用されるという立場である。
これは、これらシステムが熱力学的に開放系であるという単純な観測ベースによるのである。なぜならそれは、太陽エネルギーという外的な入力流external inflowsによって投与feedされて成り立つからである、そして、これは、非平衡系システムnon-equilibrium systemsであることを直接に説明することになるのである。(Kleidon, 2016)。
非‐線形性の仮定は納得のいくことではある、なぜなら、複雑なシステムは、通常沢山のフィードバック回路とこれらの性質の間での相互依存性を含んでいるからである。
これらの一般的な特性からは、さらに沢山の具体的な形式的仮説が推論され、ここでは特定のパラメータおよび起因因子について経験的にチェックをすることに至らしめるのである。
ここまでくると、もはや、筆者の存在論的考慮の範囲ではない。
しかしながら、つぎのことに留意しておくことは大切である、一般的様態容姿はまた、異なるサブシステムにも適用されるのである。
エコロジーシステムは、人間経済と同様に、これらの筋にそって記述されることが可能である、これはこれらの構成単位が部分的ながら重なっている(農業がその例である)
筆者の見解では、この基礎的存在論的特性fundamental ontological characterizationは単一ではあるが、沢山の基本理論の含意を持つのであるが、それは、しかしながら、直接経験的帰着性をもつというものである、それは進化理論の地位についての前段での帰着性との議論とむすびついているという前提のもとでのことである。
この設問は、我々が進化動力学dynamic of evolutionについてのさらなる基礎的な過程をつくるべきかにかかっている。
これは、物理学的原理の上に成り立つにちがいない、なぜならこれらは、生物学的システムと技術の双方に対して適用できるからである。
筆者は示唆するのであるが、これは、Lotkaの最大力原理Lotka's Maximum Power principle (Lotka 1922a, b)であることである。
Lotkaの原理は最大エントロピー原理と繋がっている。これは最近の地球システムの研究から言えることである(Kleidon, 2011; 最近の論文集としては, つぎを見よ Dewar et al., 2014).
このことは、「技術圏」科学がエコロジー経済学の知的原点と関係がある、名前をあげればGeorgescu-Roegen's(1971)のエントロピーと経済学に関する業績である。
筆者はつぎのことを主張したい;生物圏、技術という意味での「技術圏」そして経済をあわせた単一概念unifying conceptは「最大出力」‘maximum power’である。
その結論に至るひとつの道筋は、つぎのことを論議することであるべきである、つなわち、開放系、非‐線形的非‐平衡系のシステムopen, non-linear non-equilibrium systems、これが、最大エントロピー生産原理Maximum Entropy Production Principleを発生せしめるのである。そして、この最大原理は、より高い量のエントロピーをシステム環境system environmentへと貫流させる新たな状態に追従を起さしめる。このような構造変化の軌跡を現実化するということを意味している(Sciubba,2011)。
時間と適正なシステム境界を設定すること、そしてしかるべき制約条件を同定するidentifying the relevant constraintsにもかかわらず、それはエントロピー生産の最大化の傾向を反映していくであろう。
生命システムについていえば、Lotka最大出力原理Lotka's Maximum Power principleは中間的な起因機構intermediary causal mechanismを具体化するのである。この機構は構造パターン(organisms, demes etc.)を発生するための(生命システムによる)自然選択の傾向tendency of natural selectionを明かにしているが、ここでいう構造的パターンはエネルギー貫流を最大化する傾向をもつパターンである。 そしてこの貫流は、究極的には、利用レベルのひくいエネルギーへ転換していく、つまりエントロピー生産である。
流れシステムflow systemsのネットワーク動力学を解析することからひきだせる同様の結論がある(これは「構造的法則」the ‘Constructal Law’であり、 Bejan and Lorente, 2010, 2013が示唆している).
または、出力生産power productionについてのより一般的な考慮を生物圏での進化的力evolutionary forceに及ぼすこともできよう。
最大出力原理Maximum Power Principleはエコロジー経済学Ecological Economicsの文脈にも取り入れられている(Odum, 2008)。
筆者はこの論議が理論的にして、根源的でさえあるとみて、経験的な裏付けを待つものである。
つぎの二つの仮説のあいだには納得のいく区分けがある;ひとつの仮説はあるシステムがつねに最大生産の状態にあるというものと、もうひとつは連続的な変化や制約条件に変化を経て、そのシステムが最大生産の状態への移行することが不可能性ではないという状態想定をすると、システムがひとつの最大にむかう性向をもっているという状態にあるとする仮説である。
これは、「技術圏」に対してはとくに真理である、なぜならそれは、そのシステムが新しいものを連続的に出現する性向をしめすからである、たとえば新しいエネルギー源の利用性を増やしたり、あるいは新しい種類の情報を活性化してくれるような場合である。
このような原理の生物学的応用についての文献は多く、ここではその問題点とその挑戦を検討するのであり、十分に蓄積した経験の有効性が基本理論を冒すことなく、すすむのである(for example,Dewar, 2010 or Vallino, 2010)。その基本原理もまたその状況の文脈では意味を示すのである。
かくして、ひとつのシステムとして「技術圏」の一般存在論的な特性化general ontological characterizationに立って、筆者は概念を一歩すすめるのである;それは、「技術圏」の進化は、観察からの性向としても、動力学としても最大出力と最大エントロピー生産Maximum Power and Maximum Entropy Productionに向かわしめるという推測である。
このことは「技術圏」での経済の役割わりを理解するための重要な含意をもつ、なぜならそれはつぎのことを含むからである、すなわち、その経済は、連続的に拡張する出力貫流現象へむかう性向もつからである。(経済は)つまりエネルギー流である。
このことは、同時につぎのことの理由を説明するものである、つまりGDP成長の意味において経済は成長する、しかし、たしかに物質‐エネルギー貫流の成長という意味でも経済は成長し(これはたとえば、人口増大もまた経済成長の一形式であるという意味である)、そしてさらに構造体化structural embodimentsの成長 (経済用語での「資本形成」‘capital formation’ )の意味でも、経済は成長するのである(Ayres and Warr, 2009; Kümmel, 2013; Herrmann-Pillath,2014)。
事実、人間文化と経済進化でのこのふたつの移行は、過激にして包括的なブレークスルーに明確に立ち帰るものである。このブレークスルーとはエネルギー貫流を動態化し、新石器時代で農業移行し、産業革命および炭素経済の動態化であった。
エネルギーに関する初期での視点は、文化圏cultural sphereを含む人間文明の中核的な様態容姿であるとしたのであったが、このことの正統を告げているのである。(Bataille, 1949/2014; White, 1949/ 2005)。
事実、我々もまた、現代社会の世俗的な「加速化」‘acceleration’について最近の社会学での理論化のために、膨張するエネルギー貫流の概念を参照することができよう(Rosa, 2010)。
このことは経済の文脈においてさえ、人間中心主義からの撤退として、つきつめておくべきことがある、それは経済成長が経済的欲望を満たすポテンシャル確保機能をもつものではなく、これは第一義的に最大出力に向かわせるものであるということについてである。
完全な議論としてはつぎのことを証明しなければならないであろう、それはその経済の機構(たとえば、競争や、制度形式an institutional formの資本主義への移行)が最大出力原理を実現するポテンシャルを確保することの証明である(Herrmann-Pillath, 2013; Haff, 2014c)。
経験的事例化を知るうえでの信頼できる交流の現場venuesは沢山ある:筆者はまさに、「リバウンド効果」rebound effectsについての内容のある研究に触れておきたい、これはJevonの「石炭問題」‘coal question’において顕著にみられるのである。この問題はさまざまな起因のチャンネルを通じて顕われるが、くわしくは如何にして、人間経済行動がエネルギー節約に向ったか、そして増大したエネルギー効率がエネルギー貫流の絶えざる成長事実をもたらしたか、かくして、最大出力原理Maximum Power principleが人間の意思決定の有無にかかわらず発動したかを顕わすのである(調査については Sorrell, 2009 or Azevedo, 2014を見よ)。
この事実が、人間個人水準でこれら起因連鎖に貢献することに関して社会および心理学的機構への豊富な考察をもたらしている(概観はSorrell, 2015を見よ)。
「技術圏」についての筆者は基礎的な存在論的様態容姿の取り扱ってきたが、最後の段階としては、情報と最大出力原理との間の関係relationship between energy and informationが残る、すでに述べたようにエネルギーと情報との間の関係は、自律機関autonomous agentの概念と「しごと」workの概念に包含されるものである。
事実、経済成長のエネルギー理論は、エネルギーそれ自体に焦点が合わせられることは少なくて、有効仕事の発生に合わせることが多い。これは最大出力の理念に近接しているものである(Ayres and Warr, 2009)。
かくして、我々は別の一般的仮説を言明することになる、すなわち「技術圏」は、起因となエネルギー流的貫流があって、それと結合して得られた内容をもつ情報の蓄積に向かって進むという仮説である。
巨大歴史研究は「技術圏」科学のひとつの重要な部分である、なぜなら、それは、進化の性向にひかりを当てることを目しているからである。これによって人間文化から生命に至り、さらに宇宙的進化をも含んでの相互の存在論的領域を橋渡しすることになるからである(Aunger, 2007)。
それは地球システムでのエネルギー移動に関する現在の研究と結びつくのである(e.g. Judson, 2017)。
ひとつの中心的な指標として、「自由エネルギー流密度」‘free energy rate density’がある、これは単位時空間あたりのエネルギー貫流を測るものである(Chaisson, 2001, 2015)。
最高密度をもつ実体は、その情報プロセスに対しての最高情報複雑性と最高容量をもつ実体である。
これは事実ということについての最も密度のたかい表現である、それは、一般進化において、エネルギー流と情報流は物理学的にも、したがって現象論的にも関係している事実なのである。
より深い物理学的なベースとしてはランダウアー原理Landauer's principleに帰着するかもしれない、そこでは情報プロセスの熱力学的コストを定量化しているのである(Faist et al., 2015)。
筆者が他の場所(Herrmann-Pillath, 2014, 2016),でも論じてきたが、この存在論的提案ontological propositionは経済と「技術圏」との間の相互作用の分析を多く含意するものであるが、とくに未来において、情報技術は経済の中核的な材料となり、そしてインフラストラクチュアの要素となろう。
ITCがエネルギー貫流と経済成長を結合かい離decoupleすることを援けるという多くの視点が出されているが、そこでは「技術圏」科学は成長、デジタル化およびエネルギー流の間でのつよいリバウンド効果rebound effectsが予想されよう。
別な重要な帰着としては出力密度(単位空間あたりのエネルギー貫流)は人間エネルギーシステムにアプローチするものである。この密度はその「技術圏」の構造的進化に対する重要な制約条件を顕わにするのである。特に継続的な都市化の文脈での構造進化がそれである(Smil, 2015)。












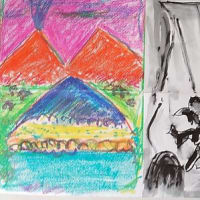













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます