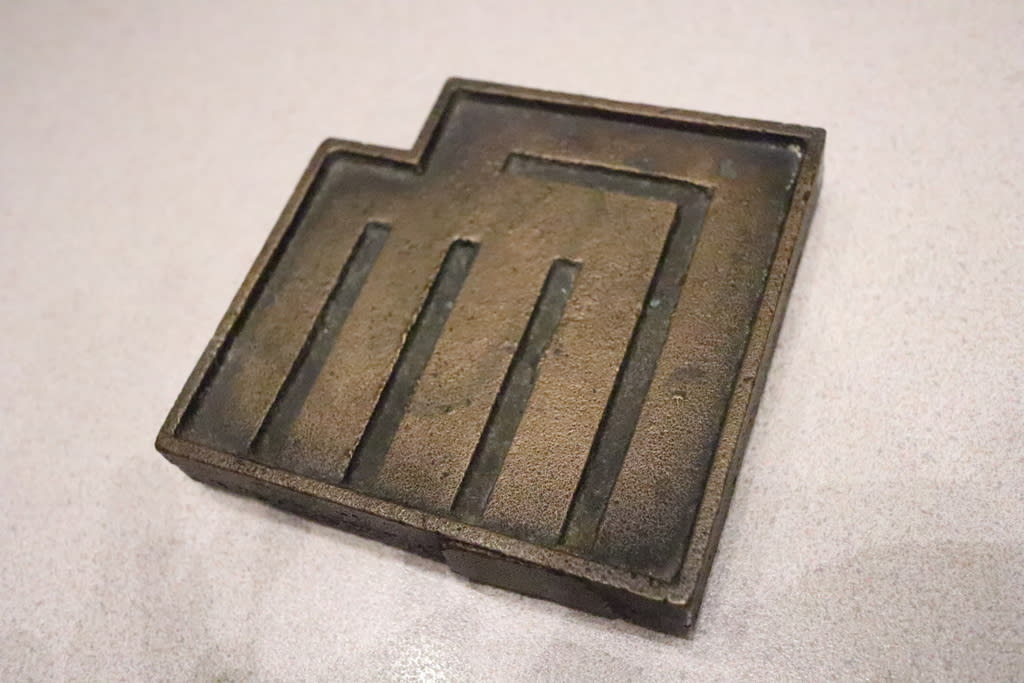今回の椀物(汁物)には「ゆばしんじょ」が入っていました。しんじょもすべて一律の食感の練物にするのではなく、時々コリッとした食感が味わえる仕立てでした。
練物も自分で作る料理長の技は素晴らしいですね。機械でない手造りだからこそ、練物にも陰影が生まれるんです。それが「技」というもんだと思います。
さて、早松(さまつ)。近年、マツタケが獲れなくなって絶滅危惧種2類に指定されるとか。今日のお椀には「早松茸」=「早松」が入っていました。とはいえサマツは松茸ではありません。モミタケというそうです。モミの木の林にできるようですね。松茸に似ているけど、全く違うものだそうです。香りもありません。料理長の技で樅茸も松茸風にに大化けです。
食材にランクをつけないで楽しみましょうね。
美味しければいいよね~。。。。。