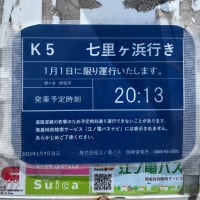江ノ電の電車が江ノ島駅を発車して専用軌道から人車が行き交う一般道に入るところ、腰越の龍口寺門前の急カーブをレールをきしませながら通過して行く。
その急カーブに面して相模湾で獲れた魚を干した干物を売る大きな店があって、デパートの地下にも出店していた。
アジやサバ、カマス、キンメダイなどが人気で、たまにカマスなどを買って食べて脂の乗り具合などに感心させられたものだ。
しかし、何といってもこの店の"目玉"は知る人ぞ知るメザシの干物だった。
小振りのイワシが5匹、目に竹串を通され藁で結わえられたイカダ状で売られていて、これが美味中の美味と言ってよく、大好物だった。
カチンカチンに水気が無くなるまで干したものではなく、まだ半乾きのような状態で売られていたから冷蔵庫モノなのだが、こいつをよく炙って小皿に注いだオリーブオイルにチョンと浸して食べると、口中にあの独特の苦みを伴った栄養価たっぷりの脂がにじんで絶品だった。
食中酒はもちろん、良く冷やした白ワイン♪
ワイン一本はあっという間に空になっていった。
ところが、コロナ禍の数年前、突如このメザシが店頭から消えてしまう。
ワケを聞くと「小イワシが獲れなくなった」のが理由だった。
振り返ってみれば同時期、シラス漁の不漁も続いていたから黒潮の大蛇行などもあって、そうした影響を受けたのかもしれなかった。
なかなか復活しないなぁ…と思っているうちに、半乾きではなく、硬めのものが登場したが、相模湾産ではなく、どこか他所の海で獲れたものを産地で干したものだった。
それでも久しぶりなので買って食べてみたが、まったくの別物で、そもそもが塩が効き過ぎていて、あんなものを食べ続けたら病気になってしまいそうなくらい、塩辛かった。
その後、コロナ禍を経て店自体もたたんでしまったのには驚いたし、あのメザシにはもう出会えないと思うと寂しさが募るばかりである。
小振りなのが良かったし、ハラワタの程よい苦みも"口福"をもたらしてくれた。なにより、塩が薄かったのもイワシ本来のうまみを引きたてていて、絶妙だったのに…
どこかで再びあのメザシに出会えないものか。
木がらしや目刺にのこる海のいろ 芥川龍之介
以下は、横浜イングリッシュガーデンの秋バラ その4