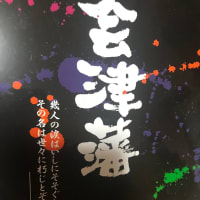日新館は
藩祖、保科正之の朱子学から思想対立を経て儒教に変わっています。
駐車場から館の門まで歩きます。
中国色が濃く感じられました。

全体的に質素な風情がいかにも学舎風
登り中断ぐらいの場所に什の掟
今の時代、この掟を見たら、反発を喰らいそうです。
「ならぬことはならぬものです」言い訳無用の厳しい掟、、。




一見お寺?と、勘違いしそうです。

四方にぐるりと教室、稽古場

中には日本初めてのプールも、。
保科正之は家訓、15か条を制定しています。
15か条、第一条には将軍家へ忠勤であり、これを破ったものは子孫に非ず、と言う厳しいものです。
保科正之は将軍家への献身的な忠勤は幕閣の人も熟知していたにも関わらず、何故わざわざ明文化したのでしょうか?
因みに15か条には、「兄を敬い弟を愛すべし」「婦人女子の言、一切聞くべからず」「法を犯すものは宥す(ゆるす)べからず」と有ります。
それは保科正之の生まれた経緯や、藩主として置かれた環境が、権力欲、妬みや誹謗中傷など貶めるための策略を見て、その処世観から自分の死後の子孫を気遣われてのことでは無いか、と、この幕末会津藩の筆者の解説として述べられています。
孔子は紀元前6世紀の思想家、哲学家で有りその教えは儒教として伝わっています。
中国はその広さから、権力争い、支配争いの歴史を繰り返しておりその争いの中で
時の権力者が儒教の教えを取り入れ、
忠臣、忠孝の教えを君主制に活かして来たと思われます。
時の為政者が民の幸せを中心として世を治めるのか、自分の権力維持を中心に世を治めるのか、はたまた愚者か賢者か、その人となりは、官民の幸不幸に大きく影響します。
同族を重んじる儒教では、一族の誰かが殺されれば、報復は当然とされ相手の一族を皆殺し、死刑には三族皆殺しがあったといいます。
覇権争いで権力を持てば政敵であった者の身内、家来に至るまで粛清する、ということがその世界の常として繰り返されました。
また、上下の秩序を重んじており、それが上のものには媚び、下のものには傲慢に接すると言う差別意識も生まれ易く、
長幼の序により後継者争いも起こったりと実践にあたっては様々な問題が生じることとなります。
日本では明治維新事に朱子学と儒学は大きな影響を与えています。
日新館の一番最初の教室に大きな掲額に「忠臣」とあります。
日新館の設立は各藩の藩校設立(前身稽古堂、郭内講所ー1674年)となって広がって封建制度の武士の世界に大きな影響を与えています。
白虎隊はこの儒学、朱子学の思想が大きかったものと思います。
13、14歳から忠臣、忠孝、長幼の序を学べば、
藩主に忠義を尽くす、自刃は当然の選択だったのです。
白虎隊の自刃が
世間一般的にはお城の落城(実は落城と勘違い)に絶望して、、
と解釈されていますが、後に、それもごく最近、白虎隊生き残り
飯沼貞吉がその時の様子を書き残していたものが発見され、
真実が明らかになってきています。
朝敵の汚名を着せられ、誤解されて解釈されてきた会津藩士の
その無念さ、悔しさ、その執着の苦しみから解放される本当の慰霊に至るまで、
そして、
恩讐を超えた和解に至るにはまだまだ時間が必要に思います。
6/30