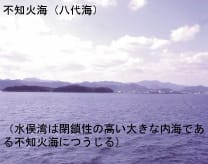
「地域居住学Ⅱ」の講義で「明日香の棚田周辺空間整備、水俣病患者から学ぶ」といったテーマで話した。明日香で都市住民が「多数」棚田管理に参加すると、周辺の空間整備が必要となる。都市住民の行動をシュミレート(跡付け)すると、自動車で大体はやってくる、田植え作業等するため着替えする、作業中トイレに行きたくなることもある、終って皆で交流する等がある。すると、駐車空間、着替え空間、トイレ、集会空間をどう整備するかが問題となろう。それは、都市でのそれらと違うように計画・整備されなくてはならない。
次に水俣病患者の住宅改善について取り組んだ事例を話した。水俣北の芦北町赤崎の佐々木つた子さんの住宅改善だ。沢山、つた子さんから学んだが主に三つあると話した。(1)不知火海が見えるようにして欲しい・・・それは自然との「つながり」を考えろ、ということだ。(2)父親や自分が働いたり遊んだりしていた赤崎港が見えるようにして欲しい・・・歴史との「つながり」を、ということだ。(3)近所の人や昔の友達と話せるようにして欲しい・・・人々との「つながり」を、ということ。私のその後の「つながりの豊かな地域居住」という考え方の原点の一つである。(写真は、綺麗な水俣湾に続く不知火海)
次に水俣病患者の住宅改善について取り組んだ事例を話した。水俣北の芦北町赤崎の佐々木つた子さんの住宅改善だ。沢山、つた子さんから学んだが主に三つあると話した。(1)不知火海が見えるようにして欲しい・・・それは自然との「つながり」を考えろ、ということだ。(2)父親や自分が働いたり遊んだりしていた赤崎港が見えるようにして欲しい・・・歴史との「つながり」を、ということだ。(3)近所の人や昔の友達と話せるようにして欲しい・・・人々との「つながり」を、ということ。私のその後の「つながりの豊かな地域居住」という考え方の原点の一つである。(写真は、綺麗な水俣湾に続く不知火海)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます