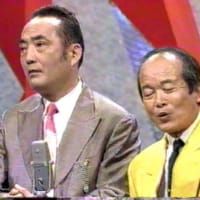来年は「浄土宗開宗850年」を迎えるそうです。(^。^)
浄土宗といえば、平安時代末期、「末法思想」が広がった世の中において、「法然上人」が「専修念仏」(せんじゅねんぶつ)の道を見出して開いた、新たな仏教宗派でしたね。(^-^)
専修念仏とは、「南無阿弥陀仏」と一心に称えることにより、時間の長短に関わらず、貧富や男女の別なく、すべての人が等しく救われるという道のこと。(^_^)
しかも、心で念じるのではなく、声に出して称えることで、常に仏様に見守っていただきながら日常生活を送ることができると説いたことから、広く大衆に広がったとされています。(^。^)
京都洛中では、法然上人ゆかりの寺院が数多くあり、総本山は「華頂山・知恩院」、その他、百万遍知恩寺などがありますが、特に、上人の名を冠した東山の「法然院」は、山中に淑やかに建つ、味わい深い佇まいです。(^-^)
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
浄土宗開宗850年キャッチコピーは、「お念佛からはじまる幸せ」。(^_^)
これは、ただ単に「幸せ」を追求するのではなく、本当の「幸せ」とは何かを考えなおすためのフレーズだそうです。(^。^)
欲求が満たされることだけが「幸せ」ではなく、「仏法僧の三宝」の「明るく、正しく、なかよく」生きる生活の中に、「幸せ」の本質があると説かれています。(^-^)
今朝の朝刊に、総本山・知恩院において、浄土門主伊藤唯眞猊下、浄土宗宗務総長川中光敎師、さだまさし氏によって行われた「鼎談」(ていだん)の特集記事がありました。(^。^)
実は、さだまさし氏は、法然上人800年大遠忌(2011年)記念の際に、「法然共生(ともいき)イメージソング」として、『いのちの理由』を作成されていた、とのこと。(^-^)
今回の鼎談において、さだまさし氏は、このようにコメントされていました。
「何のために生まれてきたのか」と悩んだ時期がありましたが、幸福って身近なところにあって、実は持ち歩いているんですよね。
みんな幸せになれるよっていう法然上人のまっすぐな教えが、宗教を超えてどんな人にも伝わるようにとつくりましたが、その思いを最も強くしたのが東日本大震災の時でした。
津波被害があった港町を歌い歩いていた時、どの町でも一番喜ばれたのが、この歌だったんです。「悲しみの海の向こうから喜びが満ちてくる」という詞があるので避けていましたが、リクエストしてくれる方が多くて。
身近で支えてきてくれた海を心から愛していたんですね。
その時、何か大きなところから頂戴した歌なんだなとしみじみ感じました。
10年、20年後も口ずさんでもらえる歌にという依頼をいただいていたので、多くの歌手がカバーしてくれるなど、反響の広がりにホッとしています。大切に歌い継いでいきたいと思っています。
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
依頼主である浄土宗の最高幹部も、「イメージソングというとアピールしたい固有名詞を繰り返す歌が多いかと思いますが、この歌には関連する言葉は何もでてこない。でも、聞くだけで浄土宗の世界、法然上人の教えが想像できる。どうして生まれてきたのかという問いの向こうに、いろんな人が喜んだり、悲しんだりする景色が浮かんできて、さださんにお願いして本当に良かったと思いました。」と述懐されていました。(^_^)
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
すでに十年以上前の曲ですが、あらためて、さださんの「いのちの理由」を聴いてみました。(^。^)
しみじみと胸に沁み込んで来る曲です。決して難しいことを説いているのでもなく、奇を衒った旋律でもない。けれど、このようにシンプルな歌詞とメロディーで万人の心に響く歌を作ることが一番難しいと実感した次第です。m(__)m
「いのちの理由」 さだまさし
◼️YouTubeはこちら↓
浄土宗といえば、平安時代末期、「末法思想」が広がった世の中において、「法然上人」が「専修念仏」(せんじゅねんぶつ)の道を見出して開いた、新たな仏教宗派でしたね。(^-^)
専修念仏とは、「南無阿弥陀仏」と一心に称えることにより、時間の長短に関わらず、貧富や男女の別なく、すべての人が等しく救われるという道のこと。(^_^)
しかも、心で念じるのではなく、声に出して称えることで、常に仏様に見守っていただきながら日常生活を送ることができると説いたことから、広く大衆に広がったとされています。(^。^)
京都洛中では、法然上人ゆかりの寺院が数多くあり、総本山は「華頂山・知恩院」、その他、百万遍知恩寺などがありますが、特に、上人の名を冠した東山の「法然院」は、山中に淑やかに建つ、味わい深い佇まいです。(^-^)
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
浄土宗開宗850年キャッチコピーは、「お念佛からはじまる幸せ」。(^_^)
これは、ただ単に「幸せ」を追求するのではなく、本当の「幸せ」とは何かを考えなおすためのフレーズだそうです。(^。^)
欲求が満たされることだけが「幸せ」ではなく、「仏法僧の三宝」の「明るく、正しく、なかよく」生きる生活の中に、「幸せ」の本質があると説かれています。(^-^)
今朝の朝刊に、総本山・知恩院において、浄土門主伊藤唯眞猊下、浄土宗宗務総長川中光敎師、さだまさし氏によって行われた「鼎談」(ていだん)の特集記事がありました。(^。^)
実は、さだまさし氏は、法然上人800年大遠忌(2011年)記念の際に、「法然共生(ともいき)イメージソング」として、『いのちの理由』を作成されていた、とのこと。(^-^)
今回の鼎談において、さだまさし氏は、このようにコメントされていました。
「何のために生まれてきたのか」と悩んだ時期がありましたが、幸福って身近なところにあって、実は持ち歩いているんですよね。
みんな幸せになれるよっていう法然上人のまっすぐな教えが、宗教を超えてどんな人にも伝わるようにとつくりましたが、その思いを最も強くしたのが東日本大震災の時でした。
津波被害があった港町を歌い歩いていた時、どの町でも一番喜ばれたのが、この歌だったんです。「悲しみの海の向こうから喜びが満ちてくる」という詞があるので避けていましたが、リクエストしてくれる方が多くて。
身近で支えてきてくれた海を心から愛していたんですね。
その時、何か大きなところから頂戴した歌なんだなとしみじみ感じました。
10年、20年後も口ずさんでもらえる歌にという依頼をいただいていたので、多くの歌手がカバーしてくれるなど、反響の広がりにホッとしています。大切に歌い継いでいきたいと思っています。
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
依頼主である浄土宗の最高幹部も、「イメージソングというとアピールしたい固有名詞を繰り返す歌が多いかと思いますが、この歌には関連する言葉は何もでてこない。でも、聞くだけで浄土宗の世界、法然上人の教えが想像できる。どうして生まれてきたのかという問いの向こうに、いろんな人が喜んだり、悲しんだりする景色が浮かんできて、さださんにお願いして本当に良かったと思いました。」と述懐されていました。(^_^)
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
すでに十年以上前の曲ですが、あらためて、さださんの「いのちの理由」を聴いてみました。(^。^)
しみじみと胸に沁み込んで来る曲です。決して難しいことを説いているのでもなく、奇を衒った旋律でもない。けれど、このようにシンプルな歌詞とメロディーで万人の心に響く歌を作ることが一番難しいと実感した次第です。m(__)m
「いのちの理由」 さだまさし
◼️YouTubeはこちら↓
父と母とに出会うため
私が生まれてきた訳は
きょうだいたちに出会うため
私が生まれて来た訳は
友達みんなに出会うため
私が生まれて来た訳は
愛しいあなたに出会うため
春来れば花自ずから咲くように
秋来れば葉は自ずから散るように
しあわせになるために
誰もが生まれて来たんだよ
悲しみの花の後からは
喜びの実が実るように
私が生まれてきた訳は
私が生まれて来た訳は
友達みんなに出会うため
私が生まれて来た訳は
愛しいあなたに出会うため
春来れば花自ずから咲くように
秋来れば葉は自ずから散るように
しあわせになるために
誰もが生まれて来たんだよ
悲しみの花の後からは
喜びの実が実るように
私が生まれてきた訳は
何処かの誰かを傷つけて
私が生まれてきた訳は
何処かの誰かに傷ついて
私が生まれてきた訳は
何処かの誰かに救われて
私が生まれてきた訳は
何処かの誰かを救うため
しあわせになるために
しあわせになるために
誰もが生きているんだよ
悲しみの海の向こうから
喜びが満ちて来るように
私が生まれてきた訳は
私が生まれてきた訳は
愛しいあなたに出会うため
私が生まれてきた訳は
愛しいあなたを護るため
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
「月欠けて夜長四方山話かな」 祖谷馬関
(注)夜長は秋の季語。秋の夜の長いことをいう。秋分が過ぎると、昼よりも夜が長くなり気分的にも、夜の長さが身にしみる。残暑もなくなり、夜業や読書にも身が入る。四方山話(よもやまばなし)は、特定の話題について話すのではなく話題が二転三転する状況の世間話のこと。
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
「月欠けて夜長四方山話かな」 祖谷馬関
(注)夜長は秋の季語。秋の夜の長いことをいう。秋分が過ぎると、昼よりも夜が長くなり気分的にも、夜の長さが身にしみる。残暑もなくなり、夜業や読書にも身が入る。四方山話(よもやまばなし)は、特定の話題について話すのではなく話題が二転三転する状況の世間話のこと。