
こんにちわ。中川かすみです。今回は、子どもたちが子どもの権利について学んでいる様子について、プノンペンから車で30分程度離れたところにある中学校の活動を通じて紹介します。国際子ども権利センターは、同学校における子どもの権利普及活動に技術面でも資金面でも支援しています。
まず最初に、今回活動を紹介する中学校は、ジャヤバルマン7世中学校という名前です。ジャヤバルマン7世は、カンボジア人であれば必ず知っている歴史上の王様です。この王様は、15世紀にカンボジアを統治したアンコール王朝時代におけるもっとも有名な王様です。ユネスコの世界遺産であるアンコールワット遺跡群の建設、その中でも特にアンコールワットおよびバイヨン寺院の建設に全力を注いだ王様です。ちなみに、現在でも「理想的な妻」として頻繁に引き合いに出される女性はインドラデービーであり、ジャヤバルマン7世の妻(王妃)です。わたしが大学の講義で学生に「もっとも尊敬されていて理想的なカンボジア女性は?」と質問すると、必ず最初に名前が挙がる女性です(近現代で理想的な女性はいない様子)。その有名な王様の名前を持つ学校は、カンボジア全土で最初に「子どもクラブ」(子どもの権利を普及するための子どもの活動推進母体)がCRF(子ども権利基金 国際子ども権利センターのパートナー団体)の支援によって設立された学校です。偶然かもしれませんが、学校の哲学を示しているような印象を受けます。3000人以上の生徒を抱えるマンモス校です。
さて、4月30日に、同学校で子どもの権利について学んでいる様子を国際子ども権利センターのスタッフ(甲斐田さんと近藤さん)がモニタリングするのを一緒に見学しましたので、少し紹介します。この日は、中学生たちが子どもの権利条約の重要な原則について先生から学んだ後で、3つのケースを使って具体的に「子どもの最善の利益」という原則に従って、子どもの権利を守る方法についてグループワークをしながら勉強しました。1番目のケースは、「両親が離婚する場合、子どもはどちらと生活すればいいか。母親が裕福で父親が貧しいという設定で、家庭内暴力のない家庭」です。2番目は、「父親が子どもに対して暴力を振るっている家庭で生活する子どもは、誰と生活するのがいいか。母親が父親の暴力をとめることができない」という設定です。3番目は、「母親が娘を買春宿に売ってしまい、警察がその娘を救出したあと、その娘は誰と生活するのがいいか」。3つのケーススタディーすべてにおいて、子どもたちは「もし自分が裁判官だったらどう判断するか」を念頭において話し合いました。
印象的だったのは、話し合いの中で「子どもの最善の利益」について、常に考える子どもたちの姿勢でした。「NGOの施設に行くより、家庭に戻ったほうが温かい環境で生活できると思う。でもそのためにはお父さん(あるいはお母さん)に約束事をしてもらって、子どもが苦しまないようにしないといけない」、「子どもが毎日学校に通えるように、文房具を買うお金を与えるよう約束させる」、「子どもが間違った行為をしても、暴力を振るわずに優しい言葉で指導するように約束させる」など、具体的に解決法を探していました。
「もし自分だったらどうしてほしいか」、ということを多分きっと念頭に置きつつ、子どもの権利を守る具体策について子どもたち自身が考えるという学習方法は、とても効果的だと思いました。ケーススタディーの内容も、「もしかしたら自分が直面するかもしれない」と思えるような具体的かつわかりやすいケースを選んであり、とても適切なものでした。このようなやり方だと、「子どもの最善の利益」というちょっとわかりにくい原則も子どもたちが理解しやすいのではないでしょうか。けれども、こういった学習方法を取り入れている学校は、まだそれほど多くありません。今後、より多くの学校において、多くの生徒が子どもの権利について積極的にかつ楽しく学んでほしいと思いました。
少女たちをエンパワーするために
http://jicrc/pc/member/index.html



















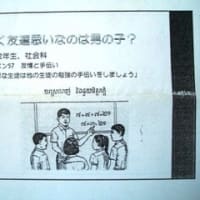
実際の裁判では、「こどもの最善の利益」は
判決に考慮・取り入れられているのでしょうか?
子どもと保護者が一緒に権利を学ぶ機会もあるのですか?