ひと 重松 清さん
山本周五郎賞に決まった作家
「受賞作」のタイトル「エイジ」には、
時代という意味が込められている。
14歳の少年による通り魔事件ではなく、その事件に
揺れる「ふつう」の少年エイジ君が、主人公だ。
新聞連載中は、中、高校生から
「僕らのことが描かれている」という共感の手紙が相次いだ。
「彼らが、もやもやと感じていて、言葉にできていない気分を
表現したつもりです。」
選考委員の作家山田太一氏は
「気持ちのいい鮮やかなヒット。少年への身の寄せ方が
うまいし、楽しい。」
と評した。
いじめを扱った「ナイフ」
ニュータウンでの定年後の生活を描いた「定年ゴジラ」でも、
重松さんの物語の主役は、時代の空気だった。
執筆では「私」を限りなく、抑える。
連載時にも「エイジ」のゴーストライターのつもりで」と語っていた。
フリーライターとして、女優から社長まで様々なゴーストを
こなしてきた。
「早稲田文学」の編集長だったとき、酔いつぶれた作家の
故中上健次氏を背負い、送っていったことがある。
中上氏に比べて、自分は「何もなかった世代」だと痛感し、
「私」を抑えるスタイルをとるようになった。
作家として9冊の著者がある今も
「現役のフリーライター」と言ってのける。
ペンネームを使い分け、単行本は100冊、雑誌原稿3000本という
仕事をこなしてきた。
インタビューなどの仕事は、時代を感じ取るアンテナになっている。
「事件とは、水が沸点に達して気化した現象です。
ライターとしては、水蒸気を追うが、作家としては、
じわじわと沸点に近づいていくまでの水の動きに関心があります。」
今も残る大衆小説を書き続けた山本周五郎は、目標のひとり。
「何もなかった世代」から、
大きな物語への突破口が見えてきた。
(朝日新聞 1999年5月14日付 ひとより抜粋)
私が、重松さんを知ることになったのは、
「きみの友だち」という作品からだ。
時間を忘れて、ページをめくることが楽しくもあり、
クライマックスにむかうことで、
この作品が、終わってしまう寂しさもあった。
重松さんの書いた作品を読むたびに、
心に残る一言を小説から、自分に送られているような気がする。
先日も、Amazonを使って、
重松さんがエッセイを書いた
「セカンドライン エッセイ100連発」を注文し、
今日の午前にメール便で届いた。
最初の1本目のエッセイで、重松さんはこのようなことを
述べている。
小数や分数を学ぶ以前の、割り算の初歩中の初歩
「7割る3は、2余り1」
僕の書いたお話には、必ず「余り」がついてしまう。
お話の表面に置いた出来事には、とりあえずケリがついても
根本的な問題は、残ったまま、という構図ばかりだ。
きれいに割り切れて、答えの出るお話はなかなか書けないし、
たぶん書こうともしていないのだろう。
「余り」つきの居心地の悪さにこそ、
いまの時代を生きるリアリティがあると思うから・・・
なんていうと、かっこつけすぎだけど。
(セカンドライン 1より抜粋)
余り・・・・・何をやるにしても、私たちの生活には、
この余りがついてくる気がする。
嬉しさの余りもあれば、悔しさの余りもある。
やりきれない思いが、余りとなって
次の計算(行動)の際に、
きれいに割れることを願って足されるのかもしれない。
「余り」つきのお話
書店に行って、重松さんの作品を探してみるのも
良いかもしれません。
山本周五郎賞に決まった作家
「受賞作」のタイトル「エイジ」には、
時代という意味が込められている。
14歳の少年による通り魔事件ではなく、その事件に
揺れる「ふつう」の少年エイジ君が、主人公だ。
新聞連載中は、中、高校生から
「僕らのことが描かれている」という共感の手紙が相次いだ。
「彼らが、もやもやと感じていて、言葉にできていない気分を
表現したつもりです。」
選考委員の作家山田太一氏は
「気持ちのいい鮮やかなヒット。少年への身の寄せ方が
うまいし、楽しい。」
と評した。
いじめを扱った「ナイフ」
ニュータウンでの定年後の生活を描いた「定年ゴジラ」でも、
重松さんの物語の主役は、時代の空気だった。
執筆では「私」を限りなく、抑える。
連載時にも「エイジ」のゴーストライターのつもりで」と語っていた。
フリーライターとして、女優から社長まで様々なゴーストを
こなしてきた。
「早稲田文学」の編集長だったとき、酔いつぶれた作家の
故中上健次氏を背負い、送っていったことがある。
中上氏に比べて、自分は「何もなかった世代」だと痛感し、
「私」を抑えるスタイルをとるようになった。
作家として9冊の著者がある今も
「現役のフリーライター」と言ってのける。
ペンネームを使い分け、単行本は100冊、雑誌原稿3000本という
仕事をこなしてきた。
インタビューなどの仕事は、時代を感じ取るアンテナになっている。
「事件とは、水が沸点に達して気化した現象です。
ライターとしては、水蒸気を追うが、作家としては、
じわじわと沸点に近づいていくまでの水の動きに関心があります。」
今も残る大衆小説を書き続けた山本周五郎は、目標のひとり。
「何もなかった世代」から、
大きな物語への突破口が見えてきた。
(朝日新聞 1999年5月14日付 ひとより抜粋)
私が、重松さんを知ることになったのは、
「きみの友だち」という作品からだ。
時間を忘れて、ページをめくることが楽しくもあり、
クライマックスにむかうことで、
この作品が、終わってしまう寂しさもあった。
重松さんの書いた作品を読むたびに、
心に残る一言を小説から、自分に送られているような気がする。
先日も、Amazonを使って、
重松さんがエッセイを書いた
「セカンドライン エッセイ100連発」を注文し、
今日の午前にメール便で届いた。
最初の1本目のエッセイで、重松さんはこのようなことを
述べている。
小数や分数を学ぶ以前の、割り算の初歩中の初歩
「7割る3は、2余り1」
僕の書いたお話には、必ず「余り」がついてしまう。
お話の表面に置いた出来事には、とりあえずケリがついても
根本的な問題は、残ったまま、という構図ばかりだ。
きれいに割り切れて、答えの出るお話はなかなか書けないし、
たぶん書こうともしていないのだろう。
「余り」つきの居心地の悪さにこそ、
いまの時代を生きるリアリティがあると思うから・・・
なんていうと、かっこつけすぎだけど。
(セカンドライン 1より抜粋)
余り・・・・・何をやるにしても、私たちの生活には、
この余りがついてくる気がする。
嬉しさの余りもあれば、悔しさの余りもある。
やりきれない思いが、余りとなって
次の計算(行動)の際に、
きれいに割れることを願って足されるのかもしれない。
「余り」つきのお話
書店に行って、重松さんの作品を探してみるのも
良いかもしれません。










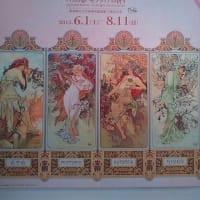









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます