のっけから私事で恐縮だが、今年の春、女性に告白して9日間でフラれるという体験をした。相手から一応のOKを貰って9日間、その間に2度デートをし、2度目のデートの帰りにフラれた。
そこがわからないからフラれたのだが、僕は今もって何故フラれたのか分かっていない。あれこれ予想は立てるが、解はない。
翌日、僕はウイスキーの瓶に口をつけ呑んでいた。当然、壊れた。道路で寝そべり、通りのガラスに接吻しまくり、友人を殴り、体液をバラ撒き、警官と揉めた。
その翌日以降に僕に残ったのは「悲しみが沈殿している」という感覚だった。
普段は表層に表れないのだが、ある瞬間、例えば似た後ろ姿を見たとき、急に胸の奥に悲しみが広がる。しばらくすると治まるが、また何かの拍子に胸中に表れる。
例えるならば、心の水槽に水と砂を入れているような感じだ。砂を入れ、一定時間経つと砂が水槽下部に沈殿する。何かで外部から刺激が加わると砂が舞い上がり、水槽は濁る。時間が経過すると砂は再び沈殿して水槽の水は透明になる。「悲しみが沈殿している」とはそんな状態だ。
不意に訪れ、誰かを侵すものを「毒」と呼ぶとして恋愛もその範疇に入れるなら僕は「毒」に侵されていた。
「名もなき毒」の物語には「毒」に侵された多くの人々が登場する。原因不明の喘息が止まらない子を持つ会社員、祖父を青酸毒物によって殺される高校生、父親を殺した嫌疑をかけられる母親、クビにしたアルバイトに振り回される社内報編集長、罪を犯した娘を持つ父親、土壌汚染の土地に住まざるおえない青年、事件に近づくライター、事件が近づいてくる主人公の元には様々な形で「毒」と出会ってしまった人々が集まる。
それも天災の類ではなく、「人間だけがもっている毒」に侵された人々がやってくる。「人間だけがもっている毒」とは人が生きる中で起こる歪みに基づく「毒」のことである。
「毒」には最初から原因や質のはっきりしたわかりやすいものもあるが、一方で”nameless poison”である場合も多い。「名もなき毒」を眼前にしたとき人はどうするであろうか。
個人によって対応は異なるが、共通してすることは「毒」に名前をつける作業である。誰の書いた何という小説かは忘れてしまったが、こんなくだりを覚えている。
人は恐怖を長持ちさせることはできない。対して不安はいつまでも残る。
恐怖は正体を知ってしまうとそれがどれだけ大きな恐怖であっても徐々に薄らいでゆく。不安はそれが漠然として全体が見えないものであるが故にいつまでも人の心に居座り蝕んでいく。
「毒」も同じで名前がない状態、つまり原因や質がわからない状態では小さな「毒」であっても人の心の中で如何様にも肥大していく。逆にそれがどれだけ強力な「毒」であっても受け手がそれを計量できてしまうとき威力は時間とともに弱まっていく。
だから、名札をつけるというプロセスが「毒」を受けた、または触れた人間には必要である。そうすることで己に安定を与えようとする。
しかし、「人だけがもっている毒」をその受け手が計量することは難しい。物事は容易にその全容を見せない複雑怪奇なものであるから。さらに自分のどんな「常識」や思考と整合性のとれない「毒」に出くわすことがある。
自分の理解を超えた「毒」に。それでも人は曲がりなりにも理解しなければ心の安定を保つことができないので、わかりの良い理由を自分で創作する。
僕の母親は僕に対して、僕が犯罪や悪いことして捕まったら絶対、母子家庭が原因だと周囲から言われると話したことがある。幸運にも僕は捕まった経験がなく、よって「母子家庭が悪い」と後ろ指さされた経験もない。
それは置いておいて、彼女の発言は社会がどういうものの見方をしがちかということを的確に表現している。
人は一つのレッテルで事象を評価してしまう傾向がある。それは楽であるし、何より納得しやすい。「毒」に対しても同じアプローチをとってしまう。
この作品のなかでは元アルバイト原田いづみが「あおぞら」編集部へ行う執拗な攻撃を編集長である園田瑛子は理解できずに苦しむ。
自分の管理能力が足りなかったからではないか。私に落ち度があったから原田いずみは人を傷つけようとするのではないか。生真面目な園田は「毒」の原因を自分に求める。
その後、原田の父親から娘の過去、そしていずみが家族を崩壊させた嘘の「暴露」について話を聞く。園田はいずみの父親が帰った後、こう呟く「彼女の情緒不安定の原因がそこ(暴露した話)あるんだとしたらどう?すっきりしない?」[( )内は論者]
園田は原田いずみが放つ「毒」の本質を納得したい為にわかりやすいところに寄りかかろうとする。この行為は人が得体の知れないものを眼前にしたときに見せる正直な反応といえる。
先にも書いたが、「毒」との向き合い方は一様でない。個人の複合的要素と密接に絡み合っている。経験、知識、思考、資質、経済力、時間などによって向き合い方は変化する。それが当事者ではなく第三者としての関わりであって同じである。
事件の方からやってきてしまう主人公は家族にたしなめられながら「お他人様」のことに深入りしてしまう。これは物語だからと身も蓋もないことを脇に置けば、事件が彼によってくるのは主人公のパーソナリティによるところは大きい。
しかし、同時に今多グループトップの娘婿であるというポジションが「お他人様」に首を突っ込む余裕を与えていることも見逃すことはできない。金銭面での不安が殆どないということは一つ理由となっている。
彼の行動力はその日の米代を稼ぐことに精一杯な人間には真似できない種類の好奇心に動かされているといっていい。この安定が後半、主人公が当事者となる新たな「毒」を持ち込む。
主人公のように事件からやってくる事は例外であるが、私たちが「毒」と向き合う時、生活の問題を抜きには考えられない。
漫画家の小林よしのりは雑誌「Quick Japan 67」での映画監督森達也との対談の中でオウム真理教と社会との関わりについて森が社会はオウム信者を異物として排除するだけで知ろうとしていないと言ったのに対して以下のような趣旨で反論している。
地域住民には生活がある。宗教はそれがイコール生活であるが、一般では仕事等で悩みながら暮らしている。そんな中で異物と化したものを知るべきだとか協調しろといわれても無理だ。
「生活」
私達は日々の営みがあり、生きている。当事者ならば受け入れざるおえないが、周囲に「毒」があるとしてそれにばかり目を向けているわけにはいかない。
デートもしたいし、映画も見たいし、欲しいものをいかに安く購入するかも考えたい。自分の生活を優先する中で社会にある「毒」を凝視する余裕は今の日本社会にはほとんどない。だから僕達は宮部が以下に書いたように過ごしている。
「不運にも毒に触れ、それに蝕まれてしまうとき以外、私達はいつも、この世の毒など考えないようにして生きている。日々を安らかに過ごすには、それしかほかに術がないから。」
私達は日頃、対岸の火事として社会の「毒」から微妙に目を背けて生きている。テレビの前で瞬間的には共感しても自分には関係ないこととして振舞う。「もしや」と思っても「うちに限って」と距離を置く。
しかし、これが根拠のない楽観であることは言うまでもない。宮部は作中の人物にこうも言わせている。
『「どこにいたって、怖いものや汚いものには遭遇する。完全に遮断することはできん」それが生きることだ』
僕はまた、かなりの確率で「毒」に出会う。生きるということがそうであるなら僕も例外ではない。僕がそういうものに遭遇したとき、これまたかなりの確率で逃げるはずだ。
それが何の解決にもならず、後のことを考えたら逃げることは向かう事よりずっと苦しくても僕は逃げる。逃げてしまうだろう。
そして、誰かを恨むかもしれない。なぜ自分だけがこんな目にあうのかと嘆き、同じ思いを他人にもさせたいと考えるはずだ。実際に誰かを「毒」で侵そうとするかもしれない。
今でさえ無意識に誰かに「毒」を撒いているかもしれないのだ。意識すれば簡単に放出できる。自身を停められるか、それは僕にはわからない。
「毒」とであったとき、あなたはどうだろうか。
最新の画像[もっと見る]










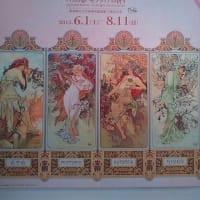









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます