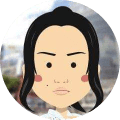私の師匠、はぎさんは大正生まれで現在102歳。施設に入っていますが、元気です。
旦那さんの故竹一さんも勿論紙すき職人でしたが、私が弟子入りしたときには引退されていたので、奥さんのはぎさんが師匠。
そのお二人の戦時中のお話をさせていただきます。
この話は竹一さん、はぎさんから聞いていて、何かの折に記者さんに話したところ、
中日新聞太田朗子さんが記事にしてくれました。
新聞記事を参照にした部分に、私が聞いた話を足しています。
二人は数軒隣のご近所さんで小さい頃から知る仲でした。
美濃の牧谷集落はほとんどが紙すきの家。
竹一さんの家もはぎさんの家も紙すき。
ところが結婚し新家となり、名古屋の工場に仕事が決まり引っ越す支度をしていました。はぎさんは都会にでれるとウキウキ。
ところが、竹一さんの兄が戦死。
紙すきの仕事(家)を残すためそのまま家を継ぎ紙すきを続けることに。紙すきが嫌になっていたはぎさんは、名古屋に行けなくなりとてもガッカリしたそうです。
※
竹一さんが招集されたのは1942年。激戦地のビルマに送られました。
結婚したばかりのはぎさんと、お腹に宿る長女を置いての出征でした。
苦しく辛い日々を生き、多くの戦友を失いました。45年八月アバロンで終戦を迎え、46年まで捕虜生活を送ることに。
場所ははっきりと覚えていないが、およそ二万人の日本人が収容されていたといいます。
いつ帰国出来るかわからない不安。
半年ほど経ったある日、日本人将校が訪れた。
将校は捕虜全員の職業を調べ、製紙業と書かれていた竹一さんら五人を集めて尋ねます。
「お前たち、ここで紙が漉けるか」
日本一の美濃和紙をすく職人の自負で
「何とかなると思います」答えた。
将校は便所で使う紙が欲しかったのだ。
五人は現地の人の案内で山に入り、使える原料や道具になりそうなモノを探して歩き回った。
トロロアオイの代わりには名もない植物のツル。原料を潰すのは米を潰す杵、簀桁を作り、風呂桶を舟に使った。
一番頭を悩ませたのは原料。
ふと、収容所に積んである段ボールが目に入った。繊維質がしっかりしていて丈夫な紙になりそう。
手伝い要員で増えた10人の兵士と共に段ボールを細かくちぎり、水に浸したのち杵でつき、ツルの抽出液を加え、ためすきの要領で漉くと茶色い紙が出来た。
15歳から紙すきを続ける職人だから出来た仕事だった。
出来上がった紙を将校は気に入り、竹一さんら五人は食事が将校扱いになったという。
日に二百枚ほどすき、幌に貼り付け乾かした。
使えたのは将校ら一部の人だけだったが、こっそり隠して自分たちで使ったと笑う。
帰国の日まで「無事に家に帰りたい」と祈り紙を漉き続けた。
竹一さんは月を見ると、ビルマで見た月を思い出して涙が出るとぼろぼろと涙を流しながら語る。
月はこの世に一つ、どこから見上げても同じ月。はぎさんから届いた長女の写真を見ながら、同じ月を見ているのに自分は家族と離れている。ビルマで月を見るたびに家族を想った。
「話せんことはいっぱいある。戦争なんかやっちゃあいかん」
戦争の残酷さを一時も忘れたことのない竹一さんの重い言葉だ。
と新聞記事はここまでの話でしたが、その後…
日本に帰れることになった竹一さん。
知らせを送ることが出来ず帰国の舟に乗った。汽車やバスを乗り継いで蕨生のバス停に。
ずいぶん長く離れていた為、家族がどういう反応をするか心配だったそうです。
バス停に降りた竹一さんを見つけた村の人。大急ぎで自転車をこぎ竹一さんの家に報告しにいきます。
知らせを聞いたお父さんは一言
「風呂を沸かせ!」
おもりの付いたかのような重い足を一歩また一歩と進める。家まではなだらかな坂道になっているのでより重い。
家では上を下への大騒ぎ。お風呂を沸かし、ご馳走の準備。まだかまだか。
上がったり下がったり、幾つかの曲がり道を過ぎ、最後の曲がり道を曲がると、お互いの姿が見える。
ようやく、ようやく帰ってきた。
それから家族で紙すきを続け、戦後和紙が売れない苦しいときも二人で乗り越え、夫婦共に永年紙を漉き続けました。子育てが一段落したのを機に息子のお嫁さんが紙すきの仕事を手伝ってくれることに。会社勤めをしていた息子さんが定年退職後従事。さらにその息子のお嫁さんと、本美濃紙を守り伝えています。
戦争には個人というものがなく、大きく人生を変えてしまう事が当たり前だったようですね。
今生きていること、続いてるものには実は誰かの物語が隠れているかもしれませんね。
竹一さんが亡くなられた12月、
家に二重の虹がかかりました。
とても安らかな、美しい顔でした。