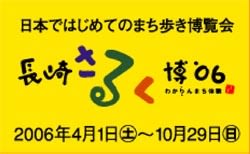
<長崎さるく博>
http://www.sarukuhaku.com/index.html
「長崎さるく博」は、日本ではじめてのまち歩き博覧会。
鎖国の日本で海外に開かれた、ただひとつのまち・長崎。
幕末の開国で西洋文化がどこより早く押し寄せたまち・長崎。
長い交流のなかで中国文化が深く息づくまち・長崎。
そんな長崎は、日本と中国と西洋<和華蘭>の文化が今なお色濃く混在する「わからんまち」です。

「さるく」とは、ぶらぶら歩くという長崎弁。「わからんまち長崎」をゆっくり歩いてみませんか。
長崎ならではの歴史や風物、かくされた謎をたんねんに紹介する42のコースと名物「さるくガイド」があなたを「わからんまち」にご案内します。
74もの特別うんちくコースやコースめぐりを楽しく彩る演出もたっぷり企画しました。見て、触れて、食べて、あなただけの発見をお楽しみください。
長崎のまち歩き。日本の「はじめて」を体験するまち歩きです。日本西端のまちがこんなに楽しいと気づく、エンタテイメントのまち歩きです。さあ、2006年の春夏秋は、日本ではじめてのまち歩き博覧会「長崎さるく博」へ。
長崎さるく博’06ってなぁ~に!
観光産業は二十一世紀の基幹産業
本誌の読者を考えて、数字を交えた話からはじめたい。
観光は、みなさんが想像されているよりも、わが国で重要な産業の一つになっている。国内の観光産業は二十一兆円(GDPの四・二%)もの消費市場を形成し、そのうち付加価値創出額は十一兆円(GDPの二・二%)に達している。付加価値額は自動車産業、電器等の一般機械産業に匹敵して、農林水産業より大きい。直接の雇用効果は百八十七万人(全雇用の二・八%)で、これは金融業や電器機械産業、食品産業と同規模で自動車産業よりずっと大きい。さらに、観光産業は他産業と違って完全に属地的であることが特徴で、製造工場はコストの安い立地を求めるが、長崎観光は長崎でしかできないという性格がある。観光産業は、地域の投資と雇用の効果を直接その地域にもたらす優れた地域性産業といえる。さらには、観光産業は他産業への波及効果が非常に大きく、日本では二次波及で四十九兆円にもなる。日本経済の外需依存に限界がみえている最中で、観光産業は内需を主導し、地域を先導する優れた産業であることは間違いないのだ。
しかし、世界においては観光産業の占める地位はさらに高い。市場は世界全体で約四兆ドル、世界中のGDPの一割を超えている。米国ではGDPの十一%、一・一兆ドルに達している。そしてこの市場は今後さらに拡大し、WTTC(世界旅行産業会議)では二〇一〇年に世界のGDPの一二・五%、雇用人口は全雇用者の一〇・九%になると予測している。この予測数値に日本の観光産業が追いつくならば、現在より二倍以上に市場規模が拡大することになる。
ところが、現実はこのような観光産業の世界的な潮流から日本はすっかり取り残されてしまっているようにみえる。
国内観光産業は、一九九三年にピークを迎え、二〇〇〇年以降は減少傾向が続き、二〇〇一年には宿泊観光客の平均宿泊日数が一・九三泊と二泊を下回った。市場が拡大する世界の流れと逆に国内の観光産業は縮小しているのだ。外国から日本へ入国する観光客も政府の施策で徐々に増加しているがまだ五百二十万人程度で、出国する観光客千六百万人と大きな差があり、年間の赤字は三兆円に達している。
長崎市の観光産業も同様で、市場は七百億円、市のGDP一・四兆円の五%を占めている重要な産業である。しかし観光入れ込み客数は一九九〇年の六百二十七万人をピークにして漸減状態で、近年は五百万人をわずかに上回っている程度になってしまった。「長崎よ、おまえもか」であるが、日本の観光産業はどこで間違ってしまったのだろうか。
都市観光の開発が急がれる
日本の観光産業の置かれている状況を説明するのがくどくなってしまったが、「長崎さるく博’06」の背景にこのような事情があることを、ひとまず理解していただきたい。
日本の観光市場が世界の流れと逆に沈滞気味であるのはなぜだろうか。長引く不景気を指摘することができるが、不景気は日本だけの状況ではなく、日本人の生活はむしろ観光消費に対してまだ十分な経済的余裕に恵まれている。現実に、千六百万人もの人々が海外で高額の消費を楽しんでいるではないか。日本の国内観光需要減退の主な原因はほかにあるに違いない。それは、ずばり、日本の観光が面白くないからだ。
第一に「名所旧跡温泉宴会観光バス」という、団体旅行主体の観光にはすっかり飽きてしまった。お仕着せの観光コースを駆け足で早回りするのは個人の知的興味を満たさない。
第二に、高コストである。観光シーズンに需要が偏って集中し、旅費も宿泊費も高くなる上に、テーマパーク型観光に見られるように“施設費用”がとても高くつく。
このような状況から抜け出すために、長期滞在型のスローツーリズムやグリーンツーリズムが模索されてきたが、近頃俄然取りざたされてきたのが都市観光のあり方である。都市観光とは都市にある日常の生活文化を楽しむ観光で、都市こそ観光の本来の対象であることは、海外旅行というとニューヨークやパリや上海やと都市へ出かけるのが普通であることでもわかる。私たちは、タイムズスクエアをほっつき歩いてニューヨーカー気分になったり、シャンゼリゼでパリジャンの気分を味わうためにそこへ行く。人人人であふれる大通りに先端中国都市のあり様を見に上海へ行く。そこに美術館や劇場があってそれを楽しむのはあくまでもプラスアルファの楽しみだ。
ところが、日本では「名所旧跡温泉宴会」から外れているせいか、都市観光の概念はいまでも明確でなく、優れた観光都市の代表である京都でも、清水寺と金閣寺と三十三間堂が三点セットだとタクシーの運転手さんに聞いたことがあるが、所詮、名所旧跡の施設観光に過ぎない。もう一つの日本を代表する観光都市である長崎でも、観光客はグラバー園と平和公園を訪ねてちゃんぽんか皿うどん食べてハウステンボスへ行ってしまう。状況はまったく同じで、長崎でも都市観光が成立しているとはとても言いがたい。
都市観光こそホンモノのまちの生活と文化をそっくりそのまま楽しむという観光の本道である。魅力的な生活様式や歴史、文化を持つ都市にとっては、都市観光の開発は新しい観光産業を確立する絶好のテーマなのではないだろうか。
そこで、日本ではじめてのまち歩きの博覧会「長崎さるく博」
ここまで背景説明をすると、なぜ「長崎さるく博」なのかはよく理解していただけたのではないだろうか。
「長崎さるく博」はパビリオンを建てて入場料を取って集客するという、あの博覧会ではない。パビリオンに替わるものが居留地であり、寺町であり、丸山であり、唐人屋敷であり、平和公園であり、浜町であり、新地であり、稲佐山であり、もちろんグラバー園であり、出島であり、新しい博物館であり、美術館である。〇六年には外海や野母崎にも範囲は広がる。
それらを楽しむ方法さえはっきりと提示できれば、観光客に長崎都市観光を存分に楽しんでもらえるのではないか。そのように考えて「さるく博」では、四十四の定番コース(「長崎遊・通コース」))を開発することにした。定番とはいつ来ても楽しめると言うことである。これらのコースがどれほど魅力にあふれるかは、そこに登場する人物が、坂本龍馬に高杉晋作、勝海舟、福沢諭吉、大隈重信、シーボルトにおタキさんにおイネさん、トーマス・グラバー、おツルさん、そして愛八姐さん、大浦お慶に稲佐おえいと、口先からぱらぱらこぼれるだけでもすごいキャスティングで、そこへもってきて、ぶらぶら節や龍踊りやマダムバタフライと絡めば、誰でも好奇心が膨らんではちきれそうになるでは。
「長崎通さるく」では、個性あふれるガイドさんがそれぞれのコースを言葉巧みに案内する。いずれ名物ガイドさんが生まれてガイド振りが評判になるのだろう。これらの企画を楽しむのに高額の入場料は要らない。安価な宿泊のしくみと組み合わせれば、従来の日本の高コスト観光から解放される。
定番コース以外でも、七十に及ぶ講座つきの特別企画「長崎学さるく」をつくるので、奥深く長崎の魅力を堪能してもらえる。プレイベントでは、唐人屋敷を探索して当時の復元料理を楽しむ企画や、しっぽく料理を食べながらお座敷遊びを楽しむなどの企画を提供したら、あっという間に定員超過した。当日は「長崎はこんげん楽しかと」と実感された男女市民の興奮が会場に満ちていた。
博覧会だから当然、イベントも盛りだくさんに企画している。全国からまち歩きに来てもらうウォーキングの大会や路面電車のサミットもある。オープニングや春・夏の大騒ぎイベントもある。グラバー園や出島では往時の雰囲気を再現して来園者にタイムスリップしてもらうことにした。二〇〇六年は、春から秋まで、既存の祭りも加わって長崎はまち中がヒートアップするはずだ。
しかし、イベントはあくまでも長崎のまちを盛り上げるための演出的な企画であって、今回の博覧会の本質ではない。本質は、まちを歩いてまちを楽しんでもらうことである。それには、博覧会の企画はそれとして、市民自らの日常活動で長崎のまちを盛り上げてもらうことがとても重要だ。
ここでみなさんにお願いがある。「長崎さるく博’06」に呼応して、元気に事業を展開してもらいたい。大売出しをやってもらいたい。販売や営業のキャンペーンをやっていただきたい。記念の商品を出してもらいたい。これを長崎市内の全事業者にお願いしたい。博覧会のロゴやマークやキャラクターは、無料でどうぞ。観光客はそんな元気な長崎を見に来るのだ。市民がやって市民が利益を享受する、それが「長崎さるく博’06」の真のねらいである。そして市民が自ら自分のまちを楽しむ。
市民が楽しまなくて観光客が楽しめるはずがない。そんな「長崎さるく博'06」をやりたい。(了)
*本稿は長崎法人会会報「いしだたみ」に掲載されたものです。
<<長崎さるく博>>公式ホームページより引用をさせていただきました。残りがあと2日という事で見学できませんでしたが、本当に残念です。是非皆さんもこのページを隅から隅まで、ズズーズーイとご覧になってください。
ご意見を!!!
http://www.sarukuhaku.com/index.html
「長崎さるく博」は、日本ではじめてのまち歩き博覧会。
鎖国の日本で海外に開かれた、ただひとつのまち・長崎。
幕末の開国で西洋文化がどこより早く押し寄せたまち・長崎。
長い交流のなかで中国文化が深く息づくまち・長崎。
そんな長崎は、日本と中国と西洋<和華蘭>の文化が今なお色濃く混在する「わからんまち」です。

「さるく」とは、ぶらぶら歩くという長崎弁。「わからんまち長崎」をゆっくり歩いてみませんか。
長崎ならではの歴史や風物、かくされた謎をたんねんに紹介する42のコースと名物「さるくガイド」があなたを「わからんまち」にご案内します。
74もの特別うんちくコースやコースめぐりを楽しく彩る演出もたっぷり企画しました。見て、触れて、食べて、あなただけの発見をお楽しみください。
長崎のまち歩き。日本の「はじめて」を体験するまち歩きです。日本西端のまちがこんなに楽しいと気づく、エンタテイメントのまち歩きです。さあ、2006年の春夏秋は、日本ではじめてのまち歩き博覧会「長崎さるく博」へ。
長崎さるく博’06ってなぁ~に!
観光産業は二十一世紀の基幹産業
本誌の読者を考えて、数字を交えた話からはじめたい。
観光は、みなさんが想像されているよりも、わが国で重要な産業の一つになっている。国内の観光産業は二十一兆円(GDPの四・二%)もの消費市場を形成し、そのうち付加価値創出額は十一兆円(GDPの二・二%)に達している。付加価値額は自動車産業、電器等の一般機械産業に匹敵して、農林水産業より大きい。直接の雇用効果は百八十七万人(全雇用の二・八%)で、これは金融業や電器機械産業、食品産業と同規模で自動車産業よりずっと大きい。さらに、観光産業は他産業と違って完全に属地的であることが特徴で、製造工場はコストの安い立地を求めるが、長崎観光は長崎でしかできないという性格がある。観光産業は、地域の投資と雇用の効果を直接その地域にもたらす優れた地域性産業といえる。さらには、観光産業は他産業への波及効果が非常に大きく、日本では二次波及で四十九兆円にもなる。日本経済の外需依存に限界がみえている最中で、観光産業は内需を主導し、地域を先導する優れた産業であることは間違いないのだ。
しかし、世界においては観光産業の占める地位はさらに高い。市場は世界全体で約四兆ドル、世界中のGDPの一割を超えている。米国ではGDPの十一%、一・一兆ドルに達している。そしてこの市場は今後さらに拡大し、WTTC(世界旅行産業会議)では二〇一〇年に世界のGDPの一二・五%、雇用人口は全雇用者の一〇・九%になると予測している。この予測数値に日本の観光産業が追いつくならば、現在より二倍以上に市場規模が拡大することになる。
ところが、現実はこのような観光産業の世界的な潮流から日本はすっかり取り残されてしまっているようにみえる。
国内観光産業は、一九九三年にピークを迎え、二〇〇〇年以降は減少傾向が続き、二〇〇一年には宿泊観光客の平均宿泊日数が一・九三泊と二泊を下回った。市場が拡大する世界の流れと逆に国内の観光産業は縮小しているのだ。外国から日本へ入国する観光客も政府の施策で徐々に増加しているがまだ五百二十万人程度で、出国する観光客千六百万人と大きな差があり、年間の赤字は三兆円に達している。
長崎市の観光産業も同様で、市場は七百億円、市のGDP一・四兆円の五%を占めている重要な産業である。しかし観光入れ込み客数は一九九〇年の六百二十七万人をピークにして漸減状態で、近年は五百万人をわずかに上回っている程度になってしまった。「長崎よ、おまえもか」であるが、日本の観光産業はどこで間違ってしまったのだろうか。
都市観光の開発が急がれる
日本の観光産業の置かれている状況を説明するのがくどくなってしまったが、「長崎さるく博’06」の背景にこのような事情があることを、ひとまず理解していただきたい。
日本の観光市場が世界の流れと逆に沈滞気味であるのはなぜだろうか。長引く不景気を指摘することができるが、不景気は日本だけの状況ではなく、日本人の生活はむしろ観光消費に対してまだ十分な経済的余裕に恵まれている。現実に、千六百万人もの人々が海外で高額の消費を楽しんでいるではないか。日本の国内観光需要減退の主な原因はほかにあるに違いない。それは、ずばり、日本の観光が面白くないからだ。
第一に「名所旧跡温泉宴会観光バス」という、団体旅行主体の観光にはすっかり飽きてしまった。お仕着せの観光コースを駆け足で早回りするのは個人の知的興味を満たさない。
第二に、高コストである。観光シーズンに需要が偏って集中し、旅費も宿泊費も高くなる上に、テーマパーク型観光に見られるように“施設費用”がとても高くつく。
このような状況から抜け出すために、長期滞在型のスローツーリズムやグリーンツーリズムが模索されてきたが、近頃俄然取りざたされてきたのが都市観光のあり方である。都市観光とは都市にある日常の生活文化を楽しむ観光で、都市こそ観光の本来の対象であることは、海外旅行というとニューヨークやパリや上海やと都市へ出かけるのが普通であることでもわかる。私たちは、タイムズスクエアをほっつき歩いてニューヨーカー気分になったり、シャンゼリゼでパリジャンの気分を味わうためにそこへ行く。人人人であふれる大通りに先端中国都市のあり様を見に上海へ行く。そこに美術館や劇場があってそれを楽しむのはあくまでもプラスアルファの楽しみだ。
ところが、日本では「名所旧跡温泉宴会」から外れているせいか、都市観光の概念はいまでも明確でなく、優れた観光都市の代表である京都でも、清水寺と金閣寺と三十三間堂が三点セットだとタクシーの運転手さんに聞いたことがあるが、所詮、名所旧跡の施設観光に過ぎない。もう一つの日本を代表する観光都市である長崎でも、観光客はグラバー園と平和公園を訪ねてちゃんぽんか皿うどん食べてハウステンボスへ行ってしまう。状況はまったく同じで、長崎でも都市観光が成立しているとはとても言いがたい。
都市観光こそホンモノのまちの生活と文化をそっくりそのまま楽しむという観光の本道である。魅力的な生活様式や歴史、文化を持つ都市にとっては、都市観光の開発は新しい観光産業を確立する絶好のテーマなのではないだろうか。
そこで、日本ではじめてのまち歩きの博覧会「長崎さるく博」
ここまで背景説明をすると、なぜ「長崎さるく博」なのかはよく理解していただけたのではないだろうか。
「長崎さるく博」はパビリオンを建てて入場料を取って集客するという、あの博覧会ではない。パビリオンに替わるものが居留地であり、寺町であり、丸山であり、唐人屋敷であり、平和公園であり、浜町であり、新地であり、稲佐山であり、もちろんグラバー園であり、出島であり、新しい博物館であり、美術館である。〇六年には外海や野母崎にも範囲は広がる。
それらを楽しむ方法さえはっきりと提示できれば、観光客に長崎都市観光を存分に楽しんでもらえるのではないか。そのように考えて「さるく博」では、四十四の定番コース(「長崎遊・通コース」))を開発することにした。定番とはいつ来ても楽しめると言うことである。これらのコースがどれほど魅力にあふれるかは、そこに登場する人物が、坂本龍馬に高杉晋作、勝海舟、福沢諭吉、大隈重信、シーボルトにおタキさんにおイネさん、トーマス・グラバー、おツルさん、そして愛八姐さん、大浦お慶に稲佐おえいと、口先からぱらぱらこぼれるだけでもすごいキャスティングで、そこへもってきて、ぶらぶら節や龍踊りやマダムバタフライと絡めば、誰でも好奇心が膨らんではちきれそうになるでは。
「長崎通さるく」では、個性あふれるガイドさんがそれぞれのコースを言葉巧みに案内する。いずれ名物ガイドさんが生まれてガイド振りが評判になるのだろう。これらの企画を楽しむのに高額の入場料は要らない。安価な宿泊のしくみと組み合わせれば、従来の日本の高コスト観光から解放される。
定番コース以外でも、七十に及ぶ講座つきの特別企画「長崎学さるく」をつくるので、奥深く長崎の魅力を堪能してもらえる。プレイベントでは、唐人屋敷を探索して当時の復元料理を楽しむ企画や、しっぽく料理を食べながらお座敷遊びを楽しむなどの企画を提供したら、あっという間に定員超過した。当日は「長崎はこんげん楽しかと」と実感された男女市民の興奮が会場に満ちていた。
博覧会だから当然、イベントも盛りだくさんに企画している。全国からまち歩きに来てもらうウォーキングの大会や路面電車のサミットもある。オープニングや春・夏の大騒ぎイベントもある。グラバー園や出島では往時の雰囲気を再現して来園者にタイムスリップしてもらうことにした。二〇〇六年は、春から秋まで、既存の祭りも加わって長崎はまち中がヒートアップするはずだ。
しかし、イベントはあくまでも長崎のまちを盛り上げるための演出的な企画であって、今回の博覧会の本質ではない。本質は、まちを歩いてまちを楽しんでもらうことである。それには、博覧会の企画はそれとして、市民自らの日常活動で長崎のまちを盛り上げてもらうことがとても重要だ。
ここでみなさんにお願いがある。「長崎さるく博’06」に呼応して、元気に事業を展開してもらいたい。大売出しをやってもらいたい。販売や営業のキャンペーンをやっていただきたい。記念の商品を出してもらいたい。これを長崎市内の全事業者にお願いしたい。博覧会のロゴやマークやキャラクターは、無料でどうぞ。観光客はそんな元気な長崎を見に来るのだ。市民がやって市民が利益を享受する、それが「長崎さるく博’06」の真のねらいである。そして市民が自ら自分のまちを楽しむ。
市民が楽しまなくて観光客が楽しめるはずがない。そんな「長崎さるく博'06」をやりたい。(了)
*本稿は長崎法人会会報「いしだたみ」に掲載されたものです。
<<長崎さるく博>>公式ホームページより引用をさせていただきました。残りがあと2日という事で見学できませんでしたが、本当に残念です。是非皆さんもこのページを隅から隅まで、ズズーズーイとご覧になってください。
ご意見を!!!






















観光産業も経済の一部で有ります。最大需要期には、また最大需要期の日祝日前は、確かに高価格に成ります。しかし、オフシーズンには、価格も下がり、ホントにこんな・・・・・と云われる位の価格にも成ります。此の最大原因は、人件費で有ります。最大期の人材を抱えていれば、オフが持たずに崩壊します。しかし、オフの人材で有れば、最大需要をクリアー出来ません。また最大需要期には、人材確保の為の経費もかかり、こうした諸々の物が販売価格に乗っかるわけです。しかし、お客様から見れば、良いときに、安く行きたい、に成るのは、当然の事で有ります。
では、どうして此の問題をクリアーするのか・・・・・と云いますと、オフを最大需要期同等程度に引っ張り上げる事で有ります。地方都市のビジネスホテル・旅館は、地方出張や、そこそこの観光などで、年間70%上下10%程度で廻っている所が少なくありません。
しかし此の点、奈良は、どうでしょう?本日正倉院展が開催され、しかも土曜日・・・・・道路は、びっしりです。しかし、正月が明ければ、奈良県庁の前など、人っ子一人居ないゴーストタウン状態で有ります。此の問題を解決しない限り、根本的に奈良地区は浮上しません。サービス・商品を売りにしたかったら、官・民共同で知恵を出すべきでしょう。自分は、大川前市長の「温泉」などは、一つの解決策で有った様な気がします。旧跡の中の温泉は、結構売りに成りますし、「温泉」を使った街作りも可能です。
無論、「温泉」だけに限って云える事では無いですが、まず、最大期と最小期の格差を如何にして埋めていくか、を考える事が得策で有る、と信じます。格差が無くなれば、宿泊単価も中庸で落ち着いて、割高感も無くなってきます。労働者も安定した雇用が生まれてくるので、定住人口も増加します。此に伴って、税収も増え、市役所も楽になりますよ。
鳩首会議で、頭から血が出る位考えましょう。